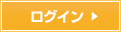サプリ研究の第一人者、蒲原先生の公式ブログです。 |
|
| ドイツのヘルスシステムでのハーブの重要性 |
今月のヘルスサービス研究の専門ジャーナル(電子版)に、ドイツのヘルスケアシステムにおけるハーブの重要性や利用率、背景因子を調べた調査研究が、ドイツのグループから報告されていました。 (BMC Health Serv Res 2019.) ハーブの利用率は世界的に増加しています。 ヨーロッパ、特にドイツでは、ハーブサプリメントについての研究が行われてきており、 OTC医薬品としても活用されてきました。 今回の研究では、 ドイツの一般人口において、ハーブの利用状況、利用者の特徴、ハーブ利用に影響する因子が調べられました。 具体的には、 ドイツでのオンライン調査として、 2906名の参加者から、 ハーブの利用が調べられました。 解析の結果、 ハーブの利用率は非常に高く、 ・過去12か月でハーブを使用した群:75.4% ・過去12か月ではハーブを使用しなかったが、これまでに利用した群:11.3%、 ・今までハーブを使用しなかった群:13.3% でした。 ハーブの利用おいて、セルフメディケーションは一般的な実践であり、 同時にハーブの利用者は、 医師に知らせることはなく、 知識は十分とは考えておらず、 インターネットを主な情報源としていました。 ハーブ利用の目的となる症状や病気、および、有用性に関する認識は、次のようになっています。 風邪やインフルエンザ 1441名 65.8%が利用、 効果ない:2.3%%、一定の効果あり:56.8% よく効いた:40.9% 呼吸器系の症状 1355名 61.8%が利用、 (有用性の内訳;2.4 49.4 48.2) 消化器系症状 1048名47.8% (有用性の内訳;2.0 44.8 53.2) 睡眠障害 655名29.9% (15.7 53.4 30.9) 不安 500名22.8% (13.6 54.4 32.0) 過去12か月のハーブ利用者の特徴は、 女性、 高学歴、 個人保険に加入、 仕事に就いている、 健康志向の高いライフスタイル でした。 特定の社会人口統計学的および健康関連の因子も、ハーブ利用および非利用にある程度、影響はしますが限定的でした。 以上、 今回の調査研究から、 ハーブ利用がドイツのヘルスケアシステムで重要な役割を果たしていることが示唆されます。 課題として、 セルフケアが主体であり、 医師とのコミュニケーション不足なども示唆されます。 論文著者らは、 ドイツでのハーブの利用率が高いことから、 医療従事者やヘルスケアサービスの提供者は、これらの課題を認識するべきであると考察しています。 DHCでは、ハーブサプリメントの適正使用に関するエビデンスをまとめて出版しています。 サプリメントと医薬品の相互作用ハンドブック―機能性食品の適正使用情報  ------------------------------------------------------------------ DHCは、トータルヘルスケア企業として地方自治体と連携し、健康づくり事業に取り組んでいます。ふるさと納税にも協力し、地方創生を支援しています。 地域での健康長寿社会の実現に、DHCとして貢献できるように努めています。 ビタミンMが認知症と脳卒中を防ぐ!―日本人が知らない健康長寿のための葉酸の効果 ------------------------------------------------------------------ |
| posted at 23:54 | この記事のURL |
| この記事のURL |
| http://www.dhcblog.com/kamohara/archive/5000 |
|