風唄 本編12 [2008年06月19日(木)]
「兄貴」
静かに、白い顔がゆっくりと振り返る。顔色に似合わず、その口元は大体機嫌よく微笑みが刻まれている。
「ん?」
北斗を見留めた今も、それは変わらない。
兄ならきっと分かってくれるだろうという確信は、微笑む顔を見て何故か不安へと変化していった。
「あぁ、北斗。読みたかった本は見つかった?」
「うん、まあ」
先程あんな会話を交わした後。切り出す事が、こんなにも難しいなんて。
「あのさ」
意を決して、なんとか言葉を紡いだその時だった。
「たっだいまーん!!!」
廊下で話す2人の丁度真ん中にあった扉が、盛大な音を立てて開いた。
大声且つ場の空気を読まずに闖入してきたのは、北斗のすぐ上の姉だった。
我が家の女は、どうしてこうも強いのだろうか。
体中に渦巻いていた緊張はとりあえずどこかへ消え、呆れと脱力感で姉を見るしかなかった。
「…………」
「おかえり。遅かったね」
兄は、そんな時でも笑顔で彼女を出迎える。
「お兄、ただいま。何、北斗ってばそんな目であたしを見て。そんなにお姉様に会いたかった?」
そしてこの姉は、何かと因縁を付けては北斗を困らせるのだ。小さい頃はよく泣かされていたものだ。
北斗は彼女の言葉に応じず、出来るだけ視線を逸らし後ずさった。それを見た兄は口元に手を当て、声を殺して笑っている。
「飲んできたな…」
間違いない。姉の頬はいつもより若干赤く染まっており、目はきちんと開けられていない。
決め手は姉が乱入してきた時から漂い始めた、あの独特の匂いだ。
姉は酒が入ると益々絡んでくる。ターゲットは勿論北斗である。その質の悪さに、北斗はいつも閉口するのだ。
「そんな事どうだっていいのよ。会いたかったの?会いたくなかったの〜〜?」
据わった目で一歩ずつ近づいてくる。勿論答える気などさらさらない。
「な、」
どうしたものかと考える暇もなく、姉は突然北斗に突撃してきた。とてもじゃないが、避けられる隙はなかった。
「北斗くんってば〜〜、お姉さんに甘えたいならそう言いなさーーーい!」
「!?」
女性にしてはなかなか長身の姉に、一瞬で頭を彼女の脇腹に固定された。バランスを崩し、中腰になった体は上手く力が入らない。
「離せ!触るな!!」
高笑いしながら北斗の頭を掻き回す姉に、くぐもったその声は聞こえないようだ。
耳にのあたりに柔らかな何かが押し当てられるが、こんな姉じゃ嬉しくもなんともない。寧ろ迷惑だ。
北斗が己の不運を心の中で嘆いた時、兄が笑いを堪えながら助け船を出した。
「まって、ちょっと、その辺にしといてあげて。北斗は僕に話があるみたいなんだ」
よっぽど笑っていたのか、息も絶え絶えの兄の声が聞こえた。
「そーだ!だから離せよ!」
「何よぉ。何の話ぃ?」
北斗の言葉はどうやら無視されたらしい。そのままの格好で、腕の力が緩められる気配はない。
「男兄弟の会話だよ。決まってるじゃないか」
兄は呼吸も整ったらしく、いつものペースで柔らかく話す。北斗の視界は今、床しか見えないが、その顔は微笑んでいるに違いない。
彼が微笑んでる時は、大体が本気で楽しんでいる。常に笑っているイメージの兄は、簡単に言えば笑い上戸なのだ。
はいはい、と姉は半ば呆れたように北斗の首に掛かっていた腕を外し、あれだけしつこく絡んだ事が嘘のように踵を返した。
これぞまさに、鶴の一声。
「猥談なら部屋でやんなさいよ」
「おい!!」
片手をひらひらさせながら去って行く姉。最後に爆弾を落として帰っていった。
「本当に何でうちの女達って…」
北斗の呟きに、兄の笑い声はいよいよ本気のものとなり、目尻には涙が滲んでいる。
それを人差し指で拭うと、息も絶え絶え、彼は言った。
「それじゃあ、部屋に行こっか」
さっきの大笑いといい、今日の兄は調子も機嫌もいいようだ。
普段より若干早い動きで北斗を自室に促し座らせると、自分も寝台に腰を下ろした。
「それで、どうしたの?」
うん、と北斗は頷いた。もしかしたら、今から自分がやろうとしているのは家族への裏切り行為かもしれない。
そう思うと、なかなか切り出せなかった。
「あれっ?本当に好きな娘でもできたの?」
「違う!」
兄の目が少しだけ輝いたような、気のせいか?
「そっか」
輝いた割には、さして落胆した様子は見られない。
どこまで本気なのか、時々北斗でさえも読めないときがあるが、兄はこれでなかなか冗談好きなのだ。
「兄貴には言おうと思って。驚かないで聞いて欲しい」
「うん。あんまり驚くと胸が痛くなるから、驚かないよ」
「…………」
「どうしたの?」
「いや…」
我が家の強者は、女だけではないかもしれないと、今更ながら感じる北斗であった。
そんな兄のいつもと変わらない様子だったから、北斗は自分でも驚く程、その言葉はするりと流れ出た。
それこそが兄の狙いだと、北斗は見抜けなかった。
「俺、旅に出ようと思う」
しばしの沈黙。
北斗が見る兄は、暖かい茶を口元に運んでいる。
「そう」
静かな返事だった。
「帰りはいつになるかわからない。帰ってこれるかもわからない…けど、俺は行くって決めたんだ」
表面に息を吹きかけ、熱を飛ばしている。一口飲み下すと、兄は微笑んだ。
「そう」
北斗は安堵に包まれた。
「旅立ちは、いつ?」
「街を出るのは夜明け。でも合流しなければならない奴がいるから、もう家を出ようと思う」
コトリ、傍らにカップを置いた。あんなに湯気が立っていたのに、もう飲み干したらしい。
「それで…」
「大丈夫。みんなには僕からうまく言っておく。それが、僕に教えてくれた一番の理由だろ?」
兄が下の兄弟に慕われてるのは、こういったところにあるのだと思う。二歩も三歩も先を読んでいて、北斗は敵わないと心から感じる。
「…ありがとう」
「気をつけて」
「ああ」
何も聞かず、何も言わず。
神話に登場する神々が本当にいるのなら、何故、と問いたい。
こんなにも人の心を汲み取ことに長ける兄に、どうして脆弱な肉体しか与えなかったのか。
陽の光を浴びるに相応しい人間を、神は見抜けなかったのだろうか。
「兄貴は…俺が逃げてるって思わないのか?」
「思わないなぁ」
即答が嬉しかった。そう思ってくれる理由は聞かない。
「ね、北斗。僕なら大丈夫だから、心配しないで、自分と仲間の事だけ考えて、進むんだよ」
ぽん、と肩に手を置く兄に遠い昔がフラッシュバックした。
幼い頃にもこうして何かある度に、半ベソをかいた北斗を少し歳の離れたこの兄が肩や背中に手を置いて宥めてくれていた。
「これから兄貴には頭が上がらないな」
にっこり微笑んだ兄が返した。
「恩は高く売っとかないと」
漆黒に浮かぶ月や星が身を潜め、藍色から紫へ、そして清々しい空気と共にオレンジに水平線を染め始めた。
岩窟から少し歩けば、夕焼けも、朝焼けも見ることができるのが岬の良いところだ。
「オレあそこの紫とオレンジの間の色が好き」
颯輝はかつてを思い出し、懐かしい思いと共にその場所を指し示した。
「俺は…もう少し上だな。颯輝よりほんの少し、上」
「やっぱ、似てるのは顔だけなんだなー。大星はやっと藍色になった頃が好きだって言ってた」
大星の言っていた色はもうかなり後方に追いやられていて、振り向かないと見ることができない。でも今は、今だけは、それは見ない。後ろを振り向かずにいたい。
「駒馳はな、もっともっと太陽近く。太陽が登る直前の水平線だって」
「シスコン」
「なんだよ!」
「お、返事したな」
「違う!そういう意味じゃ…」
「ほら、登るぞ」
気持ちが急くのか、早起きな小鳥に起こされたのか、東の空が大星の好きな色に変わる頃、颯輝は目が覚めた。
すると、いてもたっても居られない程、旅立ち前に日の出を見たくなった。
あの後戻ってきた北斗もすぐさま眠りについた。それなのに彼の寝起きは酷かった。揺さぶり叩き起こし、感服しつつも引き摺るようにしてここまで出てきた。
「うん、きれいだ」
「俺は眠い」
まだ言うか!と、颯輝は北斗に一瞬目をやるが、眠いと悪態をつきながらも、うっすら開けた瞼から彼はしっかり朝焼けを見ていた。
朝焼けにその瞳が不思議な色に染まっている。
穏やかな気分だった。
「大丈夫。きっと」
「…ああ」
オレンジ色が、眩しく岬を照らす。妹の好きな色が、2人を照らす。
不安は尽きない。それでも颯輝の心は希望で満ちていた。
古き友と新たな友が見つけてくれた突破口は、確実に颯輝の向かう未来に続いている自信があった。
段々と白に染まりゆく水平線は、希望の色だ。
頬を撫でる風が、足元の小さな花の綿毛を浚っていった。
静かに、白い顔がゆっくりと振り返る。顔色に似合わず、その口元は大体機嫌よく微笑みが刻まれている。
「ん?」
北斗を見留めた今も、それは変わらない。
兄ならきっと分かってくれるだろうという確信は、微笑む顔を見て何故か不安へと変化していった。
「あぁ、北斗。読みたかった本は見つかった?」
「うん、まあ」
先程あんな会話を交わした後。切り出す事が、こんなにも難しいなんて。
「あのさ」
意を決して、なんとか言葉を紡いだその時だった。
「たっだいまーん!!!」
廊下で話す2人の丁度真ん中にあった扉が、盛大な音を立てて開いた。
大声且つ場の空気を読まずに闖入してきたのは、北斗のすぐ上の姉だった。
我が家の女は、どうしてこうも強いのだろうか。
体中に渦巻いていた緊張はとりあえずどこかへ消え、呆れと脱力感で姉を見るしかなかった。
「…………」
「おかえり。遅かったね」
兄は、そんな時でも笑顔で彼女を出迎える。
「お兄、ただいま。何、北斗ってばそんな目であたしを見て。そんなにお姉様に会いたかった?」
そしてこの姉は、何かと因縁を付けては北斗を困らせるのだ。小さい頃はよく泣かされていたものだ。
北斗は彼女の言葉に応じず、出来るだけ視線を逸らし後ずさった。それを見た兄は口元に手を当て、声を殺して笑っている。
「飲んできたな…」
間違いない。姉の頬はいつもより若干赤く染まっており、目はきちんと開けられていない。
決め手は姉が乱入してきた時から漂い始めた、あの独特の匂いだ。
姉は酒が入ると益々絡んでくる。ターゲットは勿論北斗である。その質の悪さに、北斗はいつも閉口するのだ。
「そんな事どうだっていいのよ。会いたかったの?会いたくなかったの〜〜?」
据わった目で一歩ずつ近づいてくる。勿論答える気などさらさらない。
「な、」
どうしたものかと考える暇もなく、姉は突然北斗に突撃してきた。とてもじゃないが、避けられる隙はなかった。
「北斗くんってば〜〜、お姉さんに甘えたいならそう言いなさーーーい!」
「!?」
女性にしてはなかなか長身の姉に、一瞬で頭を彼女の脇腹に固定された。バランスを崩し、中腰になった体は上手く力が入らない。
「離せ!触るな!!」
高笑いしながら北斗の頭を掻き回す姉に、くぐもったその声は聞こえないようだ。
耳にのあたりに柔らかな何かが押し当てられるが、こんな姉じゃ嬉しくもなんともない。寧ろ迷惑だ。
北斗が己の不運を心の中で嘆いた時、兄が笑いを堪えながら助け船を出した。
「まって、ちょっと、その辺にしといてあげて。北斗は僕に話があるみたいなんだ」
よっぽど笑っていたのか、息も絶え絶えの兄の声が聞こえた。
「そーだ!だから離せよ!」
「何よぉ。何の話ぃ?」
北斗の言葉はどうやら無視されたらしい。そのままの格好で、腕の力が緩められる気配はない。
「男兄弟の会話だよ。決まってるじゃないか」
兄は呼吸も整ったらしく、いつものペースで柔らかく話す。北斗の視界は今、床しか見えないが、その顔は微笑んでいるに違いない。
彼が微笑んでる時は、大体が本気で楽しんでいる。常に笑っているイメージの兄は、簡単に言えば笑い上戸なのだ。
はいはい、と姉は半ば呆れたように北斗の首に掛かっていた腕を外し、あれだけしつこく絡んだ事が嘘のように踵を返した。
これぞまさに、鶴の一声。
「猥談なら部屋でやんなさいよ」
「おい!!」
片手をひらひらさせながら去って行く姉。最後に爆弾を落として帰っていった。
「本当に何でうちの女達って…」
北斗の呟きに、兄の笑い声はいよいよ本気のものとなり、目尻には涙が滲んでいる。
それを人差し指で拭うと、息も絶え絶え、彼は言った。
「それじゃあ、部屋に行こっか」
さっきの大笑いといい、今日の兄は調子も機嫌もいいようだ。
普段より若干早い動きで北斗を自室に促し座らせると、自分も寝台に腰を下ろした。
「それで、どうしたの?」
うん、と北斗は頷いた。もしかしたら、今から自分がやろうとしているのは家族への裏切り行為かもしれない。
そう思うと、なかなか切り出せなかった。
「あれっ?本当に好きな娘でもできたの?」
「違う!」
兄の目が少しだけ輝いたような、気のせいか?
「そっか」
輝いた割には、さして落胆した様子は見られない。
どこまで本気なのか、時々北斗でさえも読めないときがあるが、兄はこれでなかなか冗談好きなのだ。
「兄貴には言おうと思って。驚かないで聞いて欲しい」
「うん。あんまり驚くと胸が痛くなるから、驚かないよ」
「…………」
「どうしたの?」
「いや…」
我が家の強者は、女だけではないかもしれないと、今更ながら感じる北斗であった。
そんな兄のいつもと変わらない様子だったから、北斗は自分でも驚く程、その言葉はするりと流れ出た。
それこそが兄の狙いだと、北斗は見抜けなかった。
「俺、旅に出ようと思う」
しばしの沈黙。
北斗が見る兄は、暖かい茶を口元に運んでいる。
「そう」
静かな返事だった。
「帰りはいつになるかわからない。帰ってこれるかもわからない…けど、俺は行くって決めたんだ」
表面に息を吹きかけ、熱を飛ばしている。一口飲み下すと、兄は微笑んだ。
「そう」
北斗は安堵に包まれた。
「旅立ちは、いつ?」
「街を出るのは夜明け。でも合流しなければならない奴がいるから、もう家を出ようと思う」
コトリ、傍らにカップを置いた。あんなに湯気が立っていたのに、もう飲み干したらしい。
「それで…」
「大丈夫。みんなには僕からうまく言っておく。それが、僕に教えてくれた一番の理由だろ?」
兄が下の兄弟に慕われてるのは、こういったところにあるのだと思う。二歩も三歩も先を読んでいて、北斗は敵わないと心から感じる。
「…ありがとう」
「気をつけて」
「ああ」
何も聞かず、何も言わず。
神話に登場する神々が本当にいるのなら、何故、と問いたい。
こんなにも人の心を汲み取ことに長ける兄に、どうして脆弱な肉体しか与えなかったのか。
陽の光を浴びるに相応しい人間を、神は見抜けなかったのだろうか。
「兄貴は…俺が逃げてるって思わないのか?」
「思わないなぁ」
即答が嬉しかった。そう思ってくれる理由は聞かない。
「ね、北斗。僕なら大丈夫だから、心配しないで、自分と仲間の事だけ考えて、進むんだよ」
ぽん、と肩に手を置く兄に遠い昔がフラッシュバックした。
幼い頃にもこうして何かある度に、半ベソをかいた北斗を少し歳の離れたこの兄が肩や背中に手を置いて宥めてくれていた。
「これから兄貴には頭が上がらないな」
にっこり微笑んだ兄が返した。
「恩は高く売っとかないと」
漆黒に浮かぶ月や星が身を潜め、藍色から紫へ、そして清々しい空気と共にオレンジに水平線を染め始めた。
岩窟から少し歩けば、夕焼けも、朝焼けも見ることができるのが岬の良いところだ。
「オレあそこの紫とオレンジの間の色が好き」
颯輝はかつてを思い出し、懐かしい思いと共にその場所を指し示した。
「俺は…もう少し上だな。颯輝よりほんの少し、上」
「やっぱ、似てるのは顔だけなんだなー。大星はやっと藍色になった頃が好きだって言ってた」
大星の言っていた色はもうかなり後方に追いやられていて、振り向かないと見ることができない。でも今は、今だけは、それは見ない。後ろを振り向かずにいたい。
「駒馳はな、もっともっと太陽近く。太陽が登る直前の水平線だって」
「シスコン」
「なんだよ!」
「お、返事したな」
「違う!そういう意味じゃ…」
「ほら、登るぞ」
気持ちが急くのか、早起きな小鳥に起こされたのか、東の空が大星の好きな色に変わる頃、颯輝は目が覚めた。
すると、いてもたっても居られない程、旅立ち前に日の出を見たくなった。
あの後戻ってきた北斗もすぐさま眠りについた。それなのに彼の寝起きは酷かった。揺さぶり叩き起こし、感服しつつも引き摺るようにしてここまで出てきた。
「うん、きれいだ」
「俺は眠い」
まだ言うか!と、颯輝は北斗に一瞬目をやるが、眠いと悪態をつきながらも、うっすら開けた瞼から彼はしっかり朝焼けを見ていた。
朝焼けにその瞳が不思議な色に染まっている。
穏やかな気分だった。
「大丈夫。きっと」
「…ああ」
オレンジ色が、眩しく岬を照らす。妹の好きな色が、2人を照らす。
不安は尽きない。それでも颯輝の心は希望で満ちていた。
古き友と新たな友が見つけてくれた突破口は、確実に颯輝の向かう未来に続いている自信があった。
段々と白に染まりゆく水平線は、希望の色だ。
頬を撫でる風が、足元の小さな花の綿毛を浚っていった。
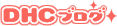


URL http://www.dhcblog.com/arianotonoburoguhoshi/tb_ping/875