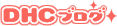風唄 本編15 [2008年06月19日(木)]
颯輝は拳を握りしめた。妹の消息が分からなくなってから大星が突き止めるまで、自分は少しでも強くなれるよう努力したのだ。その時、自分が師と慕う人物に教えられた武器は、双剣。旅の早い段階で必要になると考えてはいたが、ジノはそれすら見抜いていたようだ。
「…おい、傷大丈夫か?」
女性達の姿が砂塵で見えなくなってから、北斗がその傷を確認するように跪いた。傷口に手を伸ばすが、指先が小刻みに震えている。初のバトルは、体よりも精神にダメージを残したようだ。
「平気平気。ってかあの人たち、何だったんだろうなぁ」
「さあ。あまり感じ良くは無かった。一応、出血が酷い所は縛っておくぞ」
そんなに激しく出血している訳ではないので大丈夫だろうと言いながら北斗は平静を装い、縛るものを探した。
「ぇえー、魔法かけてくれよ。一発で治るだろ」
「………それだけ元気なら大丈夫そうだ。マックス、首のそれ、貸してくれんか」
傍で自分の傷口を舐めていたマックスは自分が呼ばれたことに気付いて起き上がると、言葉の意味を理解しているのだろう、
ひょこひょこと近寄ってきた。少し辛そうではあるが、彼もまた重傷ではないようで胸を撫で下ろした。
北斗はマックスが首輪代わりにしていた帯状のものに手を伸ばす。応急処置には丁度良いだろう。しかし、間の抜けた場違いに大きな声が彼の手を止めた。
「あぁっと、それ!」
忘れてた、と慌てたように四つん這いでマックスに近づき、そしてその首の布をいじり始めた。そんなに元気なら傷を縛る必要もないみたいだな、と北斗は安堵すると同時に、行動が突拍子もない颯輝に小さくため息をついた。結び目を摘んだり引っ張ったりして、それを取ろうとしている。マックスは大人しくしたまま上を向いているが颯輝の手はもたついていて、何だか難儀しているようだ。
北斗は敢えて手助けをせず、黙ってそれを見守った。
…いつの間にか解くことをあきらめたらしい颯輝が無理矢理マックスの頭を通そうとしているまで。
マックスの顔が変形している。されたい放題のマックスは少しもがくだけで、それでも爪をひっこめたままというところが健気である。
「これぜってーおかしい!」
「馬鹿、マックスの首が締まるだろ。貸せ」
少し強引に小さな体躯を引き寄せる。颯輝があちらで悪態をついているが気にせずその毛並みを撫でる。可哀想に、苦しかったろう。
北斗はその首にかかる布を確認した。
「お前、よっぽど不器用なんじゃあるまいか」
「ちが…それマジ変なんだって!」
それは予想よりずっとゆるく結ばれてる上、結び方も大したものではない。
拍子抜けした気分だったが、颯輝の言ってる意味がわからない。変、とは?
しかしそれはすぐに理解できた。
北斗がその結び目に指を触れた途端……本当に触れただけで、それはいとも簡単にするりと解け、北斗の手のひらに落下した。
「…………」
何が起きたのか。取り敢えずそれを手に乗せたまま、颯輝を見遣る。彼も憮然としたままだ。
「…だから変だって言ったろー」
この場で晴れ晴れとした顔をしているのはマックスだけだった。
どうやらこれには魔術がかかっていたようだ。解けたきっかけ、一体何が鍵だったのかはわからないが一応颯輝に尋ねてみる。何となく、帰ってくる言葉は予想できるが。
「…これは?」
「大星の」
返答は至って簡潔だった。やはりなとも呆れともつかない何とも不思議な気分に陥る北斗である。どこまでも優秀であらせられたのだろうな、一代目よ。
「なーんとなくだけどさ、それ、北斗が持ってた方が良いような気がする」
何に使えるのかは颯輝にもわからないが、それは北斗が解いたのだ。結び目…封じられた何かを。大星が託したのだ。何か意味があるに違いない。
「な…んだ?」
戸惑うような北斗の声にふとその手元に注意を向けた。皺を伸ばすようになぞっていたはずのそれは。
「伸びてるね」
元はといえば、大星の私物。そう思うと、颯輝はもう何も驚かない。先程まではマックスの首に丁度良いサイズであったはずのそれは、ゆるりとその長さを変えた。
「しかし何故」
「さあ?」
やっぱり北斗に関係している。直感は確信に近づいた。しかし当の本人はまだ呆気にとられたように手にある物を見つめたままである。
「細かいことは気にしない。きっとなんか役に立つだろーし」
気楽な風体で颯輝が声を掛けると、北斗は僅かに顔の筋肉を緩め、小さく息を吐いた。そして少し考えてからその帯をピンと張ると、自らの頭に巻き始めた。
―――確か大星はそれを左腕に巻いていた。
その彼そっくりな末裔が、彼が愛用していた物を身につけている。擬視感ともつかない不思議な感覚は、不快ではない。
「似合う似合う」
茶化したように笑ってやると、憮然とした目で睨まれた。帯は幅も長さもあるようだ。何周か巻かれたその隙間から、北斗の短めの髪が飛び出ている。彼は苦虫を噛み潰したような顔で頭に触れた。
「身に付けたら何か起こるかと思ったんだが…」
「ふーん?」
実際、鳶色をしたそれは彼の金茶の瞳に良く似合っている。
「…行こう」
もうこの話題は十分だと言わんばかりに北斗は歩み始めた。続いてマックスが。その背中を見て、颯輝は負傷した体とは裏腹に、何故か心が浮き立つのを感じている。まだまだ分からない事ばかりなのは仕方がない。しかしなんて頼もしい友人達であろうか。
傷口はまだ痛む。荒野から巻き上げられる砂塵も鬱陶しい。今回のバトルだって危なかった。しかし、全て始まったばかりだという希望が颯輝の胸を満たしていた。照りつける太陽は段々と強さを増し、自分もろとも行くべき道を照らすだろう。夜で見えなくなった時には月と星の光を頼ろうか。寒ければ火を熾すのもいいだろう。自分では大変な作業も、北斗がいればなんとかなる気がする。
それでも寒さに凍えそうな時は、暖かな毛皮をもったマックスを抱いて眠ればいい。
それが、独りではないということ。
2人を追うべく、颯輝は駆け出した。
「…おい、傷大丈夫か?」
女性達の姿が砂塵で見えなくなってから、北斗がその傷を確認するように跪いた。傷口に手を伸ばすが、指先が小刻みに震えている。初のバトルは、体よりも精神にダメージを残したようだ。
「平気平気。ってかあの人たち、何だったんだろうなぁ」
「さあ。あまり感じ良くは無かった。一応、出血が酷い所は縛っておくぞ」
そんなに激しく出血している訳ではないので大丈夫だろうと言いながら北斗は平静を装い、縛るものを探した。
「ぇえー、魔法かけてくれよ。一発で治るだろ」
「………それだけ元気なら大丈夫そうだ。マックス、首のそれ、貸してくれんか」
傍で自分の傷口を舐めていたマックスは自分が呼ばれたことに気付いて起き上がると、言葉の意味を理解しているのだろう、
ひょこひょこと近寄ってきた。少し辛そうではあるが、彼もまた重傷ではないようで胸を撫で下ろした。
北斗はマックスが首輪代わりにしていた帯状のものに手を伸ばす。応急処置には丁度良いだろう。しかし、間の抜けた場違いに大きな声が彼の手を止めた。
「あぁっと、それ!」
忘れてた、と慌てたように四つん這いでマックスに近づき、そしてその首の布をいじり始めた。そんなに元気なら傷を縛る必要もないみたいだな、と北斗は安堵すると同時に、行動が突拍子もない颯輝に小さくため息をついた。結び目を摘んだり引っ張ったりして、それを取ろうとしている。マックスは大人しくしたまま上を向いているが颯輝の手はもたついていて、何だか難儀しているようだ。
北斗は敢えて手助けをせず、黙ってそれを見守った。
…いつの間にか解くことをあきらめたらしい颯輝が無理矢理マックスの頭を通そうとしているまで。
マックスの顔が変形している。されたい放題のマックスは少しもがくだけで、それでも爪をひっこめたままというところが健気である。
「これぜってーおかしい!」
「馬鹿、マックスの首が締まるだろ。貸せ」
少し強引に小さな体躯を引き寄せる。颯輝があちらで悪態をついているが気にせずその毛並みを撫でる。可哀想に、苦しかったろう。
北斗はその首にかかる布を確認した。
「お前、よっぽど不器用なんじゃあるまいか」
「ちが…それマジ変なんだって!」
それは予想よりずっとゆるく結ばれてる上、結び方も大したものではない。
拍子抜けした気分だったが、颯輝の言ってる意味がわからない。変、とは?
しかしそれはすぐに理解できた。
北斗がその結び目に指を触れた途端……本当に触れただけで、それはいとも簡単にするりと解け、北斗の手のひらに落下した。
「…………」
何が起きたのか。取り敢えずそれを手に乗せたまま、颯輝を見遣る。彼も憮然としたままだ。
「…だから変だって言ったろー」
この場で晴れ晴れとした顔をしているのはマックスだけだった。
どうやらこれには魔術がかかっていたようだ。解けたきっかけ、一体何が鍵だったのかはわからないが一応颯輝に尋ねてみる。何となく、帰ってくる言葉は予想できるが。
「…これは?」
「大星の」
返答は至って簡潔だった。やはりなとも呆れともつかない何とも不思議な気分に陥る北斗である。どこまでも優秀であらせられたのだろうな、一代目よ。
「なーんとなくだけどさ、それ、北斗が持ってた方が良いような気がする」
何に使えるのかは颯輝にもわからないが、それは北斗が解いたのだ。結び目…封じられた何かを。大星が託したのだ。何か意味があるに違いない。
「な…んだ?」
戸惑うような北斗の声にふとその手元に注意を向けた。皺を伸ばすようになぞっていたはずのそれは。
「伸びてるね」
元はといえば、大星の私物。そう思うと、颯輝はもう何も驚かない。先程まではマックスの首に丁度良いサイズであったはずのそれは、ゆるりとその長さを変えた。
「しかし何故」
「さあ?」
やっぱり北斗に関係している。直感は確信に近づいた。しかし当の本人はまだ呆気にとられたように手にある物を見つめたままである。
「細かいことは気にしない。きっとなんか役に立つだろーし」
気楽な風体で颯輝が声を掛けると、北斗は僅かに顔の筋肉を緩め、小さく息を吐いた。そして少し考えてからその帯をピンと張ると、自らの頭に巻き始めた。
―――確か大星はそれを左腕に巻いていた。
その彼そっくりな末裔が、彼が愛用していた物を身につけている。擬視感ともつかない不思議な感覚は、不快ではない。
「似合う似合う」
茶化したように笑ってやると、憮然とした目で睨まれた。帯は幅も長さもあるようだ。何周か巻かれたその隙間から、北斗の短めの髪が飛び出ている。彼は苦虫を噛み潰したような顔で頭に触れた。
「身に付けたら何か起こるかと思ったんだが…」
「ふーん?」
実際、鳶色をしたそれは彼の金茶の瞳に良く似合っている。
「…行こう」
もうこの話題は十分だと言わんばかりに北斗は歩み始めた。続いてマックスが。その背中を見て、颯輝は負傷した体とは裏腹に、何故か心が浮き立つのを感じている。まだまだ分からない事ばかりなのは仕方がない。しかしなんて頼もしい友人達であろうか。
傷口はまだ痛む。荒野から巻き上げられる砂塵も鬱陶しい。今回のバトルだって危なかった。しかし、全て始まったばかりだという希望が颯輝の胸を満たしていた。照りつける太陽は段々と強さを増し、自分もろとも行くべき道を照らすだろう。夜で見えなくなった時には月と星の光を頼ろうか。寒ければ火を熾すのもいいだろう。自分では大変な作業も、北斗がいればなんとかなる気がする。
それでも寒さに凍えそうな時は、暖かな毛皮をもったマックスを抱いて眠ればいい。
それが、独りではないということ。
2人を追うべく、颯輝は駆け出した。
風唄 本編14 [2008年06月19日(木)]
「少年」
影だと思ったそれは、人だった。棒だと思った物は、三叉に分かれた槍だった。三叉。あの皮膚を容易く切り裂き、肉を貫通させたのは、あろうことか三叉に分かれた武器だった。その人はやはり容易くその武器を引き抜くと血糊を払っている。
「少年、」
「あ、ああ!」
呼ばれていたのはどうやら自分らしい。慌てて下敷きとなった自分の下半身を引き抜く。
立ち上がり、足元を見ると魔物は完全に事切れており、2つ突き刺さったものの内、縦は目の前の人の槍、今はもうその人の手にある。横から刺さった透明な方は冷気を放っている。どこから飛んできたのだろう。どうやら氷の刃ようだ。
顔を上げると、自分を助けてくれたらしいその人は武器を背中に携え直し、こちらを見ている。どこにそんな力が秘められているのだろうか。槍を扱うの人物は、長い髪を後ろで結わえた女性だった。
「えっと……ありがとう」
そう一言礼を述べると、特に返事もなく彼女は視線を外した。無事を確かめる為だけに自分を呼んだらしい。赤い目に、冷たい印象を受ける。
2人はどうしただろう。
そう思いマックスを見ると、ゆっくりとこちらへ向かって歩いてきている。どうやら大きな怪我はないようだ。
北斗は?彼の姿を探し振り向いた時、思いも寄らない事故に見舞われた。
「おっつかれーーーー!!ボクたち、最速!最強!」
その人物は凄いスピードでぶつかったらしい。全身にダメージを受けている颯輝はそれを堪えることができずに、尻持ちを付いた。しかしぶつかってきた本人は全く意に介すことなく槍の彼女とハイタッチを交わしている。渦巻きの頬が目に付いた。
「颯輝、無事か」
その少女を追うように走ったのだろう。振り向くと、息を切らした北斗が立っていた。
「北斗…」
尻餅をついたままの姿勢だが、なんとかバトルに勝利し安堵した事と、突然現れた女2人組に驚き、立ち上がる気力が起きない。
そんな颯輝に、北斗は手を貸した。突然現れた2人組を見て、例の難しい顔をしている。
あの人達は、何者なのだろう。
そんな風に思っていたことが伝わってしまったのだろうか、先程より幾ばくか穏やかな赤い目がまたこちらを向き、言葉が紡がれた。
「君達の戦い、見せて貰った」
そう向き直る彼女の体には無駄がない。むき出しの腕は引き締まっていて、女性にしては長身の肉体があの大きな槍を簡単に扱うことを可能にしているようだ。
「あんたら何者だ。見てたって…どういうことだ」
すかさず北斗が応えた。助けてもらったとはいえ、彼は警戒心を解いていない。
「こいつはこの辺りじゃかなり強い部類に入る。だからここまで戦えたのは大健闘と言えるな」
彼女は足元に倒れる魔物を足蹴にし、ひっくり返した。北斗の問いに応えるつもりはないらしい。
颯輝は呟いた。
「強い…な…」
彼女の赤い目が颯輝を見て、楽しげに細められた。
その顔は満足そうでありながら皮肉が混じったようで、釘付けとなった颯輝は笑えない。
「ぁきゃぁぁ〜〜〜」
突然響いた間の抜けた声。
何事かとその主を見遣ると、思い切りぶつかってきたもう1人の謎の人物が回転し、その手には何か抱かれている。少女は至極楽しげだ。
「ま、マックス!!」
満身創痍のはずである彼は、しかし上半身はかなり乱暴に抱えられ、下半身は遠心力に負けて投げ出されている。
されるがままに脱力しているというよりも、抵抗する気力も無さそううに見えた。
槍を持った彼女がため息と共に、一言放つ。
「人様の動物を何の許可もなく振り回すんじゃない」
「ねぇ、可愛い!猫ちゃん!この子可愛いよ!!」
ぶつかっても謝らない。まるで話を聞いていない。何という自由奔放。注意を促した方も早々に諦めたようで、また颯輝を見た。
「この方向、リージアに行くんだろう」
「ぁ…あぁ」
「ならばあそこで一番古い武器屋を探せ。そこで双剣を買うといいだろう」
呆気に取られる颯輝を余所に、彼女は辺りを見回し唇を鳴らした。高い音が空気を切り裂く。それを聞いてはっとしたように少女もマックスを下ろした。
地面にそろりと足をつけ、頭を振る姿が哀れこの上ない。
「長所を生かせなければ、強くはなれない。お前の長所は速さだろ」
彼女の口笛に寄ってきたのは2羽の巨大な鳥類だった。首が異様に長く、手綱はなんとも頼りない。そのうちの一羽はが彼女の元へ控えた。その嘴を撫で、彼女片足を鐙にかけると、軽い所作で飛び乗った。
「行くぞ」
声を掛けられた少女は目を回したマックスを楽しげに見つめ、そしてまた例の間の抜けた返事をしてもう一羽の手綱を取る。こちらの鳥は比較的小柄なようだ。少女と鳥は再会を喜ぶかのように頬を寄せ合う。
そして振り向いた。
「ねぇ君。それ、ワザと?」
「…―――え?」
言葉の意味が分からず、颯輝は返答に倦ね、少女の瞳を見た。否、彼女が見ていたのは。
「………」
真後ろに立つ北斗は睨むでもなく、ただ息を詰めたように少女と視線を絡ませている。お互い譲る所がない。そんな殺伐とした空気が2人を包み、間に立たされた颯輝はやや狼狽した。
やがて少女は、ふーんと納得したように、それでも少し不満気に鼻を鳴らして鳥に跨り、2人の火花はとりあえず鎮火された。
槍の女性は、器用に手綱を捌いて少年達に背を向ける。まるで、もう用はないと言うかのように。
「な…ちょっと!」
「ボク達2人揃ってJR。最強無敵の2人組。ね、ノーンちゃん!!」
先程の剣呑な眼差しが嘘のようにふざけた口調、節を付けた独特の話し方が颯輝の言葉を遮った。そしてそれは今、颯輝の気になっている情報を的確にもたらす。
「……ジノ」
「ノンちゃんって呼んであげてね!ボクはライチだよ〜ん」
少し振り返るようにして、槍の彼女が。あぶみを踏みしめ立ち上がるようにしながら渦巻きの少女が。
「恐らく、また会う事になる」
「ボク達のこと、忘れんなよ!君、頭悪そうだから」
「………は?な…おい!!」
ライチの言う事を理解するまで、若干のタイムロス。彼女の言葉を真っ向から否定することができない自分が悲しい。
「また、とは?」
風が強くなってきて、目を細めなければ砂埃が入る。風に負けぬよう、北斗がいつもより大きな声で訪ねた。ジノは一瞥するだけでその問いかけには応えず、手綱を握り直した。
「……それまでにバトルの腕上げておけ」
「よわっちい男はモテないぜぇ〜〜〜」
一言余計なんだよ!という颯輝の声は砂塵と風にかき消されてしまった。しかし2人には届いたのだろうか。
今まさに鳥を走らようとする彼女たちは、砂の向こう側で僅かに笑っていたように思える。
圧倒的な強さを見せた、ジノ。
他人の魔力の方向性を瞬時に変えてしまった、ライチ。
また会う、と不思議な言葉だけを残していった2人組の見事な連携は、旅が始まったばかりの少年達には衝撃だった。
旅は簡単な道ではないと覚悟していたが、こうも始めから窮地に陥るなんて。これから先、魔物との遭遇は避けられない。
ジノはああ言ったが、今回の魔物より強い敵などそれこそ掃いて捨てる程居るだろう。その時自分は。
影だと思ったそれは、人だった。棒だと思った物は、三叉に分かれた槍だった。三叉。あの皮膚を容易く切り裂き、肉を貫通させたのは、あろうことか三叉に分かれた武器だった。その人はやはり容易くその武器を引き抜くと血糊を払っている。
「少年、」
「あ、ああ!」
呼ばれていたのはどうやら自分らしい。慌てて下敷きとなった自分の下半身を引き抜く。
立ち上がり、足元を見ると魔物は完全に事切れており、2つ突き刺さったものの内、縦は目の前の人の槍、今はもうその人の手にある。横から刺さった透明な方は冷気を放っている。どこから飛んできたのだろう。どうやら氷の刃ようだ。
顔を上げると、自分を助けてくれたらしいその人は武器を背中に携え直し、こちらを見ている。どこにそんな力が秘められているのだろうか。槍を扱うの人物は、長い髪を後ろで結わえた女性だった。
「えっと……ありがとう」
そう一言礼を述べると、特に返事もなく彼女は視線を外した。無事を確かめる為だけに自分を呼んだらしい。赤い目に、冷たい印象を受ける。
2人はどうしただろう。
そう思いマックスを見ると、ゆっくりとこちらへ向かって歩いてきている。どうやら大きな怪我はないようだ。
北斗は?彼の姿を探し振り向いた時、思いも寄らない事故に見舞われた。
「おっつかれーーーー!!ボクたち、最速!最強!」
その人物は凄いスピードでぶつかったらしい。全身にダメージを受けている颯輝はそれを堪えることができずに、尻持ちを付いた。しかしぶつかってきた本人は全く意に介すことなく槍の彼女とハイタッチを交わしている。渦巻きの頬が目に付いた。
「颯輝、無事か」
その少女を追うように走ったのだろう。振り向くと、息を切らした北斗が立っていた。
「北斗…」
尻餅をついたままの姿勢だが、なんとかバトルに勝利し安堵した事と、突然現れた女2人組に驚き、立ち上がる気力が起きない。
そんな颯輝に、北斗は手を貸した。突然現れた2人組を見て、例の難しい顔をしている。
あの人達は、何者なのだろう。
そんな風に思っていたことが伝わってしまったのだろうか、先程より幾ばくか穏やかな赤い目がまたこちらを向き、言葉が紡がれた。
「君達の戦い、見せて貰った」
そう向き直る彼女の体には無駄がない。むき出しの腕は引き締まっていて、女性にしては長身の肉体があの大きな槍を簡単に扱うことを可能にしているようだ。
「あんたら何者だ。見てたって…どういうことだ」
すかさず北斗が応えた。助けてもらったとはいえ、彼は警戒心を解いていない。
「こいつはこの辺りじゃかなり強い部類に入る。だからここまで戦えたのは大健闘と言えるな」
彼女は足元に倒れる魔物を足蹴にし、ひっくり返した。北斗の問いに応えるつもりはないらしい。
颯輝は呟いた。
「強い…な…」
彼女の赤い目が颯輝を見て、楽しげに細められた。
その顔は満足そうでありながら皮肉が混じったようで、釘付けとなった颯輝は笑えない。
「ぁきゃぁぁ〜〜〜」
突然響いた間の抜けた声。
何事かとその主を見遣ると、思い切りぶつかってきたもう1人の謎の人物が回転し、その手には何か抱かれている。少女は至極楽しげだ。
「ま、マックス!!」
満身創痍のはずである彼は、しかし上半身はかなり乱暴に抱えられ、下半身は遠心力に負けて投げ出されている。
されるがままに脱力しているというよりも、抵抗する気力も無さそううに見えた。
槍を持った彼女がため息と共に、一言放つ。
「人様の動物を何の許可もなく振り回すんじゃない」
「ねぇ、可愛い!猫ちゃん!この子可愛いよ!!」
ぶつかっても謝らない。まるで話を聞いていない。何という自由奔放。注意を促した方も早々に諦めたようで、また颯輝を見た。
「この方向、リージアに行くんだろう」
「ぁ…あぁ」
「ならばあそこで一番古い武器屋を探せ。そこで双剣を買うといいだろう」
呆気に取られる颯輝を余所に、彼女は辺りを見回し唇を鳴らした。高い音が空気を切り裂く。それを聞いてはっとしたように少女もマックスを下ろした。
地面にそろりと足をつけ、頭を振る姿が哀れこの上ない。
「長所を生かせなければ、強くはなれない。お前の長所は速さだろ」
彼女の口笛に寄ってきたのは2羽の巨大な鳥類だった。首が異様に長く、手綱はなんとも頼りない。そのうちの一羽はが彼女の元へ控えた。その嘴を撫で、彼女片足を鐙にかけると、軽い所作で飛び乗った。
「行くぞ」
声を掛けられた少女は目を回したマックスを楽しげに見つめ、そしてまた例の間の抜けた返事をしてもう一羽の手綱を取る。こちらの鳥は比較的小柄なようだ。少女と鳥は再会を喜ぶかのように頬を寄せ合う。
そして振り向いた。
「ねぇ君。それ、ワザと?」
「…―――え?」
言葉の意味が分からず、颯輝は返答に倦ね、少女の瞳を見た。否、彼女が見ていたのは。
「………」
真後ろに立つ北斗は睨むでもなく、ただ息を詰めたように少女と視線を絡ませている。お互い譲る所がない。そんな殺伐とした空気が2人を包み、間に立たされた颯輝はやや狼狽した。
やがて少女は、ふーんと納得したように、それでも少し不満気に鼻を鳴らして鳥に跨り、2人の火花はとりあえず鎮火された。
槍の女性は、器用に手綱を捌いて少年達に背を向ける。まるで、もう用はないと言うかのように。
「な…ちょっと!」
「ボク達2人揃ってJR。最強無敵の2人組。ね、ノーンちゃん!!」
先程の剣呑な眼差しが嘘のようにふざけた口調、節を付けた独特の話し方が颯輝の言葉を遮った。そしてそれは今、颯輝の気になっている情報を的確にもたらす。
「……ジノ」
「ノンちゃんって呼んであげてね!ボクはライチだよ〜ん」
少し振り返るようにして、槍の彼女が。あぶみを踏みしめ立ち上がるようにしながら渦巻きの少女が。
「恐らく、また会う事になる」
「ボク達のこと、忘れんなよ!君、頭悪そうだから」
「………は?な…おい!!」
ライチの言う事を理解するまで、若干のタイムロス。彼女の言葉を真っ向から否定することができない自分が悲しい。
「また、とは?」
風が強くなってきて、目を細めなければ砂埃が入る。風に負けぬよう、北斗がいつもより大きな声で訪ねた。ジノは一瞥するだけでその問いかけには応えず、手綱を握り直した。
「……それまでにバトルの腕上げておけ」
「よわっちい男はモテないぜぇ〜〜〜」
一言余計なんだよ!という颯輝の声は砂塵と風にかき消されてしまった。しかし2人には届いたのだろうか。
今まさに鳥を走らようとする彼女たちは、砂の向こう側で僅かに笑っていたように思える。
圧倒的な強さを見せた、ジノ。
他人の魔力の方向性を瞬時に変えてしまった、ライチ。
また会う、と不思議な言葉だけを残していった2人組の見事な連携は、旅が始まったばかりの少年達には衝撃だった。
旅は簡単な道ではないと覚悟していたが、こうも始めから窮地に陥るなんて。これから先、魔物との遭遇は避けられない。
ジノはああ言ったが、今回の魔物より強い敵などそれこそ掃いて捨てる程居るだろう。その時自分は。
風唄 本編13 [2008年06月19日(木)]
転々と晒される岩、好き勝手伸びる木々、荒野。この光景を目にするのは、昨日に引き続き2度目だ。
2人と1匹は街を出て、例の靄のような壁を背にして立っている。
颯輝の古い記憶では、目的地である大聖堂は確かここより北にあった。
短くない旅路、幼い妹を連れての道は、肉体は言うまでもなく、精神的にも決して楽ではなかった。
あの時、全てが変わってしまったのだ。
「北を目指しつつ、まずは隣町のリージアに行こう」
北斗の提案に、颯輝は少し考え頷いた。
リージア、そう遠くはない商業に栄えた街。
「必要物資と…もしかしたら神話についての情報も集められるかもしれない」
「だな。確かでーっかい街だったなぁ。相変わらずなんだ?」
「そうだ。人の集まるところには情報も集まる。ここから徒歩で行けなくもないが…運が良ければ輸送用の車に乗ろう」
道無き道、と思っていたが、街同士の貿易はなかなか頻繁に行われているらしい。足元から伸びる轍の跡は、遥か遠くまで続いている。
全く見知らぬ世界という訳ではない。その事が、今の颯輝には大きな救いだ。
「な、さっき抜けた街を包んでるみたいなアレは誰がどうやって考えたんだ?」
歩みを止めぬまま少し後方に目を遣って、北斗の顔を伺う。彼は、あぁと一言呟き颯輝と同じように後ろを見た。
白い壁は、地面に這う雲のように、その実体を隠し続けている。
「数年前、街の術に優れた奴らが集められて共同で結界を張ったんだ。近くでよく見ると、陣が描かれてる」
陣?颯輝は魔法に疎い。全く気づかなかった。
「ふーん…。アレ、やっぱ魔物避けなんだろ?」
「そうだ。魔物は街がそこにあることも気付かず、さらに侵入も許さない仕組みになってる。
もし結界を無理に破ったとしても、その瞬間術師が気付く」
「すげー!」
颯輝は身を乗り出した。大星も確か、優れた魔法の使い手であったようだが、使っている場面を見る事はあっても、
詳しい話は一切聞いた事がなかった。術にも様々な使い方もあるのだろう。
「んー術師ってば、北斗も魔法使えるんだろ?もしかして、北斗が結界張った人々の一員だったりして」
颯輝は軽いステップを踏みながら友人の肩に手を置いた。
された本人はただ呆れたように息を吐いたが、払いのける事もせずに歩みを進めている。
「あんた、さっきから勘違いしてるみたいだけど、俺は、」
冷たい風が吹いたのと、2人が振り向き、マックスが駆けたのは同時だった。
「………!!」
会話は完全に中断され、颯輝は咄嗟に北斗の肩を突き飛ばす形で自分と彼の身を守った。
羽音を響かせ、醜悪な姿は見るに耐えない。
対峙した敵の片眼は、斬り裂かれたように潰れていて、それは新しい傷のようだ。
先ほどの攻撃は尾から繰り出されたものだ。耳元で空気を切り裂く音は、僅かでも遅れたらその攻撃を受ける所だった証明だ。骨の何本かが犠牲になったかもしれない。
「早速のお出ましか」
尻もちをついた北斗が体制を立て直し、身構える。先制攻撃をすんでのところでかわした2人に傷はない。
正面を見据えた時、颯輝は気が付いた。敵は目と羽の一枚に傷を負っている。
「昨日のやつだ…」
「え?」
「昨日倒したと思ってたやつ!」
敵が猛り、口元の大気がが歪み始めた。
攪乱するマックスの動きを直感的に把握し、颯輝は持ち前の速さを生かして敵の懐に足元から滑り込んだ。
地面に手を付き、跳ね起きの要領で敵の喉元を狙うが、横っ面に蹴りを入れる程度に止まってしまった。しかし、それでも魔物の口から吐かれた炎は標的から逸れ、地の草の一部を消し炭と変えた。
敵との間合いを置くためその場から一時退くと、颯輝は北斗の横に付いた。彼は荷物探り、薄い書籍のようなものを取り出す。
「北斗、平気か!?」
「俺は何もしとらんぞ。あんたこそ」
動物のように顔を振り、頭に乗った砂埃を払いのけ颯輝は笑って見せた。今のところ、無傷。
「マックス」
小さな体はしっかりと魔物の動きを捉え、最小限の動きで攻撃を避けている。魔物に感情などあるのだろうか。
残された目はマックスの黄色と黒の模様しか映らず、執拗に攻撃を繰り出している。小さな彼の動きに鈍りはないが、いつまでも魔物の攻撃をかわし続ければ消耗は激しく、確実に不利だろう。
「あいつ倒さなきゃ…援護よろしく!」
颯輝は再び駆け出し、北斗はページをめくる。 マックスが咆哮し、守りに徹していた体制を翻し、地面を蹴った。
「こっちだ!!」
マックスの動きに気を取られていた魔物は、突然現れた颯輝に躊躇した。
その瞬間マックスは羽の一部に食らいつき、颯輝は敵の左頬辺りに掌打を繰り出す。相変わらず硬い皮膚だ。
敵の動きは一時鈍り後退するものの、羽に張り付くマックスを振り払い、足摺りをして唸った。間髪を置かず颯輝は一歩踏み出す。目と目の間はどの生物においても弱点だ。真っ直ぐに繰り出す拳は敵の動きよりも早く捉える。
しかし。
「颯輝!」
たまらず北斗が叫んだ。
敵は、颯輝が予想していたよりもずっと速く颯輝の動きを察知し、そして牙を剥いた。攻撃の手を止めた颯輝の右腕から赤い血が滴る。
「ちっきしょ…」
感覚が麻痺しているのだろうか。滲み出てくる血液は鮮やかではあるが、痛みはあまりない。
致命傷では無いが、これで確実にこのバトルが厳しいものとなった。傷口が、ただ熱い。
途端、マックスの警告のような声がした。慌てて顔を上げると、この間合いを一瞬で詰めた魔物の顔がそこにあった。
「な…!!」
転がるように横に飛び退くが、敵の攻撃の手が早い。
颯輝も素早く立ち上がるも、この距離では連続した攻撃を見極めてかわすことが精一杯だ。その間にも爪が彼の肌を掠め、小さな傷を作り続けている。一度目のバトルに激昂したのだろうか。比にならない強さに、颯輝は倦ねていた。―――武器が欲しい。
守りに徹する颯輝の視界に、今まさに飛びかかろうとするマックスの姿が映った。
瞬間、魔物の負傷している目に拳を叩き込むが、直後、腹部に重い衝撃が走り、着地もままならず後ろに吹っ飛んだ。
うまく呼吸ができない。太い鞭のような尾に、マックスの体も弾かれたのが見えた。
こちらを向き直る敵の目の色が、更に暗黒に濁った気がした。羽を大きく広げ、空気が歪む。
あの、地面を抉る攻撃がくる。颯輝は地面を踏みしめ、食いしばった。
「弾けろ!!」
しかし、覚悟とは裏腹に大気に響いたのは、後ろで控えていた北斗の声だった。その瞬間、バチバチと音の軌跡が走り、敵の顔面で衝撃音が唸る。
振り返り北斗の顔を見ると、息を切らし、彼自身驚いたような表情を浮かべている。
敵に真っ直ぐ向かっていた右手を静かに下ろし、颯輝を見た。
しかし2人の視線はすぐに断ち切られる。砂煙に巻かれた魔物の地を踏みしめる音が聞こえたのだ。
「まだやんのかよ…」
ゆっくりと前進し姿を現す魔物に、颯輝は右手を庇いながらも身構えた。背中に冷たい汗が伝う。次はどう来るか。
北斗は凄まじい勢いでまたページを探す。マックスの毛並みにも血が滲んでいるが、その足取りはしっかりしている。
怒りの咆哮。一つしかない目で、颯輝を強く睨みつける。
まだ旅は始まったばかりだ。
颯輝は一笑した。
一気に間合いが詰まる。
速さが一つの武器である颯輝と、空気を切り裂く羽をもつ魔物が、互いに向かって駆け出した。駆ける速さはそのままに、魔物は体を捻って颯輝を殴打しようとするが、颯輝もまたスピードに乗った跳躍によってそれをかわした。
勢いがついまま回転した敵の真後ろに着地すると、すぐさま颯輝は魔物の羽を絡めとり、その関節とは逆の方向へ全身を使って折り曲げた。
魔物の声がつんざく。
北斗は詠唱し続け、マックスは敵の喉元に食らいている。
魔物は頭を振ってマックスを引き剥がすと、一際大きな雄叫びとともに颯輝に向き直った。
魔物の感情が読める。怒りだ。
口元から炎が吐かれる。横転してそれをかわし、見上げた直後。
魔物の牙が僅かすぐそこにあった。
―――間に合わない!!
絶体絶命の友を見つめ、北斗が早口に詠唱を終えるまさにその時だった。
汗の滲む自分の手に、別の何かが触れる感覚があった。
「キミ、それじゃあだめだよ」
振り返るより、早く。
真っ黒い影が自分を覆う。
もうだめだ、と考えるよりも、太陽を背負う魔物の黒さと眩しい空のコントラストが苦しかった。それでも鍛えられた体はどこからか警鐘を発して、体制を立て直そうとしている。
牙が来る。
それでも颯輝は目を閉じなかった。
閉じなかったから、その様子が良く見えたのだと思う。視界の奥、自分に襲いかかる魔物の更に後方。
魔物よりも空に近く太陽の光を背負った影。高く高く飛んでいる。
すると突然、手前の魔物の顔に横から透明な何かが突き刺さり、ほぼ同時に、魔物にかかる影が棒のようなものを直角に突き刺した。
あの硬い皮膚が嘘のようだった。
魔物が地に落ちる。
颯輝の下半身がその体躯の下敷きになったようだが、手をついて体を起こそうとしている。どうやら無事らしい。
その事を確認すると、北斗は振り向いた。
「…何者だ」
顔に描かれている紋様は、この世界では商人を表す。彼女の絵柄は渦巻き。まだ幼さが残るその頬は、満足そうに口角が上がったままだ。
自分は先程と同じ魔法を唱えていた。しかし彼女が触れた瞬間、体に集めた魔の力は瞬時に変換され、鋭利な氷の矢になって敵に突き刺さった。
敵に一矢報いたあの最初の魔法でさえ、能力の低い自分には奇跡のようなものだったというのに。
少女は小首を傾げ、微笑んだままだ。
2人と1匹は街を出て、例の靄のような壁を背にして立っている。
颯輝の古い記憶では、目的地である大聖堂は確かここより北にあった。
短くない旅路、幼い妹を連れての道は、肉体は言うまでもなく、精神的にも決して楽ではなかった。
あの時、全てが変わってしまったのだ。
「北を目指しつつ、まずは隣町のリージアに行こう」
北斗の提案に、颯輝は少し考え頷いた。
リージア、そう遠くはない商業に栄えた街。
「必要物資と…もしかしたら神話についての情報も集められるかもしれない」
「だな。確かでーっかい街だったなぁ。相変わらずなんだ?」
「そうだ。人の集まるところには情報も集まる。ここから徒歩で行けなくもないが…運が良ければ輸送用の車に乗ろう」
道無き道、と思っていたが、街同士の貿易はなかなか頻繁に行われているらしい。足元から伸びる轍の跡は、遥か遠くまで続いている。
全く見知らぬ世界という訳ではない。その事が、今の颯輝には大きな救いだ。
「な、さっき抜けた街を包んでるみたいなアレは誰がどうやって考えたんだ?」
歩みを止めぬまま少し後方に目を遣って、北斗の顔を伺う。彼は、あぁと一言呟き颯輝と同じように後ろを見た。
白い壁は、地面に這う雲のように、その実体を隠し続けている。
「数年前、街の術に優れた奴らが集められて共同で結界を張ったんだ。近くでよく見ると、陣が描かれてる」
陣?颯輝は魔法に疎い。全く気づかなかった。
「ふーん…。アレ、やっぱ魔物避けなんだろ?」
「そうだ。魔物は街がそこにあることも気付かず、さらに侵入も許さない仕組みになってる。
もし結界を無理に破ったとしても、その瞬間術師が気付く」
「すげー!」
颯輝は身を乗り出した。大星も確か、優れた魔法の使い手であったようだが、使っている場面を見る事はあっても、
詳しい話は一切聞いた事がなかった。術にも様々な使い方もあるのだろう。
「んー術師ってば、北斗も魔法使えるんだろ?もしかして、北斗が結界張った人々の一員だったりして」
颯輝は軽いステップを踏みながら友人の肩に手を置いた。
された本人はただ呆れたように息を吐いたが、払いのける事もせずに歩みを進めている。
「あんた、さっきから勘違いしてるみたいだけど、俺は、」
冷たい風が吹いたのと、2人が振り向き、マックスが駆けたのは同時だった。
「………!!」
会話は完全に中断され、颯輝は咄嗟に北斗の肩を突き飛ばす形で自分と彼の身を守った。
羽音を響かせ、醜悪な姿は見るに耐えない。
対峙した敵の片眼は、斬り裂かれたように潰れていて、それは新しい傷のようだ。
先ほどの攻撃は尾から繰り出されたものだ。耳元で空気を切り裂く音は、僅かでも遅れたらその攻撃を受ける所だった証明だ。骨の何本かが犠牲になったかもしれない。
「早速のお出ましか」
尻もちをついた北斗が体制を立て直し、身構える。先制攻撃をすんでのところでかわした2人に傷はない。
正面を見据えた時、颯輝は気が付いた。敵は目と羽の一枚に傷を負っている。
「昨日のやつだ…」
「え?」
「昨日倒したと思ってたやつ!」
敵が猛り、口元の大気がが歪み始めた。
攪乱するマックスの動きを直感的に把握し、颯輝は持ち前の速さを生かして敵の懐に足元から滑り込んだ。
地面に手を付き、跳ね起きの要領で敵の喉元を狙うが、横っ面に蹴りを入れる程度に止まってしまった。しかし、それでも魔物の口から吐かれた炎は標的から逸れ、地の草の一部を消し炭と変えた。
敵との間合いを置くためその場から一時退くと、颯輝は北斗の横に付いた。彼は荷物探り、薄い書籍のようなものを取り出す。
「北斗、平気か!?」
「俺は何もしとらんぞ。あんたこそ」
動物のように顔を振り、頭に乗った砂埃を払いのけ颯輝は笑って見せた。今のところ、無傷。
「マックス」
小さな体はしっかりと魔物の動きを捉え、最小限の動きで攻撃を避けている。魔物に感情などあるのだろうか。
残された目はマックスの黄色と黒の模様しか映らず、執拗に攻撃を繰り出している。小さな彼の動きに鈍りはないが、いつまでも魔物の攻撃をかわし続ければ消耗は激しく、確実に不利だろう。
「あいつ倒さなきゃ…援護よろしく!」
颯輝は再び駆け出し、北斗はページをめくる。 マックスが咆哮し、守りに徹していた体制を翻し、地面を蹴った。
「こっちだ!!」
マックスの動きに気を取られていた魔物は、突然現れた颯輝に躊躇した。
その瞬間マックスは羽の一部に食らいつき、颯輝は敵の左頬辺りに掌打を繰り出す。相変わらず硬い皮膚だ。
敵の動きは一時鈍り後退するものの、羽に張り付くマックスを振り払い、足摺りをして唸った。間髪を置かず颯輝は一歩踏み出す。目と目の間はどの生物においても弱点だ。真っ直ぐに繰り出す拳は敵の動きよりも早く捉える。
しかし。
「颯輝!」
たまらず北斗が叫んだ。
敵は、颯輝が予想していたよりもずっと速く颯輝の動きを察知し、そして牙を剥いた。攻撃の手を止めた颯輝の右腕から赤い血が滴る。
「ちっきしょ…」
感覚が麻痺しているのだろうか。滲み出てくる血液は鮮やかではあるが、痛みはあまりない。
致命傷では無いが、これで確実にこのバトルが厳しいものとなった。傷口が、ただ熱い。
途端、マックスの警告のような声がした。慌てて顔を上げると、この間合いを一瞬で詰めた魔物の顔がそこにあった。
「な…!!」
転がるように横に飛び退くが、敵の攻撃の手が早い。
颯輝も素早く立ち上がるも、この距離では連続した攻撃を見極めてかわすことが精一杯だ。その間にも爪が彼の肌を掠め、小さな傷を作り続けている。一度目のバトルに激昂したのだろうか。比にならない強さに、颯輝は倦ねていた。―――武器が欲しい。
守りに徹する颯輝の視界に、今まさに飛びかかろうとするマックスの姿が映った。
瞬間、魔物の負傷している目に拳を叩き込むが、直後、腹部に重い衝撃が走り、着地もままならず後ろに吹っ飛んだ。
うまく呼吸ができない。太い鞭のような尾に、マックスの体も弾かれたのが見えた。
こちらを向き直る敵の目の色が、更に暗黒に濁った気がした。羽を大きく広げ、空気が歪む。
あの、地面を抉る攻撃がくる。颯輝は地面を踏みしめ、食いしばった。
「弾けろ!!」
しかし、覚悟とは裏腹に大気に響いたのは、後ろで控えていた北斗の声だった。その瞬間、バチバチと音の軌跡が走り、敵の顔面で衝撃音が唸る。
振り返り北斗の顔を見ると、息を切らし、彼自身驚いたような表情を浮かべている。
敵に真っ直ぐ向かっていた右手を静かに下ろし、颯輝を見た。
しかし2人の視線はすぐに断ち切られる。砂煙に巻かれた魔物の地を踏みしめる音が聞こえたのだ。
「まだやんのかよ…」
ゆっくりと前進し姿を現す魔物に、颯輝は右手を庇いながらも身構えた。背中に冷たい汗が伝う。次はどう来るか。
北斗は凄まじい勢いでまたページを探す。マックスの毛並みにも血が滲んでいるが、その足取りはしっかりしている。
怒りの咆哮。一つしかない目で、颯輝を強く睨みつける。
まだ旅は始まったばかりだ。
颯輝は一笑した。
一気に間合いが詰まる。
速さが一つの武器である颯輝と、空気を切り裂く羽をもつ魔物が、互いに向かって駆け出した。駆ける速さはそのままに、魔物は体を捻って颯輝を殴打しようとするが、颯輝もまたスピードに乗った跳躍によってそれをかわした。
勢いがついまま回転した敵の真後ろに着地すると、すぐさま颯輝は魔物の羽を絡めとり、その関節とは逆の方向へ全身を使って折り曲げた。
魔物の声がつんざく。
北斗は詠唱し続け、マックスは敵の喉元に食らいている。
魔物は頭を振ってマックスを引き剥がすと、一際大きな雄叫びとともに颯輝に向き直った。
魔物の感情が読める。怒りだ。
口元から炎が吐かれる。横転してそれをかわし、見上げた直後。
魔物の牙が僅かすぐそこにあった。
―――間に合わない!!
絶体絶命の友を見つめ、北斗が早口に詠唱を終えるまさにその時だった。
汗の滲む自分の手に、別の何かが触れる感覚があった。
「キミ、それじゃあだめだよ」
振り返るより、早く。
真っ黒い影が自分を覆う。
もうだめだ、と考えるよりも、太陽を背負う魔物の黒さと眩しい空のコントラストが苦しかった。それでも鍛えられた体はどこからか警鐘を発して、体制を立て直そうとしている。
牙が来る。
それでも颯輝は目を閉じなかった。
閉じなかったから、その様子が良く見えたのだと思う。視界の奥、自分に襲いかかる魔物の更に後方。
魔物よりも空に近く太陽の光を背負った影。高く高く飛んでいる。
すると突然、手前の魔物の顔に横から透明な何かが突き刺さり、ほぼ同時に、魔物にかかる影が棒のようなものを直角に突き刺した。
あの硬い皮膚が嘘のようだった。
魔物が地に落ちる。
颯輝の下半身がその体躯の下敷きになったようだが、手をついて体を起こそうとしている。どうやら無事らしい。
その事を確認すると、北斗は振り向いた。
「…何者だ」
顔に描かれている紋様は、この世界では商人を表す。彼女の絵柄は渦巻き。まだ幼さが残るその頬は、満足そうに口角が上がったままだ。
自分は先程と同じ魔法を唱えていた。しかし彼女が触れた瞬間、体に集めた魔の力は瞬時に変換され、鋭利な氷の矢になって敵に突き刺さった。
敵に一矢報いたあの最初の魔法でさえ、能力の低い自分には奇跡のようなものだったというのに。
少女は小首を傾げ、微笑んだままだ。
風唄 本編12 [2008年06月19日(木)]
「兄貴」
静かに、白い顔がゆっくりと振り返る。顔色に似合わず、その口元は大体機嫌よく微笑みが刻まれている。
「ん?」
北斗を見留めた今も、それは変わらない。
兄ならきっと分かってくれるだろうという確信は、微笑む顔を見て何故か不安へと変化していった。
「あぁ、北斗。読みたかった本は見つかった?」
「うん、まあ」
先程あんな会話を交わした後。切り出す事が、こんなにも難しいなんて。
「あのさ」
意を決して、なんとか言葉を紡いだその時だった。
「たっだいまーん!!!」
廊下で話す2人の丁度真ん中にあった扉が、盛大な音を立てて開いた。
大声且つ場の空気を読まずに闖入してきたのは、北斗のすぐ上の姉だった。
我が家の女は、どうしてこうも強いのだろうか。
体中に渦巻いていた緊張はとりあえずどこかへ消え、呆れと脱力感で姉を見るしかなかった。
「…………」
「おかえり。遅かったね」
兄は、そんな時でも笑顔で彼女を出迎える。
「お兄、ただいま。何、北斗ってばそんな目であたしを見て。そんなにお姉様に会いたかった?」
そしてこの姉は、何かと因縁を付けては北斗を困らせるのだ。小さい頃はよく泣かされていたものだ。
北斗は彼女の言葉に応じず、出来るだけ視線を逸らし後ずさった。それを見た兄は口元に手を当て、声を殺して笑っている。
「飲んできたな…」
間違いない。姉の頬はいつもより若干赤く染まっており、目はきちんと開けられていない。
決め手は姉が乱入してきた時から漂い始めた、あの独特の匂いだ。
姉は酒が入ると益々絡んでくる。ターゲットは勿論北斗である。その質の悪さに、北斗はいつも閉口するのだ。
「そんな事どうだっていいのよ。会いたかったの?会いたくなかったの〜〜?」
据わった目で一歩ずつ近づいてくる。勿論答える気などさらさらない。
「な、」
どうしたものかと考える暇もなく、姉は突然北斗に突撃してきた。とてもじゃないが、避けられる隙はなかった。
「北斗くんってば〜〜、お姉さんに甘えたいならそう言いなさーーーい!」
「!?」
女性にしてはなかなか長身の姉に、一瞬で頭を彼女の脇腹に固定された。バランスを崩し、中腰になった体は上手く力が入らない。
「離せ!触るな!!」
高笑いしながら北斗の頭を掻き回す姉に、くぐもったその声は聞こえないようだ。
耳にのあたりに柔らかな何かが押し当てられるが、こんな姉じゃ嬉しくもなんともない。寧ろ迷惑だ。
北斗が己の不運を心の中で嘆いた時、兄が笑いを堪えながら助け船を出した。
「まって、ちょっと、その辺にしといてあげて。北斗は僕に話があるみたいなんだ」
よっぽど笑っていたのか、息も絶え絶えの兄の声が聞こえた。
「そーだ!だから離せよ!」
「何よぉ。何の話ぃ?」
北斗の言葉はどうやら無視されたらしい。そのままの格好で、腕の力が緩められる気配はない。
「男兄弟の会話だよ。決まってるじゃないか」
兄は呼吸も整ったらしく、いつものペースで柔らかく話す。北斗の視界は今、床しか見えないが、その顔は微笑んでいるに違いない。
彼が微笑んでる時は、大体が本気で楽しんでいる。常に笑っているイメージの兄は、簡単に言えば笑い上戸なのだ。
はいはい、と姉は半ば呆れたように北斗の首に掛かっていた腕を外し、あれだけしつこく絡んだ事が嘘のように踵を返した。
これぞまさに、鶴の一声。
「猥談なら部屋でやんなさいよ」
「おい!!」
片手をひらひらさせながら去って行く姉。最後に爆弾を落として帰っていった。
「本当に何でうちの女達って…」
北斗の呟きに、兄の笑い声はいよいよ本気のものとなり、目尻には涙が滲んでいる。
それを人差し指で拭うと、息も絶え絶え、彼は言った。
「それじゃあ、部屋に行こっか」
さっきの大笑いといい、今日の兄は調子も機嫌もいいようだ。
普段より若干早い動きで北斗を自室に促し座らせると、自分も寝台に腰を下ろした。
「それで、どうしたの?」
うん、と北斗は頷いた。もしかしたら、今から自分がやろうとしているのは家族への裏切り行為かもしれない。
そう思うと、なかなか切り出せなかった。
「あれっ?本当に好きな娘でもできたの?」
「違う!」
兄の目が少しだけ輝いたような、気のせいか?
「そっか」
輝いた割には、さして落胆した様子は見られない。
どこまで本気なのか、時々北斗でさえも読めないときがあるが、兄はこれでなかなか冗談好きなのだ。
「兄貴には言おうと思って。驚かないで聞いて欲しい」
「うん。あんまり驚くと胸が痛くなるから、驚かないよ」
「…………」
「どうしたの?」
「いや…」
我が家の強者は、女だけではないかもしれないと、今更ながら感じる北斗であった。
そんな兄のいつもと変わらない様子だったから、北斗は自分でも驚く程、その言葉はするりと流れ出た。
それこそが兄の狙いだと、北斗は見抜けなかった。
「俺、旅に出ようと思う」
しばしの沈黙。
北斗が見る兄は、暖かい茶を口元に運んでいる。
「そう」
静かな返事だった。
「帰りはいつになるかわからない。帰ってこれるかもわからない…けど、俺は行くって決めたんだ」
表面に息を吹きかけ、熱を飛ばしている。一口飲み下すと、兄は微笑んだ。
「そう」
北斗は安堵に包まれた。
「旅立ちは、いつ?」
「街を出るのは夜明け。でも合流しなければならない奴がいるから、もう家を出ようと思う」
コトリ、傍らにカップを置いた。あんなに湯気が立っていたのに、もう飲み干したらしい。
「それで…」
「大丈夫。みんなには僕からうまく言っておく。それが、僕に教えてくれた一番の理由だろ?」
兄が下の兄弟に慕われてるのは、こういったところにあるのだと思う。二歩も三歩も先を読んでいて、北斗は敵わないと心から感じる。
「…ありがとう」
「気をつけて」
「ああ」
何も聞かず、何も言わず。
神話に登場する神々が本当にいるのなら、何故、と問いたい。
こんなにも人の心を汲み取ことに長ける兄に、どうして脆弱な肉体しか与えなかったのか。
陽の光を浴びるに相応しい人間を、神は見抜けなかったのだろうか。
「兄貴は…俺が逃げてるって思わないのか?」
「思わないなぁ」
即答が嬉しかった。そう思ってくれる理由は聞かない。
「ね、北斗。僕なら大丈夫だから、心配しないで、自分と仲間の事だけ考えて、進むんだよ」
ぽん、と肩に手を置く兄に遠い昔がフラッシュバックした。
幼い頃にもこうして何かある度に、半ベソをかいた北斗を少し歳の離れたこの兄が肩や背中に手を置いて宥めてくれていた。
「これから兄貴には頭が上がらないな」
にっこり微笑んだ兄が返した。
「恩は高く売っとかないと」
漆黒に浮かぶ月や星が身を潜め、藍色から紫へ、そして清々しい空気と共にオレンジに水平線を染め始めた。
岩窟から少し歩けば、夕焼けも、朝焼けも見ることができるのが岬の良いところだ。
「オレあそこの紫とオレンジの間の色が好き」
颯輝はかつてを思い出し、懐かしい思いと共にその場所を指し示した。
「俺は…もう少し上だな。颯輝よりほんの少し、上」
「やっぱ、似てるのは顔だけなんだなー。大星はやっと藍色になった頃が好きだって言ってた」
大星の言っていた色はもうかなり後方に追いやられていて、振り向かないと見ることができない。でも今は、今だけは、それは見ない。後ろを振り向かずにいたい。
「駒馳はな、もっともっと太陽近く。太陽が登る直前の水平線だって」
「シスコン」
「なんだよ!」
「お、返事したな」
「違う!そういう意味じゃ…」
「ほら、登るぞ」
気持ちが急くのか、早起きな小鳥に起こされたのか、東の空が大星の好きな色に変わる頃、颯輝は目が覚めた。
すると、いてもたっても居られない程、旅立ち前に日の出を見たくなった。
あの後戻ってきた北斗もすぐさま眠りについた。それなのに彼の寝起きは酷かった。揺さぶり叩き起こし、感服しつつも引き摺るようにしてここまで出てきた。
「うん、きれいだ」
「俺は眠い」
まだ言うか!と、颯輝は北斗に一瞬目をやるが、眠いと悪態をつきながらも、うっすら開けた瞼から彼はしっかり朝焼けを見ていた。
朝焼けにその瞳が不思議な色に染まっている。
穏やかな気分だった。
「大丈夫。きっと」
「…ああ」
オレンジ色が、眩しく岬を照らす。妹の好きな色が、2人を照らす。
不安は尽きない。それでも颯輝の心は希望で満ちていた。
古き友と新たな友が見つけてくれた突破口は、確実に颯輝の向かう未来に続いている自信があった。
段々と白に染まりゆく水平線は、希望の色だ。
頬を撫でる風が、足元の小さな花の綿毛を浚っていった。
静かに、白い顔がゆっくりと振り返る。顔色に似合わず、その口元は大体機嫌よく微笑みが刻まれている。
「ん?」
北斗を見留めた今も、それは変わらない。
兄ならきっと分かってくれるだろうという確信は、微笑む顔を見て何故か不安へと変化していった。
「あぁ、北斗。読みたかった本は見つかった?」
「うん、まあ」
先程あんな会話を交わした後。切り出す事が、こんなにも難しいなんて。
「あのさ」
意を決して、なんとか言葉を紡いだその時だった。
「たっだいまーん!!!」
廊下で話す2人の丁度真ん中にあった扉が、盛大な音を立てて開いた。
大声且つ場の空気を読まずに闖入してきたのは、北斗のすぐ上の姉だった。
我が家の女は、どうしてこうも強いのだろうか。
体中に渦巻いていた緊張はとりあえずどこかへ消え、呆れと脱力感で姉を見るしかなかった。
「…………」
「おかえり。遅かったね」
兄は、そんな時でも笑顔で彼女を出迎える。
「お兄、ただいま。何、北斗ってばそんな目であたしを見て。そんなにお姉様に会いたかった?」
そしてこの姉は、何かと因縁を付けては北斗を困らせるのだ。小さい頃はよく泣かされていたものだ。
北斗は彼女の言葉に応じず、出来るだけ視線を逸らし後ずさった。それを見た兄は口元に手を当て、声を殺して笑っている。
「飲んできたな…」
間違いない。姉の頬はいつもより若干赤く染まっており、目はきちんと開けられていない。
決め手は姉が乱入してきた時から漂い始めた、あの独特の匂いだ。
姉は酒が入ると益々絡んでくる。ターゲットは勿論北斗である。その質の悪さに、北斗はいつも閉口するのだ。
「そんな事どうだっていいのよ。会いたかったの?会いたくなかったの〜〜?」
据わった目で一歩ずつ近づいてくる。勿論答える気などさらさらない。
「な、」
どうしたものかと考える暇もなく、姉は突然北斗に突撃してきた。とてもじゃないが、避けられる隙はなかった。
「北斗くんってば〜〜、お姉さんに甘えたいならそう言いなさーーーい!」
「!?」
女性にしてはなかなか長身の姉に、一瞬で頭を彼女の脇腹に固定された。バランスを崩し、中腰になった体は上手く力が入らない。
「離せ!触るな!!」
高笑いしながら北斗の頭を掻き回す姉に、くぐもったその声は聞こえないようだ。
耳にのあたりに柔らかな何かが押し当てられるが、こんな姉じゃ嬉しくもなんともない。寧ろ迷惑だ。
北斗が己の不運を心の中で嘆いた時、兄が笑いを堪えながら助け船を出した。
「まって、ちょっと、その辺にしといてあげて。北斗は僕に話があるみたいなんだ」
よっぽど笑っていたのか、息も絶え絶えの兄の声が聞こえた。
「そーだ!だから離せよ!」
「何よぉ。何の話ぃ?」
北斗の言葉はどうやら無視されたらしい。そのままの格好で、腕の力が緩められる気配はない。
「男兄弟の会話だよ。決まってるじゃないか」
兄は呼吸も整ったらしく、いつものペースで柔らかく話す。北斗の視界は今、床しか見えないが、その顔は微笑んでいるに違いない。
彼が微笑んでる時は、大体が本気で楽しんでいる。常に笑っているイメージの兄は、簡単に言えば笑い上戸なのだ。
はいはい、と姉は半ば呆れたように北斗の首に掛かっていた腕を外し、あれだけしつこく絡んだ事が嘘のように踵を返した。
これぞまさに、鶴の一声。
「猥談なら部屋でやんなさいよ」
「おい!!」
片手をひらひらさせながら去って行く姉。最後に爆弾を落として帰っていった。
「本当に何でうちの女達って…」
北斗の呟きに、兄の笑い声はいよいよ本気のものとなり、目尻には涙が滲んでいる。
それを人差し指で拭うと、息も絶え絶え、彼は言った。
「それじゃあ、部屋に行こっか」
さっきの大笑いといい、今日の兄は調子も機嫌もいいようだ。
普段より若干早い動きで北斗を自室に促し座らせると、自分も寝台に腰を下ろした。
「それで、どうしたの?」
うん、と北斗は頷いた。もしかしたら、今から自分がやろうとしているのは家族への裏切り行為かもしれない。
そう思うと、なかなか切り出せなかった。
「あれっ?本当に好きな娘でもできたの?」
「違う!」
兄の目が少しだけ輝いたような、気のせいか?
「そっか」
輝いた割には、さして落胆した様子は見られない。
どこまで本気なのか、時々北斗でさえも読めないときがあるが、兄はこれでなかなか冗談好きなのだ。
「兄貴には言おうと思って。驚かないで聞いて欲しい」
「うん。あんまり驚くと胸が痛くなるから、驚かないよ」
「…………」
「どうしたの?」
「いや…」
我が家の強者は、女だけではないかもしれないと、今更ながら感じる北斗であった。
そんな兄のいつもと変わらない様子だったから、北斗は自分でも驚く程、その言葉はするりと流れ出た。
それこそが兄の狙いだと、北斗は見抜けなかった。
「俺、旅に出ようと思う」
しばしの沈黙。
北斗が見る兄は、暖かい茶を口元に運んでいる。
「そう」
静かな返事だった。
「帰りはいつになるかわからない。帰ってこれるかもわからない…けど、俺は行くって決めたんだ」
表面に息を吹きかけ、熱を飛ばしている。一口飲み下すと、兄は微笑んだ。
「そう」
北斗は安堵に包まれた。
「旅立ちは、いつ?」
「街を出るのは夜明け。でも合流しなければならない奴がいるから、もう家を出ようと思う」
コトリ、傍らにカップを置いた。あんなに湯気が立っていたのに、もう飲み干したらしい。
「それで…」
「大丈夫。みんなには僕からうまく言っておく。それが、僕に教えてくれた一番の理由だろ?」
兄が下の兄弟に慕われてるのは、こういったところにあるのだと思う。二歩も三歩も先を読んでいて、北斗は敵わないと心から感じる。
「…ありがとう」
「気をつけて」
「ああ」
何も聞かず、何も言わず。
神話に登場する神々が本当にいるのなら、何故、と問いたい。
こんなにも人の心を汲み取ことに長ける兄に、どうして脆弱な肉体しか与えなかったのか。
陽の光を浴びるに相応しい人間を、神は見抜けなかったのだろうか。
「兄貴は…俺が逃げてるって思わないのか?」
「思わないなぁ」
即答が嬉しかった。そう思ってくれる理由は聞かない。
「ね、北斗。僕なら大丈夫だから、心配しないで、自分と仲間の事だけ考えて、進むんだよ」
ぽん、と肩に手を置く兄に遠い昔がフラッシュバックした。
幼い頃にもこうして何かある度に、半ベソをかいた北斗を少し歳の離れたこの兄が肩や背中に手を置いて宥めてくれていた。
「これから兄貴には頭が上がらないな」
にっこり微笑んだ兄が返した。
「恩は高く売っとかないと」
漆黒に浮かぶ月や星が身を潜め、藍色から紫へ、そして清々しい空気と共にオレンジに水平線を染め始めた。
岩窟から少し歩けば、夕焼けも、朝焼けも見ることができるのが岬の良いところだ。
「オレあそこの紫とオレンジの間の色が好き」
颯輝はかつてを思い出し、懐かしい思いと共にその場所を指し示した。
「俺は…もう少し上だな。颯輝よりほんの少し、上」
「やっぱ、似てるのは顔だけなんだなー。大星はやっと藍色になった頃が好きだって言ってた」
大星の言っていた色はもうかなり後方に追いやられていて、振り向かないと見ることができない。でも今は、今だけは、それは見ない。後ろを振り向かずにいたい。
「駒馳はな、もっともっと太陽近く。太陽が登る直前の水平線だって」
「シスコン」
「なんだよ!」
「お、返事したな」
「違う!そういう意味じゃ…」
「ほら、登るぞ」
気持ちが急くのか、早起きな小鳥に起こされたのか、東の空が大星の好きな色に変わる頃、颯輝は目が覚めた。
すると、いてもたっても居られない程、旅立ち前に日の出を見たくなった。
あの後戻ってきた北斗もすぐさま眠りについた。それなのに彼の寝起きは酷かった。揺さぶり叩き起こし、感服しつつも引き摺るようにしてここまで出てきた。
「うん、きれいだ」
「俺は眠い」
まだ言うか!と、颯輝は北斗に一瞬目をやるが、眠いと悪態をつきながらも、うっすら開けた瞼から彼はしっかり朝焼けを見ていた。
朝焼けにその瞳が不思議な色に染まっている。
穏やかな気分だった。
「大丈夫。きっと」
「…ああ」
オレンジ色が、眩しく岬を照らす。妹の好きな色が、2人を照らす。
不安は尽きない。それでも颯輝の心は希望で満ちていた。
古き友と新たな友が見つけてくれた突破口は、確実に颯輝の向かう未来に続いている自信があった。
段々と白に染まりゆく水平線は、希望の色だ。
頬を撫でる風が、足元の小さな花の綿毛を浚っていった。
風唄 本編12 [2008年06月19日(木)]
「兄貴」
静かに、白い顔がゆっくりと振り返る。顔色に似合わず、その口元は大体機嫌よく微笑みが刻まれている。
「ん?」
北斗を見留めた今も、それは変わらない。
兄ならきっと分かってくれるだろうという確信は、微笑む顔を見て何故か不安へと変化していった。
「あぁ、北斗。読みたかった本は見つかった?」
「うん、まあ」
先程あんな会話を交わした後。切り出す事が、こんなにも難しいなんて。
「あのさ」
意を決して、なんとか言葉を紡いだその時だった。
「たっだいまーん!!!」
廊下で話す2人の丁度真ん中にあった扉が、盛大な音を立てて開いた。
大声且つ場の空気を読まずに闖入してきたのは、北斗のすぐ上の姉だった。
我が家の女は、どうしてこうも強いのだろうか。
体中に渦巻いていた緊張はとりあえずどこかへ消え、呆れと脱力感で姉を見るしかなかった。
「…………」
「おかえり。遅かったね」
兄は、そんな時でも笑顔で彼女を出迎える。
「お兄、ただいま。何、北斗ってばそんな目であたしを見て。そんなにお姉様に会いたかった?」
そしてこの姉は、何かと因縁を付けては北斗を困らせるのだ。小さい頃はよく泣かされていたものだ。
北斗は彼女の言葉に応じず、出来るだけ視線を逸らし後ずさった。それを見た兄は口元に手を当て、声を殺して笑っている。
「飲んできたな…」
間違いない。姉の頬はいつもより若干赤く染まっており、目はきちんと開けられていない。
決め手は姉が乱入してきた時から漂い始めた、あの独特の匂いだ。
姉は酒が入ると益々絡んでくる。ターゲットは勿論北斗である。その質の悪さに、北斗はいつも閉口するのだ。
「そんな事どうだっていいのよ。会いたかったの?会いたくなかったの〜〜?」
据わった目で一歩ずつ近づいてくる。勿論答える気などさらさらない。
「な、」
どうしたものかと考える暇もなく、姉は突然北斗に突撃してきた。とてもじゃないが、避けられる隙はなかった。
「北斗くんってば〜〜、お姉さんに甘えたいならそう言いなさーーーい!」
「!?」
女性にしてはなかなか長身の姉に、一瞬で頭を彼女の脇腹に固定された。バランスを崩し、中腰になった体は上手く力が入らない。
「離せ!触るな!!」
高笑いしながら北斗の頭を掻き回す姉に、くぐもったその声は聞こえないようだ。
耳にのあたりに柔らかな何かが押し当てられるが、こんな姉じゃ嬉しくもなんともない。寧ろ迷惑だ。
北斗が己の不運を心の中で嘆いた時、兄が笑いを堪えながら助け船を出した。
「まって、ちょっと、その辺にしといてあげて。北斗は僕に話があるみたいなんだ」
よっぽど笑っていたのか、息も絶え絶えの兄の声が聞こえた。
「そーだ!だから離せよ!」
「何よぉ。何の話ぃ?」
北斗の言葉はどうやら無視されたらしい。そのままの格好で、腕の力が緩められる気配はない。
「男兄弟の会話だよ。決まってるじゃないか」
兄は呼吸も整ったらしく、いつものペースで柔らかく話す。北斗の視界は今、床しか見えないが、その顔は微笑んでいるに違いない。
彼が微笑んでる時は、大体が本気で楽しんでいる。常に笑っているイメージの兄は、簡単に言えば笑い上戸なのだ。
はいはい、と姉は半ば呆れたように北斗の首に掛かっていた腕を外し、あれだけしつこく絡んだ事が嘘のように踵を返した。
これぞまさに、鶴の一声。
「猥談なら部屋でやんなさいよ」
「おい!!」
片手をひらひらさせながら去って行く姉。最後に爆弾を落として帰っていった。
「本当に何でうちの女達って…」
北斗の呟きに、兄の笑い声はいよいよ本気のものとなり、目尻には涙が滲んでいる。
それを人差し指で拭うと、息も絶え絶え、彼は言った。
「それじゃあ、部屋に行こっか」
さっきの大笑いといい、今日の兄は調子も機嫌もいいようだ。
普段より若干早い動きで北斗を自室に促し座らせると、自分も寝台に腰を下ろした。
「それで、どうしたの?」
うん、と北斗は頷いた。もしかしたら、今から自分がやろうとしているのは家族への裏切り行為かもしれない。
そう思うと、なかなか切り出せなかった。
「あれっ?本当に好きな娘でもできたの?」
「違う!」
兄の目が少しだけ輝いたような、気のせいか?
「そっか」
輝いた割には、さして落胆した様子は見られない。
どこまで本気なのか、時々北斗でさえも読めないときがあるが、兄はこれでなかなか冗談好きなのだ。
「兄貴には言おうと思って。驚かないで聞いて欲しい」
「うん。あんまり驚くと胸が痛くなるから、驚かないよ」
「…………」
「どうしたの?」
「いや…」
我が家の強者は、女だけではないかもしれないと、今更ながら感じる北斗であった。
そんな兄のいつもと変わらない様子だったから、北斗は自分でも驚く程、その言葉はするりと流れ出た。
それこそが兄の狙いだと、北斗は見抜けなかった。
「俺、旅に出ようと思う」
しばしの沈黙。
北斗が見る兄は、暖かい茶を口元に運んでいる。
「そう」
静かな返事だった。
「帰りはいつになるかわからない。帰ってこれるかもわからない…けど、俺は行くって決めたんだ」
表面に息を吹きかけ、熱を飛ばしている。一口飲み下すと、兄は微笑んだ。
「そう」
北斗は安堵に包まれた。
「旅立ちは、いつ?」
「街を出るのは夜明け。でも合流しなければならない奴がいるから、もう家を出ようと思う」
コトリ、傍らにカップを置いた。あんなに湯気が立っていたのに、もう飲み干したらしい。
「それで…」
「大丈夫。みんなには僕からうまく言っておく。それが、僕に教えてくれた一番の理由だろ?」
兄が下の兄弟に慕われてるのは、こういったところにあるのだと思う。二歩も三歩も先を読んでいて、北斗は敵わないと心から感じる。
「…ありがとう」
「気をつけて」
「ああ」
何も聞かず、何も言わず。
神話に登場する神々が本当にいるのなら、何故、と問いたい。
こんなにも人の心を汲み取ことに長ける兄に、どうして脆弱な肉体しか与えなかったのか。
陽の光を浴びるに相応しい人間を、神は見抜けなかったのだろうか。
「兄貴は…俺が逃げてるって思わないのか?」
「思わないなぁ」
即答が嬉しかった。そう思ってくれる理由は聞かない。
「ね、北斗。僕なら大丈夫だから、心配しないで、自分と仲間の事だけ考えて、進むんだよ」
ぽん、と肩に手を置く兄に遠い昔がフラッシュバックした。
幼い頃にもこうして何かある度に、半ベソをかいた北斗を少し歳の離れたこの兄が肩や背中に手を置いて宥めてくれていた。
「これから兄貴には頭が上がらないな」
にっこり微笑んだ兄が返した。
「恩は高く売っとかないと」
漆黒に浮かぶ月や星が身を潜め、藍色から紫へ、そして清々しい空気と共にオレンジに水平線を染め始めた。
岩窟から少し歩けば、夕焼けも、朝焼けも見ることができるのが岬の良いところだ。
「オレあそこの紫とオレンジの間の色が好き」
颯輝はかつてを思い出し、懐かしい思いと共にその場所を指し示した。
「俺は…もう少し上だな。颯輝よりほんの少し、上」
「やっぱ、似てるのは顔だけなんだなー。大星はやっと藍色になった頃が好きだって言ってた」
大星の言っていた色はもうかなり後方に追いやられていて、振り向かないと見ることができない。でも今は、今だけは、それは見ない。後ろを振り向かずにいたい。
「駒馳はな、もっともっと太陽近く。太陽が登る直前の水平線だって」
「シスコン」
「なんだよ!」
「お、返事したな」
「違う!そういう意味じゃ…」
「ほら、登るぞ」
気持ちが急くのか、早起きな小鳥に起こされたのか、東の空が大星の好きな色に変わる頃、颯輝は目が覚めた。
すると、いてもたっても居られない程、旅立ち前に日の出を見たくなった。
あの後戻ってきた北斗もすぐさま眠りについた。それなのに彼の寝起きは酷かった。揺さぶり叩き起こし、感服しつつも引き摺るようにしてここまで出てきた。
「うん、きれいだ」
「俺は眠い」
まだ言うか!と、颯輝は北斗に一瞬目をやるが、眠いと悪態をつきながらも、うっすら開けた瞼から彼はしっかり朝焼けを見ていた。
朝焼けにその瞳が不思議な色に染まっている。
穏やかな気分だった。
「大丈夫。きっと」
「…ああ」
オレンジ色が、眩しく岬を照らす。妹の好きな色が、2人を照らす。
不安は尽きない。それでも颯輝の心は希望で満ちていた。
古き友と新たな友が見つけてくれた突破口は、確実に颯輝の向かう未来に続いている自信があった。
段々と白に染まりゆく水平線は、希望の色だ。
頬を撫でる風が、足元の小さな花の綿毛を浚っていった。
静かに、白い顔がゆっくりと振り返る。顔色に似合わず、その口元は大体機嫌よく微笑みが刻まれている。
「ん?」
北斗を見留めた今も、それは変わらない。
兄ならきっと分かってくれるだろうという確信は、微笑む顔を見て何故か不安へと変化していった。
「あぁ、北斗。読みたかった本は見つかった?」
「うん、まあ」
先程あんな会話を交わした後。切り出す事が、こんなにも難しいなんて。
「あのさ」
意を決して、なんとか言葉を紡いだその時だった。
「たっだいまーん!!!」
廊下で話す2人の丁度真ん中にあった扉が、盛大な音を立てて開いた。
大声且つ場の空気を読まずに闖入してきたのは、北斗のすぐ上の姉だった。
我が家の女は、どうしてこうも強いのだろうか。
体中に渦巻いていた緊張はとりあえずどこかへ消え、呆れと脱力感で姉を見るしかなかった。
「…………」
「おかえり。遅かったね」
兄は、そんな時でも笑顔で彼女を出迎える。
「お兄、ただいま。何、北斗ってばそんな目であたしを見て。そんなにお姉様に会いたかった?」
そしてこの姉は、何かと因縁を付けては北斗を困らせるのだ。小さい頃はよく泣かされていたものだ。
北斗は彼女の言葉に応じず、出来るだけ視線を逸らし後ずさった。それを見た兄は口元に手を当て、声を殺して笑っている。
「飲んできたな…」
間違いない。姉の頬はいつもより若干赤く染まっており、目はきちんと開けられていない。
決め手は姉が乱入してきた時から漂い始めた、あの独特の匂いだ。
姉は酒が入ると益々絡んでくる。ターゲットは勿論北斗である。その質の悪さに、北斗はいつも閉口するのだ。
「そんな事どうだっていいのよ。会いたかったの?会いたくなかったの〜〜?」
据わった目で一歩ずつ近づいてくる。勿論答える気などさらさらない。
「な、」
どうしたものかと考える暇もなく、姉は突然北斗に突撃してきた。とてもじゃないが、避けられる隙はなかった。
「北斗くんってば〜〜、お姉さんに甘えたいならそう言いなさーーーい!」
「!?」
女性にしてはなかなか長身の姉に、一瞬で頭を彼女の脇腹に固定された。バランスを崩し、中腰になった体は上手く力が入らない。
「離せ!触るな!!」
高笑いしながら北斗の頭を掻き回す姉に、くぐもったその声は聞こえないようだ。
耳にのあたりに柔らかな何かが押し当てられるが、こんな姉じゃ嬉しくもなんともない。寧ろ迷惑だ。
北斗が己の不運を心の中で嘆いた時、兄が笑いを堪えながら助け船を出した。
「まって、ちょっと、その辺にしといてあげて。北斗は僕に話があるみたいなんだ」
よっぽど笑っていたのか、息も絶え絶えの兄の声が聞こえた。
「そーだ!だから離せよ!」
「何よぉ。何の話ぃ?」
北斗の言葉はどうやら無視されたらしい。そのままの格好で、腕の力が緩められる気配はない。
「男兄弟の会話だよ。決まってるじゃないか」
兄は呼吸も整ったらしく、いつものペースで柔らかく話す。北斗の視界は今、床しか見えないが、その顔は微笑んでいるに違いない。
彼が微笑んでる時は、大体が本気で楽しんでいる。常に笑っているイメージの兄は、簡単に言えば笑い上戸なのだ。
はいはい、と姉は半ば呆れたように北斗の首に掛かっていた腕を外し、あれだけしつこく絡んだ事が嘘のように踵を返した。
これぞまさに、鶴の一声。
「猥談なら部屋でやんなさいよ」
「おい!!」
片手をひらひらさせながら去って行く姉。最後に爆弾を落として帰っていった。
「本当に何でうちの女達って…」
北斗の呟きに、兄の笑い声はいよいよ本気のものとなり、目尻には涙が滲んでいる。
それを人差し指で拭うと、息も絶え絶え、彼は言った。
「それじゃあ、部屋に行こっか」
さっきの大笑いといい、今日の兄は調子も機嫌もいいようだ。
普段より若干早い動きで北斗を自室に促し座らせると、自分も寝台に腰を下ろした。
「それで、どうしたの?」
うん、と北斗は頷いた。もしかしたら、今から自分がやろうとしているのは家族への裏切り行為かもしれない。
そう思うと、なかなか切り出せなかった。
「あれっ?本当に好きな娘でもできたの?」
「違う!」
兄の目が少しだけ輝いたような、気のせいか?
「そっか」
輝いた割には、さして落胆した様子は見られない。
どこまで本気なのか、時々北斗でさえも読めないときがあるが、兄はこれでなかなか冗談好きなのだ。
「兄貴には言おうと思って。驚かないで聞いて欲しい」
「うん。あんまり驚くと胸が痛くなるから、驚かないよ」
「…………」
「どうしたの?」
「いや…」
我が家の強者は、女だけではないかもしれないと、今更ながら感じる北斗であった。
そんな兄のいつもと変わらない様子だったから、北斗は自分でも驚く程、その言葉はするりと流れ出た。
それこそが兄の狙いだと、北斗は見抜けなかった。
「俺、旅に出ようと思う」
しばしの沈黙。
北斗が見る兄は、暖かい茶を口元に運んでいる。
「そう」
静かな返事だった。
「帰りはいつになるかわからない。帰ってこれるかもわからない…けど、俺は行くって決めたんだ」
表面に息を吹きかけ、熱を飛ばしている。一口飲み下すと、兄は微笑んだ。
「そう」
北斗は安堵に包まれた。
「旅立ちは、いつ?」
「街を出るのは夜明け。でも合流しなければならない奴がいるから、もう家を出ようと思う」
コトリ、傍らにカップを置いた。あんなに湯気が立っていたのに、もう飲み干したらしい。
「それで…」
「大丈夫。みんなには僕からうまく言っておく。それが、僕に教えてくれた一番の理由だろ?」
兄が下の兄弟に慕われてるのは、こういったところにあるのだと思う。二歩も三歩も先を読んでいて、北斗は敵わないと心から感じる。
「…ありがとう」
「気をつけて」
「ああ」
何も聞かず、何も言わず。
神話に登場する神々が本当にいるのなら、何故、と問いたい。
こんなにも人の心を汲み取ことに長ける兄に、どうして脆弱な肉体しか与えなかったのか。
陽の光を浴びるに相応しい人間を、神は見抜けなかったのだろうか。
「兄貴は…俺が逃げてるって思わないのか?」
「思わないなぁ」
即答が嬉しかった。そう思ってくれる理由は聞かない。
「ね、北斗。僕なら大丈夫だから、心配しないで、自分と仲間の事だけ考えて、進むんだよ」
ぽん、と肩に手を置く兄に遠い昔がフラッシュバックした。
幼い頃にもこうして何かある度に、半ベソをかいた北斗を少し歳の離れたこの兄が肩や背中に手を置いて宥めてくれていた。
「これから兄貴には頭が上がらないな」
にっこり微笑んだ兄が返した。
「恩は高く売っとかないと」
漆黒に浮かぶ月や星が身を潜め、藍色から紫へ、そして清々しい空気と共にオレンジに水平線を染め始めた。
岩窟から少し歩けば、夕焼けも、朝焼けも見ることができるのが岬の良いところだ。
「オレあそこの紫とオレンジの間の色が好き」
颯輝はかつてを思い出し、懐かしい思いと共にその場所を指し示した。
「俺は…もう少し上だな。颯輝よりほんの少し、上」
「やっぱ、似てるのは顔だけなんだなー。大星はやっと藍色になった頃が好きだって言ってた」
大星の言っていた色はもうかなり後方に追いやられていて、振り向かないと見ることができない。でも今は、今だけは、それは見ない。後ろを振り向かずにいたい。
「駒馳はな、もっともっと太陽近く。太陽が登る直前の水平線だって」
「シスコン」
「なんだよ!」
「お、返事したな」
「違う!そういう意味じゃ…」
「ほら、登るぞ」
気持ちが急くのか、早起きな小鳥に起こされたのか、東の空が大星の好きな色に変わる頃、颯輝は目が覚めた。
すると、いてもたっても居られない程、旅立ち前に日の出を見たくなった。
あの後戻ってきた北斗もすぐさま眠りについた。それなのに彼の寝起きは酷かった。揺さぶり叩き起こし、感服しつつも引き摺るようにしてここまで出てきた。
「うん、きれいだ」
「俺は眠い」
まだ言うか!と、颯輝は北斗に一瞬目をやるが、眠いと悪態をつきながらも、うっすら開けた瞼から彼はしっかり朝焼けを見ていた。
朝焼けにその瞳が不思議な色に染まっている。
穏やかな気分だった。
「大丈夫。きっと」
「…ああ」
オレンジ色が、眩しく岬を照らす。妹の好きな色が、2人を照らす。
不安は尽きない。それでも颯輝の心は希望で満ちていた。
古き友と新たな友が見つけてくれた突破口は、確実に颯輝の向かう未来に続いている自信があった。
段々と白に染まりゆく水平線は、希望の色だ。
頬を撫でる風が、足元の小さな花の綿毛を浚っていった。
風唄 本編11 [2008年06月18日(水)]
「『天と地は未だ無限で、両者はまた境がなかった―――』この無限の天と神は天地創造、2つの世界を作り出す。神の持つ無限の空と地面を少しだけ分けてもらうんだな」
「んん?分ける?」
「神話なんてお伽話みたいなもんだ。話半分で聞け」
「ふぁ〜い」
北斗は溜め息をついた。一日中書庫で探し物をしていたため、体がだるかった。しかし溜め息は、それによるものではない。
真実ではないだろうと今までずっと否定的に読んでいたそのお伽話。
それを信じなければならない事に、何か大きな負荷がかかっているような気がする。
存在そのものが証明である少年は、目の前にいるが…彼は何も知らないのだ。
「そのお伽話を一代目は信じて颯輝に施術した訳だ」
「北斗は信じないの?」「……信じるしかない、と今は思う」
颯輝は静かに微笑んだ。
「続き、頼む」
そんな彼を北斗は一瞥し、そして書物に目を落とす。
「神はさらに2つの大地にそれぞれ子供を生む。2つの世界は分け隔てられていたが、"扉"を介し交流し合う。やがて双方に人間が生まれ、増え…戦争が始まる。愚かな生き物だな」
颯輝は何も言わず、ただ黙って聞いている。
「神の子らは人間の戦争を嘆き、扉を閉めていく。扉は幾つか存在したことになってるんだな。そして、最後の扉だけを残し2人は自ら風に溶けて消える」
抽象的な言葉に首を傾げた。美しい表現ではあるが、それは自殺行為のように颯輝は感じた。
「何で…」
「2人の神の子は、例えるなら兄弟。さらに人間は神の子の産物。兄弟の子供同士の戦争は、辛かったんだろ」
颯輝は想像し小さく頷いた。それはきっと、2人にとって見ていたくない程悲しい戦争だったのだ。
「俺には神の子らが何故中途半端に扉ひとつ残し、消えていくのかがわからんな」
扉を前に悲しみを携え消え行く兄弟。きっとそこにあったものは―――。
「信じたかったんだろ。自分達の子供…人間のこと」
今度は北斗が黙る番だった。
「んで?答えは?」
彼はページをめくった。
「ここで今まで黙って見てた神が動く。『人間達の和平は望めぬと判断し、神は最後の扉を固く閉めた』…」
「それじゃ2人の希望、なくなっちゃうじゃん」
北斗は颯輝をちらりと見ただけで続けた。
「結び部分。ここが答えと言っていいだろう」
北斗は最後の一行を指し示す。颯輝には読めないが、本当に最後の部分だということは分かる。
「序章はこう終わる。『2つの世界が2度と交わらぬよう、時を曲げた』」
北斗の静かな声が終わり、辺りは静寂に支配される。月明かりが青白く、2人の顔を照らした。
「それって…」
「『時を曲げる』ことが具体的にどういうことなのか、それは俺にもわからない。だが颯輝が300年も超えなければならない理由はここにあると推理できるな。
そして『2つの世界』について。一方がこの世界と仮定すると…妹は、また別の世界に居るんじゃないか…と推測できる」
重量を感じさせる音をたてながら本を閉じた。相当な厚みだ。答えは、その中から僅かこれだけ。
北斗は文献を整理している時に、あることに気が付き、そしてあることを決意した。
新しい、信じられないような状況に身を置くことは、自分を脅かす恐怖となって襲うかもしれない。だがその反面、新たなものが見えてくる手掛かりとなる可能性だってあるだろう?
柄になく、好奇心が疼いている。
一方で、颯輝は難しい顔で頭を掻きむしった。
「2つの世界…」
目が大きく見開かれている。
「いーみわかんねぇ!時間を曲げたって、んなことできるわけないじゃん!」
そのまま仰向けに倒れ込んだ。背中に当たる石が痛い。月が、先程より高い位置で静かに佇んでいる。
北斗が隣に座る気配がした。空を見ているようだ。2人が動かないでいると、静寂が耳にうるさい。
「夜が明けたら、出発しよう」
静寂に良く似合う声だ。颯輝は思った。
「俺も行く」
「………え?」
「お前と子猫だけじゃ、このキビシー世の中を渡っていけなさそうだしな」
颯輝は思わず身を起こした。その目は大きく見開き、月の光が溢れ出んばかりに輝く。
「マジか!マジでか!?やったーーーー!!」
喜び勇んだ声に、マックスが飛び起き、完全に夜を切り裂いた。
共鳴するように遠くで魔物の咆哮が聞こえるのは、多分気のせいじゃない。
「ってことで…ほれ」
北斗が懐に手を突っ込むと、中から食料が出てきた。
颯輝は歓声をあげ、どこにそんなに隠していたのか、次々出てくるまだ温かみの感じる晩飯に飛びついた。マックスもさっきまで眠っていたのが嘘のように機敏な動きで自分の食料を確保している。
「それと旅に必要になりそうなものも持ってきた。ここで夜を明かそう。俺も…もう家には帰らない」
颯輝は動きを止めた。
「あと4人兄弟がいる。俺1人いなくなったって大丈…」
「ダメだ」
全て言い終わらない内に、颯輝ははっきりと制した。その声に、北斗ははっとする。
先程とは打って変わって真剣な表情がそこにあった。
「ちゃんと言わなきゃダメだ」
「………」
「突然家族がいなくなって、平気な訳ない」
血のつながりが、それ程までに大切と思った事はない。家族は生まれた時から傍にいて、当たり前のように暮らしていた。
だが、颯輝の場合は―――。
「悪い…」
颯輝は少し微笑んで首を振り、北斗は立ち上がった。
「今兄貴に言ってくる。お袋や親父じゃ止められそうだ」
「いってらっさーい」
「すぐ戻る」
「急がなくていいよ。朝まで時間はたっぷりだ」
頷き、北斗は駆けて行った。傍らを見ると、満足そうに目を細め、口元を舐めている小さな相棒がいる。
「駒馳、絶対見つけだそうな」
細められていた目は颯輝を見つめ、同意するかのように尻尾が跳ねる。
そのまま颯輝の腰に寄りかかるよう首を擦り寄せ、同じ方向を見て腰を下ろした。
妙なところで甘ったれな相棒もまた、颯輝には掛け替えのない家族であった。
「なぁ、駒馳に会ったら何したい?」
マックスも、あの時駒馳不在に戸惑っていた。
それ程までに2人と1匹は仲が良く、遠くから駒馳と戯れる姿を見ると、まるでもう1人弟ができたようだった。
彼は小さく唸って考えいる。颯輝は急かさず、また星を見ながら答えを待った。
いつしか唸り声が、猫科特有の喉を鳴らすようなあの音に変化し…。
颯輝は笑った。
「抱っこされたいの?じゃオレはマックスを抱いた駒馳をおんぶだな!」
小さかったあの子は今、どうしてるだろうか。知らない世界で、好き嫌いせず食事を摂り、ちゃんと大きくなっているだろうか。
本当に連れて帰ることができるのだろうか。飛び越えた時間は正しいのだろうか。ちゃんと会えるのだろうか。
不安はそれこそ溢れて尽きることはないが、今はただ懐かしい気持ちに身を浸したい。
たった1人の血を分けた兄妹。あの時誓った想いは、まだ生きている。
「北斗、帰ってこないけど先寝ちゃうか」
寝袋に潜り込んで目を閉じると、潮騒と、懐かしい妹の鼻歌が聞こえたような気がした。
風唄 本編10 [2008年06月18日(水)]
自然は変わらず受け入れてくれる。頭上に広がる星々もそうだ。
今正にきらめいていると感じた光も、この地まで辿り着くのまでに何億光年と時間がかかっているらしい。 少し近めの星ならば、300前に光を放って今届いたものもあるだろうか?光と同じ時間を超えた自分。 だとすれば、不思議な気分だ。
空気が澄んでいて、月と星が良く見える。薄くたなびく雲も、時折月光を僅かに弱める控え目な程度で、却って綺麗だと思う。
夜に、と北斗は言っていた。彼にとっての夜は一体いつ頃からなのか分からないが、陽が落ちてからは随分経った。
しかしこの夜の海と無限を感じる空を見ていれば、退屈など感じない。
穏やかな気持ちを颯輝に与えてくれるこの眺望は、紛れもない故郷であった。違う所はひとつだけだ。
妹がいない。
「昼飯はどうしたんだ?」
星座の絵を描き始めた颯輝に、後ろから声がかかった。この静寂を壊さない、低い声だ。
星の名を冠した友人とは、やはり似てないかもしれない。
膝を立てて、後ろに両手を付いて空を見上げていた颯輝は更に首を後方に回すと、逆さまに映った北斗を見留めた。
何か、別れた時よりも薄汚れている気がする。
「おー?」
「気が回らなくてすまんかった。何か食べたか?」
「簡易食食べたからだいじょーぶ」
「簡易食?」
「オレら一緒に凍ってたのがあったっぽい」
マックスはそこで行儀良く前足を揃えて寝ている。さっきまで一緒に星を見ていたと思ったのにいつの間に。
寝相は意外に悪いから、熟睡に入れば、その内腹を出して寝言を言い出すだろう。野生は何処へ、おかしな獣である。
「周到なご先祖様だな」
鼻で笑うように北斗が言った。大星の話題になると、毎回そんな態度だ。北斗は大星が嫌いなのだろうか?
「なあ、」
「待たせたのは俺だが、今まで何して時間潰してたんだ?」
「あ、うん。街中の店ぶらついたり」
言い出しはほぼ同時か若干颯輝が先であったというのに、北斗は強引とも言える声のトーンで喋った。
何かあったのだろうか?まだ出会ったばかりの友人だ。颯輝は無理に会話を曲げる事はしなかった。
「そうか。街並みは…やっぱり変わるものか?」
「や、意外にそんな変わってなかったなぁ。オレ、自分浮いてないかヒヤヒヤしたけどそーでもなかったし。
オレよりマックスが目立ってた」
「まあ…そんな生き物滅多に見かけないしな」
生き物の腹は白く、細く速く大地を蹴る足は今、宙を力無く泳いでいる。
閉じていたと思われた口元は、ゆっくり半開きになり、ムニャムニャと口周りを舐めた後また閉じられた。
「あ、外も少し散歩してきたぞ」
「旅立ち予行練習、ってところか」
「まーな。一匹、なんかと戦ってきた」
「なんか…まさか、魔物…?」
「うん!」
北斗の口元は何とか笑みを刻んでいるものの、その顔は嫌悪でいっぱいだ。
「まぁ…旅には避けて通れない相手…だろうしな」
ぶつぶつと何か言っている。マックスと2人、武器を持たない状態でも何とか勝利を収めることができたのだ。
魔物の数は多くなったのだろうが、強さの問題はないだろう。
「怖いのか?」
「まさか」
「ほんとかなぁ〜」
「馬鹿にするなよ」
颯輝の目には、嫌悪の顔がなくなって鼻で笑う彼の姿が強がりではないように映った。
「んで、そっちは?」
ああ、と北斗は傍らに置いていた幾つかの書物に手を伸ばす。古いのが一目瞭然だ。紙は完全に変色して、茶色く端が擦り切れている。
それを別段貴重品を触るふうな様子もなく、パラパラとページを撫でる。
「時間はかかったが幾つか見つけることはできた。家系図……は見ても別に面白くもなかった。見なくていい。神話の…ここだな。序章」
古びた書物を無造作に石の上に優しくもない手つきで置く。
そして比較的白い紙で、最近の物のように見える一冊の本を手にし、目的のページを開いた。
深緑の丁装は、触るとざらりとしている。
「颯輝、お前神話の内容知らないんだよな?」
「うん」
「そして一代目から詳しい話も聞いてない」
「うんうん」
「じゃあ…合ってるかわわからんが、俺の見解、聞くか?」
「うん!」
絵本の読み聞かせが始まる直前の子供のようだ。本当に屈託なくよく笑う。
北斗は一呼吸置き、序章を指し示した。
「神話が、しかも序文が答えそのものだった」
「答え?」
「本当に…これが正しい答えなら、こんなに簡単でいいのかってくらいだ」
「オレも読めばわかるかな?」
「無理だろ。古文字で書かれてる。300年前よりずっと古い言葉と文字だ」
颯輝より長く、骨ばった指が移動し、冒頭を指し示す。
「神話だから当然神が出てくる。世界を創造する所から始まる」
北斗は少し思案し、解説を始めた。
今正にきらめいていると感じた光も、この地まで辿り着くのまでに何億光年と時間がかかっているらしい。 少し近めの星ならば、300前に光を放って今届いたものもあるだろうか?光と同じ時間を超えた自分。 だとすれば、不思議な気分だ。
空気が澄んでいて、月と星が良く見える。薄くたなびく雲も、時折月光を僅かに弱める控え目な程度で、却って綺麗だと思う。
夜に、と北斗は言っていた。彼にとっての夜は一体いつ頃からなのか分からないが、陽が落ちてからは随分経った。
しかしこの夜の海と無限を感じる空を見ていれば、退屈など感じない。
穏やかな気持ちを颯輝に与えてくれるこの眺望は、紛れもない故郷であった。違う所はひとつだけだ。
妹がいない。
「昼飯はどうしたんだ?」
星座の絵を描き始めた颯輝に、後ろから声がかかった。この静寂を壊さない、低い声だ。
星の名を冠した友人とは、やはり似てないかもしれない。
膝を立てて、後ろに両手を付いて空を見上げていた颯輝は更に首を後方に回すと、逆さまに映った北斗を見留めた。
何か、別れた時よりも薄汚れている気がする。
「おー?」
「気が回らなくてすまんかった。何か食べたか?」
「簡易食食べたからだいじょーぶ」
「簡易食?」
「オレら一緒に凍ってたのがあったっぽい」
マックスはそこで行儀良く前足を揃えて寝ている。さっきまで一緒に星を見ていたと思ったのにいつの間に。
寝相は意外に悪いから、熟睡に入れば、その内腹を出して寝言を言い出すだろう。野生は何処へ、おかしな獣である。
「周到なご先祖様だな」
鼻で笑うように北斗が言った。大星の話題になると、毎回そんな態度だ。北斗は大星が嫌いなのだろうか?
「なあ、」
「待たせたのは俺だが、今まで何して時間潰してたんだ?」
「あ、うん。街中の店ぶらついたり」
言い出しはほぼ同時か若干颯輝が先であったというのに、北斗は強引とも言える声のトーンで喋った。
何かあったのだろうか?まだ出会ったばかりの友人だ。颯輝は無理に会話を曲げる事はしなかった。
「そうか。街並みは…やっぱり変わるものか?」
「や、意外にそんな変わってなかったなぁ。オレ、自分浮いてないかヒヤヒヤしたけどそーでもなかったし。
オレよりマックスが目立ってた」
「まあ…そんな生き物滅多に見かけないしな」
生き物の腹は白く、細く速く大地を蹴る足は今、宙を力無く泳いでいる。
閉じていたと思われた口元は、ゆっくり半開きになり、ムニャムニャと口周りを舐めた後また閉じられた。
「あ、外も少し散歩してきたぞ」
「旅立ち予行練習、ってところか」
「まーな。一匹、なんかと戦ってきた」
「なんか…まさか、魔物…?」
「うん!」
北斗の口元は何とか笑みを刻んでいるものの、その顔は嫌悪でいっぱいだ。
「まぁ…旅には避けて通れない相手…だろうしな」
ぶつぶつと何か言っている。マックスと2人、武器を持たない状態でも何とか勝利を収めることができたのだ。
魔物の数は多くなったのだろうが、強さの問題はないだろう。
「怖いのか?」
「まさか」
「ほんとかなぁ〜」
「馬鹿にするなよ」
颯輝の目には、嫌悪の顔がなくなって鼻で笑う彼の姿が強がりではないように映った。
「んで、そっちは?」
ああ、と北斗は傍らに置いていた幾つかの書物に手を伸ばす。古いのが一目瞭然だ。紙は完全に変色して、茶色く端が擦り切れている。
それを別段貴重品を触るふうな様子もなく、パラパラとページを撫でる。
「時間はかかったが幾つか見つけることはできた。家系図……は見ても別に面白くもなかった。見なくていい。神話の…ここだな。序章」
古びた書物を無造作に石の上に優しくもない手つきで置く。
そして比較的白い紙で、最近の物のように見える一冊の本を手にし、目的のページを開いた。
深緑の丁装は、触るとざらりとしている。
「颯輝、お前神話の内容知らないんだよな?」
「うん」
「そして一代目から詳しい話も聞いてない」
「うんうん」
「じゃあ…合ってるかわわからんが、俺の見解、聞くか?」
「うん!」
絵本の読み聞かせが始まる直前の子供のようだ。本当に屈託なくよく笑う。
北斗は一呼吸置き、序章を指し示した。
「神話が、しかも序文が答えそのものだった」
「答え?」
「本当に…これが正しい答えなら、こんなに簡単でいいのかってくらいだ」
「オレも読めばわかるかな?」
「無理だろ。古文字で書かれてる。300年前よりずっと古い言葉と文字だ」
颯輝より長く、骨ばった指が移動し、冒頭を指し示す。
「神話だから当然神が出てくる。世界を創造する所から始まる」
北斗は少し思案し、解説を始めた。
風唄 本編9 [2008年06月18日(水)]
300年前、始祖は何故颯輝の肉体を止める必要があったのだろうか。
300年後の今に何を求めだのだろうか。北斗は急ぎ家に入ると書庫に向かった。
それにしても、妹を助けたいがために、成功するかも分からぬ賭けに乗るなんて。
彼には他に家族はいなかったのだろうか?
「…北斗?」
静かな声に呼ばれて振り返ると、そこには白い顔をして立つ兄がいた。慌てて服が裂けている部分を隠す。
「朝食、どうしたんだ?」
「あ…」
何かに夢中になるとまず食事を忘れるのは、北斗の癖だった。
「みんな下の子達に食べられちゃったよ」
あの問題双子か…と嘆息を禁じ得ない。北斗が聞いた限りでは、妹は最近ダイエット中であるはずだった。
…もし自分だったら颯輝のように妹の為に氷に入れるだろうかと思わず考えてしまった。
「…肥えても知らん」
北斗の呟きに兄は小さく笑った。兄、姉、北斗、双子の妹と弟、五人いる兄弟の仲は悪くないと思う。
中でも兄と北斗は殊更良い。体の弱い兄と、あまり活動的とは言い難い北斗は馬が合った。
だが北斗は知っている。物静かであまり感情を表に出さぬ兄だが、いつも兄弟達を強い心で見守っているということ。
家族を強く思っていること。
「書庫に行こうと思って」
自分が書物を求めて書庫に行くことは珍しいことではない。それでも何故か、直感的に颯輝の事は伏した方が良いと思った。
兄は少し間を置いてから、そう、と穏やかな声で呟くと優しい瞳で北斗を見た。優しく、そして寂しげだった。
「…ごめんね、北斗」
兄は、北斗が家を継ぐのを嫌がっている事を知っている。言った訳ではないが、気付いている。その事だ。
兄の言葉を受けて小さく首を振った。
北斗に家を継がせるという、北斗にとっての悪運を強いてしまったのは自分のせいだと思っているのだ。
―――体が悪いのは、兄貴が悪いわけじゃない。
「じゃあ俺、本探してくる」
「昼はちゃんと食べるんだよ」
「分かってる」
今度は北斗が笑う番だった。兄は、家族を誰より大切にする。能力の問題だけではない。
家を継ぐに相応しいのは、自分でなく兄であると思っている。それならば、自分は喜んでサポートだってするのに。
「兄貴もあんまり体に負担かけるなよ」
嬉しそうな顔が、北斗に向けられた。
一面古びた紙独特の匂いがする。北斗が持ち込んだ本もあり、そこにある物全てが古い書物という訳ではないが、
その殆どが北斗の生まれる前からこの家にあるものだ。家の者はあまりここへは立ち入らないが、北斗が頻繁に出入りする。
よって目立って汚れている様子はない。ただし、それは入り口付近の北斗が好んで読む哲学の本がある場所のみだ。
「…探すのだけで骨が折れそうだ」
奥を覗いただけで、少し挫折しそうになった。
見た限り荒れている様子なく、全て本棚に収まってはいるが、どれも埃を被っており、尚且つ種類別になっていない。それも大量だ。
しかし。
「探すしかないだろ」
大星が颯輝に言ったヒント、神話の本を見つけ出す。それと役に立つかはわからないが、あれば家系図。
そして始祖、大星が綴った手記などあれば御の字だ。
北斗は踏み台に上がり、上段の本から手をかけた。色褪せた背表紙は、一見しただけでは何の文献だか判別できない。
そういった物は手に取って開かねばならない。
颯輝に手伝わせるべきだったか?
噎せかえりそうな埃を頭から被ったところで後悔しかかった。
これは自分が勝手に思い付いた事だ。そしておそらく自身の未来にも関わってくるだろう。
己を奮い立たせ北斗は本を引き抜いた。
数冊が頭を直撃、落下した。
―――…やっぱり手伝わせれば良かった。
北斗はひとり、悪態を付いた。
300年後の今に何を求めだのだろうか。北斗は急ぎ家に入ると書庫に向かった。
それにしても、妹を助けたいがために、成功するかも分からぬ賭けに乗るなんて。
彼には他に家族はいなかったのだろうか?
「…北斗?」
静かな声に呼ばれて振り返ると、そこには白い顔をして立つ兄がいた。慌てて服が裂けている部分を隠す。
「朝食、どうしたんだ?」
「あ…」
何かに夢中になるとまず食事を忘れるのは、北斗の癖だった。
「みんな下の子達に食べられちゃったよ」
あの問題双子か…と嘆息を禁じ得ない。北斗が聞いた限りでは、妹は最近ダイエット中であるはずだった。
…もし自分だったら颯輝のように妹の為に氷に入れるだろうかと思わず考えてしまった。
「…肥えても知らん」
北斗の呟きに兄は小さく笑った。兄、姉、北斗、双子の妹と弟、五人いる兄弟の仲は悪くないと思う。
中でも兄と北斗は殊更良い。体の弱い兄と、あまり活動的とは言い難い北斗は馬が合った。
だが北斗は知っている。物静かであまり感情を表に出さぬ兄だが、いつも兄弟達を強い心で見守っているということ。
家族を強く思っていること。
「書庫に行こうと思って」
自分が書物を求めて書庫に行くことは珍しいことではない。それでも何故か、直感的に颯輝の事は伏した方が良いと思った。
兄は少し間を置いてから、そう、と穏やかな声で呟くと優しい瞳で北斗を見た。優しく、そして寂しげだった。
「…ごめんね、北斗」
兄は、北斗が家を継ぐのを嫌がっている事を知っている。言った訳ではないが、気付いている。その事だ。
兄の言葉を受けて小さく首を振った。
北斗に家を継がせるという、北斗にとっての悪運を強いてしまったのは自分のせいだと思っているのだ。
―――体が悪いのは、兄貴が悪いわけじゃない。
「じゃあ俺、本探してくる」
「昼はちゃんと食べるんだよ」
「分かってる」
今度は北斗が笑う番だった。兄は、家族を誰より大切にする。能力の問題だけではない。
家を継ぐに相応しいのは、自分でなく兄であると思っている。それならば、自分は喜んでサポートだってするのに。
「兄貴もあんまり体に負担かけるなよ」
嬉しそうな顔が、北斗に向けられた。
一面古びた紙独特の匂いがする。北斗が持ち込んだ本もあり、そこにある物全てが古い書物という訳ではないが、
その殆どが北斗の生まれる前からこの家にあるものだ。家の者はあまりここへは立ち入らないが、北斗が頻繁に出入りする。
よって目立って汚れている様子はない。ただし、それは入り口付近の北斗が好んで読む哲学の本がある場所のみだ。
「…探すのだけで骨が折れそうだ」
奥を覗いただけで、少し挫折しそうになった。
見た限り荒れている様子なく、全て本棚に収まってはいるが、どれも埃を被っており、尚且つ種類別になっていない。それも大量だ。
しかし。
「探すしかないだろ」
大星が颯輝に言ったヒント、神話の本を見つけ出す。それと役に立つかはわからないが、あれば家系図。
そして始祖、大星が綴った手記などあれば御の字だ。
北斗は踏み台に上がり、上段の本から手をかけた。色褪せた背表紙は、一見しただけでは何の文献だか判別できない。
そういった物は手に取って開かねばならない。
颯輝に手伝わせるべきだったか?
噎せかえりそうな埃を頭から被ったところで後悔しかかった。
これは自分が勝手に思い付いた事だ。そしておそらく自身の未来にも関わってくるだろう。
己を奮い立たせ北斗は本を引き抜いた。
数冊が頭を直撃、落下した。
―――…やっぱり手伝わせれば良かった。
北斗はひとり、悪態を付いた。
風唄 本編8 [2008年06月18日(水)]
北斗はろくに挨拶もせずに行ってしまった。
彼の祖先にあたる大星は、共に成長をし、共に過ごした時間は妹の次と言っても過言ではない親友だ。
見間違える筈のない相手と北斗を文字通り見間違えてしまった訳だが、冷静な目で見れば、彼と親友は異なる箇所も多々あるように思える。
日の高さを見ると、約束の夜まではかなりの時間がありそうだった。
「どーすっかな。マックス?」
先程まで氷の中で共に300年眠り続けたと言うのに、眠たげにゆるりと目瞬きを繰り返している。
見つめる颯輝に、まるで眠気を払うかのように顔を左右に振って応えた。
「眠気覚ましにほんとに散歩にいこうか」
尻尾がひょこんと跳ね、マックスは腰を上げた。
外の魔物の数は少なくない。北斗はそう言っていたが、バトルで体を慣らすには丁度いいかもしれない。
武器は所持してなかったが、少し囓った体術がある。周りを彷徨いている雑魚ぐらいどうにかなるだろう。
視線を感じて振り向くと、散歩を待ち望むマックスの姿がある。
小さな体に隠されている爪と牙は、実際はかなりの威力を持って敵に食い込んでいく。
大丈夫、自分には頼れる相棒もいる。
少し歩くと、潮の匂いがした。僅かな微風が運んでくる、海の香り。空と同じように、それは変わらず颯輝を迎えた。
懐かしい思いにとらわれ、颯輝は込み上げる気持ちを言葉にする事ができなかった。
水面に太陽が眩しく輝き、小波が砂を攫う。泡の粒は白くはじけて、また海に溶け込む。颯輝の髪が風に揺れた。
外は変わったらしい。しかし、この光景は紛れもなく颯輝の知る海だった。
「行こうか」
マックスもこの光景を静かに眺めていたようだ。颯輝の言葉に耳を動かして、足元に駆け寄ってきた。
風景が変わっているかも、道を行ったら迷うかもしれない。海まで降りて行って海岸沿いを歩く事にした。
300年前ならば、そのまま街の外へと出れた筈だ。
左手には海。右手の少し遠くには、背の低い煉瓦造りの家々や店と木々が見える。
18年過ごした場所。決して大きくはないこの街で、颯輝は駒馳と、そして両親とで生活してきた。
幼い時には兄妹に大星も混ざって3人で街の隅にある森を探検したり、街の中を彷徨いては裏道の発見に精をだした。
夕方には今歩いている海岸とは方角的に真逆の砂浜まで歩いて行き、そこで夕日を見てから帰るのが駒馳のお気に入りだった。
この街は三方を海に囲まれていて、漁業が栄えている。港町であるが故に、時折旅人が一時の休息に利用することもあるようだった。
今はどうなのだろう?
朝日の海岸と砂浜の夕日。颯輝は今、朝日が見える海沿いを歩いている。
もう少し海まで近づいて魚でも見てこようか、そう思ったが止めることにした。
もし、岩場で足をとられて海に落ちたりなどしたら…泳げない颯輝はそれこと生死に関わる問題だ。
「…っと!」
そんな事を考えながら歩いていたら、不思議な壁にぶつかりそうになった。
「なんだこれ?」
辺りを見渡すと、もう街の外へとあと僅かというところだった。先ほど見えていた家々は後方にある。
また正面に向き合うと、相変わらず不思議な隔たりはそこにあった。
自分の記憶を手繰ってみても、こんな所にこんな物は無かったと思う。
マックスも恐る恐る近づいて、様子を窺っているようだ。
それは無色透明で、あちら側が見えるが波打っているように歪に形をかえている。
息をかけても不規則に波打つ様子は変わらない。
颯輝は指先を近付け、触れてみようとした。しかし、それはできなかった。
「……すげー…」
人差し指でゆっくりと触れるつもりだったが、それは颯輝の指を避けるように円形に空間を作った。
そのまま手を開いてみると、円は颯輝の手に触れることなく広がった。
「いけるみたいだ、マックス」
マックスも鼻先を近づけた、するとやはり同じ様にそれは彼の少し湿った鼻を避けた。
状況把握を終了すると、四本足は少し後退した。その間颯輝は片手をつっこんだままだ。
「んじゃ、いっちょ行き…っておーい!」
マックスが後退したその場から突然加速をつけ、一足先に不思議な壁をすり抜けた。
それを見た颯輝も慌てて前進した。きっと目を瞑っていたらここに隔たりがあることなど解らないだろう。
肌にはなんの感覚もなく、街を出た。
しかし外の空気は明らかに違っている。風の匂いが違うのかもしれない。振り返ると、街は白い壁だった。
街側から見たら無色透明な不思議な壁は、外界から見たら濃厚な霧となって街を隠しているようだ。
一体何のために。その答えは北斗の言葉にあった。
「そんなに増えてるのかな…」
魔物達は、街の人々にとって思った以上に脅威らしい。
颯輝は動物達の気持ちや感情を汲み取ることを得意とする。
不思議な事に、顔や声を聞けば、手に取るように言いたいことが伝わってくる。
しかし魔物と呼ばれる彼等の言葉は聞こえない。心を伝えてくる前に、牙を剥く。
それを今嘆いても仕方がない。颯輝は辺りを見渡した。
風景は、そんなに変わっていないように思える。徐に転がる岩、気ままに伸びる雑草と、点々と生える木々。
遠くに見える禿げ山は、かつてと同じく禿げたままだった。
「散歩…にしてはおもしろくないコースかも」
颯輝は遠くへ行き過ぎぬよう、背が高めの木に歩みを進めた。登ればもう少し遠くまで見渡せるかもしれない。
マックスも蝶と戯れつつも傍らを離れず、颯輝に寄り添った。
登れそうな木であろうか。颯輝がその表皮が如何なるものか、触って確かめようとしたその時だった。
風向きが少し変わった。警告はそれだけで十分だった。
声をあげるより早く、咄嗟に颯輝とマックスは左右に分散するよう飛び退いた。
それとほぼ同時に土が抉られるような衝撃音と砂埃が辺りを支配する。
すぐさま颯輝は地に片手を付き、次の体制に立て直せるよう重心を移動した。
あちらを見遣るとマックスも同様、低く唸って戦闘態勢に入っている。
突如として空から降ってきた濃紺の物体。それは颯輝とマックスの間を割って入ってきた。
サイズは自分の背丈と同じ程度か、少し大きいか。皮膚は分厚く乾燥していて頑丈そうだ。
動物に置き換えたら、トカゲとコウモリの間というところだろう。もっとも、その羽は四枚もあるが。
咆哮は耳を塞ぎたくなるような不快な声色と音量、それに意志を汲み取ることはできない。それが颯輝にとっての何よりの証明。
魔物だった。
こんな早く出会えると思わなかった。ここで北斗の言葉を体感した訳だ。
魔物は大きく羽を広げた。瞳は暗黒で、颯輝を見つめている。照準は自分、下手に動くことはできない。次は何がくる?
しかしマックスが動き出す方が早かった。小さな体躯を生かし、素早く魔物の足元縫って気を逸らす。
羽ばたきで真空を生み出し、颯輝を狙っていた魔物の集中力が分散した。
その僅かな隙を見逃さず、横に転がるようにして危うげなく颯輝はその攻撃をかわした。
横目で見ると、もと居た場所の足元に転がっていたはずの岩や石は粉砕され、細かな砂となり果てていた。
「マックス…サンキュー」
彼がいなかったら、旅立ち前に人生が終わっていたかもしれない。
すぐさま颯輝は駆け出した。同時にマックスも相手に飛びつく。息はぴったりだ。
がっちりの爪を立て、敵の喉仏に噛みついている。
分厚い皮膚の持ち主にそれはあまり効果的な攻撃とは言えないが、マックスに気をとられている間に、颯輝が素早く回り込み一枚の羽に狙いを絞った。
怒り狂った敵が頭を左右に揺らしてマックス振り落とした。
颯輝は体を捻り、右足は羽の付け根を狙う。先程の攻撃で理解したのだが、この魔物は主に羽から攻撃を行うようだ。
そこを蹴り落とせば―――。
だが敵もそう簡単にはさせてくれなかった。
マックスが首から離れるやいなや、素早く体を半回転させ結果的に狙っていた羽の付け根部分よりやや先に蹴りを入れることになった。
それでも素早い蹴りは羽の一部に亀裂を生じさせ、僅かながらダメージを与えた。
再び魔物は颯輝と向き合う形となった。羽を損傷したことで怒り狂っている。
叫び声をあげながらそのままの勢いで、颯輝に爪で襲いかかってくる。
喰らったら大変なダメージだろうが、直線的な攻撃だ。
颯輝は意識を集中し、敵の右からの攻撃を腕で払うように流した。
間髪いれずに少し屈んで上体を捻り、相手の喉仏を上に向かって肘鉄を喰らわせた。
唾液が跳ね、敵はふらつくように、颯輝は軽いフットワークで後退し、両者の間に間合いが生み出された。
マックスが素早く颯輝の横につく。
「今のは効いたろー!?」
次はどう来るのだろう。颯輝は息を整えつつ敵を見据えた。
敵は項垂れていた頭をゆるりと元の位置に戻し、低い声で唸っている。
「おいおいおい…?」
体勢を立て直した相手を見ると硬い体表の賜物だろうか、敵に大きなダメージはなさそうだった。
運動量はほんの少しだというのに汗が額を伝う。嫌な感じだ。
マックスは顎を引いて、静かに敵の目を見続けている。自分の何倍もの大きさの魔物だというのに、引けを取る箇所はひとつもない。
「マックス、行けるか」
その様子から、行けないはずがないと分かりつつ声をかけた。
彼は颯輝を見ることも唸ることもしなかったが、彼の前を向いていた耳がこちら側に少し動いたのをしっかりと確認した。
深く、長く、息を吐く。
敵は大地を掻いて、颯輝を見つめることを止めない。自然に手が拳を作っていた。
颯輝も目を逸らすことはしない。木々のざわめきも、頬に当たっているはずの風の音も聞こえなくなった。
集中力が最大まで引き出されている。しかし颯輝は肉体の緊張とはうらはらに、不思議と心は落ち着いているのを自覚した。
息を吸い終えたのと同時に、颯輝とマックスは踏み出した。
マックスのしなやかな体躯はそれを裏切る速さで敵に襲いかかろうとしている。颯輝は注目を自分に向けるため、正面から突っ込んでいく。
敵が低いうなり声と共に負傷した羽を広げた。
また来る―――!!
「マックス!!」
弾丸のように駆けているマックスはすぐさま軌道を変更し、敵の右手に出る。
颯輝は正面からの衝撃波を高く跳躍する事でかわした。体を捻り、そのまま敵の上空を通過する。
颯輝の着地とほぼ同時に、今度はマックスが飛び付き、隠されていた爪が露わとなって敵に襲いかかった。
素早い一撃は、相手の右目に深い傷を負わせた。
「うらぁ!!」
敵は苦悶にのた打ち狂ったかのように頭を振っている。颯輝は敵の顔面がこちらを向いた瞬間、
その横っ面に渾身の力を込めて左から拳を叩き込んだ。右目を潰した魔物の堅い皮膚に、確かな手応えを感じた。
敵は一瞬ふらつくと、胴体から地に倒れ込んだ。その様子が、颯輝にはスローに見えた。
「やったか……?」
乱れた呼吸を整えつつ、颯輝は倒れた魔物の様子をうかがった。不用意に近づくのは危険だ。
マックスが頭を振って尾を一度揺らした。長めのそれはしなやかな動きで体のバランスをとっているかのようだ。
見たところ、大きな怪我はなさそうだった。
魔物は苦しげに浅く早く呼吸を繰り返し、時折前足がびくりと痙攣を起こしている。
それを見たマックスは小さく唸り警戒を露わにするが、颯輝はそれを制した。
「…もう帰ろ、マックス」
散歩を続行する気にはなれなかった。
彼の祖先にあたる大星は、共に成長をし、共に過ごした時間は妹の次と言っても過言ではない親友だ。
見間違える筈のない相手と北斗を文字通り見間違えてしまった訳だが、冷静な目で見れば、彼と親友は異なる箇所も多々あるように思える。
日の高さを見ると、約束の夜まではかなりの時間がありそうだった。
「どーすっかな。マックス?」
先程まで氷の中で共に300年眠り続けたと言うのに、眠たげにゆるりと目瞬きを繰り返している。
見つめる颯輝に、まるで眠気を払うかのように顔を左右に振って応えた。
「眠気覚ましにほんとに散歩にいこうか」
尻尾がひょこんと跳ね、マックスは腰を上げた。
外の魔物の数は少なくない。北斗はそう言っていたが、バトルで体を慣らすには丁度いいかもしれない。
武器は所持してなかったが、少し囓った体術がある。周りを彷徨いている雑魚ぐらいどうにかなるだろう。
視線を感じて振り向くと、散歩を待ち望むマックスの姿がある。
小さな体に隠されている爪と牙は、実際はかなりの威力を持って敵に食い込んでいく。
大丈夫、自分には頼れる相棒もいる。
少し歩くと、潮の匂いがした。僅かな微風が運んでくる、海の香り。空と同じように、それは変わらず颯輝を迎えた。
懐かしい思いにとらわれ、颯輝は込み上げる気持ちを言葉にする事ができなかった。
水面に太陽が眩しく輝き、小波が砂を攫う。泡の粒は白くはじけて、また海に溶け込む。颯輝の髪が風に揺れた。
外は変わったらしい。しかし、この光景は紛れもなく颯輝の知る海だった。
「行こうか」
マックスもこの光景を静かに眺めていたようだ。颯輝の言葉に耳を動かして、足元に駆け寄ってきた。
風景が変わっているかも、道を行ったら迷うかもしれない。海まで降りて行って海岸沿いを歩く事にした。
300年前ならば、そのまま街の外へと出れた筈だ。
左手には海。右手の少し遠くには、背の低い煉瓦造りの家々や店と木々が見える。
18年過ごした場所。決して大きくはないこの街で、颯輝は駒馳と、そして両親とで生活してきた。
幼い時には兄妹に大星も混ざって3人で街の隅にある森を探検したり、街の中を彷徨いては裏道の発見に精をだした。
夕方には今歩いている海岸とは方角的に真逆の砂浜まで歩いて行き、そこで夕日を見てから帰るのが駒馳のお気に入りだった。
この街は三方を海に囲まれていて、漁業が栄えている。港町であるが故に、時折旅人が一時の休息に利用することもあるようだった。
今はどうなのだろう?
朝日の海岸と砂浜の夕日。颯輝は今、朝日が見える海沿いを歩いている。
もう少し海まで近づいて魚でも見てこようか、そう思ったが止めることにした。
もし、岩場で足をとられて海に落ちたりなどしたら…泳げない颯輝はそれこと生死に関わる問題だ。
「…っと!」
そんな事を考えながら歩いていたら、不思議な壁にぶつかりそうになった。
「なんだこれ?」
辺りを見渡すと、もう街の外へとあと僅かというところだった。先ほど見えていた家々は後方にある。
また正面に向き合うと、相変わらず不思議な隔たりはそこにあった。
自分の記憶を手繰ってみても、こんな所にこんな物は無かったと思う。
マックスも恐る恐る近づいて、様子を窺っているようだ。
それは無色透明で、あちら側が見えるが波打っているように歪に形をかえている。
息をかけても不規則に波打つ様子は変わらない。
颯輝は指先を近付け、触れてみようとした。しかし、それはできなかった。
「……すげー…」
人差し指でゆっくりと触れるつもりだったが、それは颯輝の指を避けるように円形に空間を作った。
そのまま手を開いてみると、円は颯輝の手に触れることなく広がった。
「いけるみたいだ、マックス」
マックスも鼻先を近づけた、するとやはり同じ様にそれは彼の少し湿った鼻を避けた。
状況把握を終了すると、四本足は少し後退した。その間颯輝は片手をつっこんだままだ。
「んじゃ、いっちょ行き…っておーい!」
マックスが後退したその場から突然加速をつけ、一足先に不思議な壁をすり抜けた。
それを見た颯輝も慌てて前進した。きっと目を瞑っていたらここに隔たりがあることなど解らないだろう。
肌にはなんの感覚もなく、街を出た。
しかし外の空気は明らかに違っている。風の匂いが違うのかもしれない。振り返ると、街は白い壁だった。
街側から見たら無色透明な不思議な壁は、外界から見たら濃厚な霧となって街を隠しているようだ。
一体何のために。その答えは北斗の言葉にあった。
「そんなに増えてるのかな…」
魔物達は、街の人々にとって思った以上に脅威らしい。
颯輝は動物達の気持ちや感情を汲み取ることを得意とする。
不思議な事に、顔や声を聞けば、手に取るように言いたいことが伝わってくる。
しかし魔物と呼ばれる彼等の言葉は聞こえない。心を伝えてくる前に、牙を剥く。
それを今嘆いても仕方がない。颯輝は辺りを見渡した。
風景は、そんなに変わっていないように思える。徐に転がる岩、気ままに伸びる雑草と、点々と生える木々。
遠くに見える禿げ山は、かつてと同じく禿げたままだった。
「散歩…にしてはおもしろくないコースかも」
颯輝は遠くへ行き過ぎぬよう、背が高めの木に歩みを進めた。登ればもう少し遠くまで見渡せるかもしれない。
マックスも蝶と戯れつつも傍らを離れず、颯輝に寄り添った。
登れそうな木であろうか。颯輝がその表皮が如何なるものか、触って確かめようとしたその時だった。
風向きが少し変わった。警告はそれだけで十分だった。
声をあげるより早く、咄嗟に颯輝とマックスは左右に分散するよう飛び退いた。
それとほぼ同時に土が抉られるような衝撃音と砂埃が辺りを支配する。
すぐさま颯輝は地に片手を付き、次の体制に立て直せるよう重心を移動した。
あちらを見遣るとマックスも同様、低く唸って戦闘態勢に入っている。
突如として空から降ってきた濃紺の物体。それは颯輝とマックスの間を割って入ってきた。
サイズは自分の背丈と同じ程度か、少し大きいか。皮膚は分厚く乾燥していて頑丈そうだ。
動物に置き換えたら、トカゲとコウモリの間というところだろう。もっとも、その羽は四枚もあるが。
咆哮は耳を塞ぎたくなるような不快な声色と音量、それに意志を汲み取ることはできない。それが颯輝にとっての何よりの証明。
魔物だった。
こんな早く出会えると思わなかった。ここで北斗の言葉を体感した訳だ。
魔物は大きく羽を広げた。瞳は暗黒で、颯輝を見つめている。照準は自分、下手に動くことはできない。次は何がくる?
しかしマックスが動き出す方が早かった。小さな体躯を生かし、素早く魔物の足元縫って気を逸らす。
羽ばたきで真空を生み出し、颯輝を狙っていた魔物の集中力が分散した。
その僅かな隙を見逃さず、横に転がるようにして危うげなく颯輝はその攻撃をかわした。
横目で見ると、もと居た場所の足元に転がっていたはずの岩や石は粉砕され、細かな砂となり果てていた。
「マックス…サンキュー」
彼がいなかったら、旅立ち前に人生が終わっていたかもしれない。
すぐさま颯輝は駆け出した。同時にマックスも相手に飛びつく。息はぴったりだ。
がっちりの爪を立て、敵の喉仏に噛みついている。
分厚い皮膚の持ち主にそれはあまり効果的な攻撃とは言えないが、マックスに気をとられている間に、颯輝が素早く回り込み一枚の羽に狙いを絞った。
怒り狂った敵が頭を左右に揺らしてマックス振り落とした。
颯輝は体を捻り、右足は羽の付け根を狙う。先程の攻撃で理解したのだが、この魔物は主に羽から攻撃を行うようだ。
そこを蹴り落とせば―――。
だが敵もそう簡単にはさせてくれなかった。
マックスが首から離れるやいなや、素早く体を半回転させ結果的に狙っていた羽の付け根部分よりやや先に蹴りを入れることになった。
それでも素早い蹴りは羽の一部に亀裂を生じさせ、僅かながらダメージを与えた。
再び魔物は颯輝と向き合う形となった。羽を損傷したことで怒り狂っている。
叫び声をあげながらそのままの勢いで、颯輝に爪で襲いかかってくる。
喰らったら大変なダメージだろうが、直線的な攻撃だ。
颯輝は意識を集中し、敵の右からの攻撃を腕で払うように流した。
間髪いれずに少し屈んで上体を捻り、相手の喉仏を上に向かって肘鉄を喰らわせた。
唾液が跳ね、敵はふらつくように、颯輝は軽いフットワークで後退し、両者の間に間合いが生み出された。
マックスが素早く颯輝の横につく。
「今のは効いたろー!?」
次はどう来るのだろう。颯輝は息を整えつつ敵を見据えた。
敵は項垂れていた頭をゆるりと元の位置に戻し、低い声で唸っている。
「おいおいおい…?」
体勢を立て直した相手を見ると硬い体表の賜物だろうか、敵に大きなダメージはなさそうだった。
運動量はほんの少しだというのに汗が額を伝う。嫌な感じだ。
マックスは顎を引いて、静かに敵の目を見続けている。自分の何倍もの大きさの魔物だというのに、引けを取る箇所はひとつもない。
「マックス、行けるか」
その様子から、行けないはずがないと分かりつつ声をかけた。
彼は颯輝を見ることも唸ることもしなかったが、彼の前を向いていた耳がこちら側に少し動いたのをしっかりと確認した。
深く、長く、息を吐く。
敵は大地を掻いて、颯輝を見つめることを止めない。自然に手が拳を作っていた。
颯輝も目を逸らすことはしない。木々のざわめきも、頬に当たっているはずの風の音も聞こえなくなった。
集中力が最大まで引き出されている。しかし颯輝は肉体の緊張とはうらはらに、不思議と心は落ち着いているのを自覚した。
息を吸い終えたのと同時に、颯輝とマックスは踏み出した。
マックスのしなやかな体躯はそれを裏切る速さで敵に襲いかかろうとしている。颯輝は注目を自分に向けるため、正面から突っ込んでいく。
敵が低いうなり声と共に負傷した羽を広げた。
また来る―――!!
「マックス!!」
弾丸のように駆けているマックスはすぐさま軌道を変更し、敵の右手に出る。
颯輝は正面からの衝撃波を高く跳躍する事でかわした。体を捻り、そのまま敵の上空を通過する。
颯輝の着地とほぼ同時に、今度はマックスが飛び付き、隠されていた爪が露わとなって敵に襲いかかった。
素早い一撃は、相手の右目に深い傷を負わせた。
「うらぁ!!」
敵は苦悶にのた打ち狂ったかのように頭を振っている。颯輝は敵の顔面がこちらを向いた瞬間、
その横っ面に渾身の力を込めて左から拳を叩き込んだ。右目を潰した魔物の堅い皮膚に、確かな手応えを感じた。
敵は一瞬ふらつくと、胴体から地に倒れ込んだ。その様子が、颯輝にはスローに見えた。
「やったか……?」
乱れた呼吸を整えつつ、颯輝は倒れた魔物の様子をうかがった。不用意に近づくのは危険だ。
マックスが頭を振って尾を一度揺らした。長めのそれはしなやかな動きで体のバランスをとっているかのようだ。
見たところ、大きな怪我はなさそうだった。
魔物は苦しげに浅く早く呼吸を繰り返し、時折前足がびくりと痙攣を起こしている。
それを見たマックスは小さく唸り警戒を露わにするが、颯輝はそれを制した。
「…もう帰ろ、マックス」
散歩を続行する気にはなれなかった。
風唄 本編7 [2008年06月18日(水)]
言葉通り、すぐにでも旅立ちたい気分だった。300年分のブランク。
それに対して不安を感じない訳ではなかったが、スタートで足踏みしたくなかった。
「大丈夫なのか?」
北斗が心配の眼差しを向けてくる。颯輝はそれが少し嬉しくて、顔が別の種類の笑顔に変化するのを自覚した。
「大丈夫!って言いたいところだけど、それはやってみないとわかんねーからなぁ」
北斗はその笑顔に応える事なく目を細め、眉根を少しだけ寄せている。何を考えているのだろう?颯輝は続けた。
「オレにとってはたった1人の家族。大丈夫じゃなくても、駒馳に会えるなら乗り越えてやるって」
「…とんでもないシスコンだな」
「うるっせーな」
照れながら笑う颯輝に、北斗は声を出さず口角を少しだけ上げてからまたもとの表情に戻った。
「旅立ち、少し待て」
え?という言葉が出る前に、北斗がまた言った。
「そうだな…今日の夜まで待て。一代目の言った意味、情報を持ってからだって旅立ちは遅くはない。俺が家の文献から調べてやろう。…颯輝の話聞いて、俺自身考えたい事がでてきた。どうだ?」
「お…おぉ…」
反射的に頷いてしまった颯輝だが、それだけ北斗の眼差しは真剣だった。
確かに、自分が居た時代より300年の月日が流れたらしいこの世界。
300年という時の流れは、世界が変わるには十分な時間なのだろうか?
「肉体の時を止めた頃はどんなものだったか知らないが、この時代、外にいる魔物の数は少なくない」
「…マジで?」
頭の中を見透かされたように、北斗の声が降ってきた。以前は街や村の外でも、そう簡単に魔物と遭遇する事なんて少なかったような気がする。
「夜まで、散歩でもしてきたらどうだ?」
北斗は立ち上がった。髪の毛はいつの間にか殆ど乾いている。
あまり陽の差し込まない岩窟ではあるが、入り口を見遣ると太陽はもうだいぶ高くなっていることが窺える。
続いて颯輝も、膝の上で腹を出し完全リラックス状態のマックスを下ろした。勢いをつけて立ち上がり身震いをした。
久々に立ち上がった為だろうか、少しふらついた後首と肩を回す。良好だ。
北斗はもう陽の当たる所まで出ている。砂利に足をとられながらも、少し小走りに颯輝が続く。
足元の水たまりが跳ね、彼のふくらはぎを濡らす。
頬に暖かさを感じて見上げると、反射的に目を細めてしまった。
そこにある空は、変わらず青かった。
大きく息を吸う。
新鮮な空気が肺の中に立ち込めて、自分の存在ではなく、世界の存在を実感したような気がした。
この青は、どんな塗料を使用しても表現出来ないと思う。恐ろしく澄んだ空に、颯輝は暫し見蕩れた。
「じゃ、夜に。勝手に出発するんじゃないぞ」
「………あぁ」
心ここにあらず、そんな返事に北斗は尋ねた。
「そんなに空が懐かしいか?」
漸く颯輝は空を見ることを止め、北斗と向き合った。
この空に似つかわしい、良く晴れた笑顔だった。
それに対して不安を感じない訳ではなかったが、スタートで足踏みしたくなかった。
「大丈夫なのか?」
北斗が心配の眼差しを向けてくる。颯輝はそれが少し嬉しくて、顔が別の種類の笑顔に変化するのを自覚した。
「大丈夫!って言いたいところだけど、それはやってみないとわかんねーからなぁ」
北斗はその笑顔に応える事なく目を細め、眉根を少しだけ寄せている。何を考えているのだろう?颯輝は続けた。
「オレにとってはたった1人の家族。大丈夫じゃなくても、駒馳に会えるなら乗り越えてやるって」
「…とんでもないシスコンだな」
「うるっせーな」
照れながら笑う颯輝に、北斗は声を出さず口角を少しだけ上げてからまたもとの表情に戻った。
「旅立ち、少し待て」
え?という言葉が出る前に、北斗がまた言った。
「そうだな…今日の夜まで待て。一代目の言った意味、情報を持ってからだって旅立ちは遅くはない。俺が家の文献から調べてやろう。…颯輝の話聞いて、俺自身考えたい事がでてきた。どうだ?」
「お…おぉ…」
反射的に頷いてしまった颯輝だが、それだけ北斗の眼差しは真剣だった。
確かに、自分が居た時代より300年の月日が流れたらしいこの世界。
300年という時の流れは、世界が変わるには十分な時間なのだろうか?
「肉体の時を止めた頃はどんなものだったか知らないが、この時代、外にいる魔物の数は少なくない」
「…マジで?」
頭の中を見透かされたように、北斗の声が降ってきた。以前は街や村の外でも、そう簡単に魔物と遭遇する事なんて少なかったような気がする。
「夜まで、散歩でもしてきたらどうだ?」
北斗は立ち上がった。髪の毛はいつの間にか殆ど乾いている。
あまり陽の差し込まない岩窟ではあるが、入り口を見遣ると太陽はもうだいぶ高くなっていることが窺える。
続いて颯輝も、膝の上で腹を出し完全リラックス状態のマックスを下ろした。勢いをつけて立ち上がり身震いをした。
久々に立ち上がった為だろうか、少しふらついた後首と肩を回す。良好だ。
北斗はもう陽の当たる所まで出ている。砂利に足をとられながらも、少し小走りに颯輝が続く。
足元の水たまりが跳ね、彼のふくらはぎを濡らす。
頬に暖かさを感じて見上げると、反射的に目を細めてしまった。
そこにある空は、変わらず青かった。
大きく息を吸う。
新鮮な空気が肺の中に立ち込めて、自分の存在ではなく、世界の存在を実感したような気がした。
この青は、どんな塗料を使用しても表現出来ないと思う。恐ろしく澄んだ空に、颯輝は暫し見蕩れた。
「じゃ、夜に。勝手に出発するんじゃないぞ」
「………あぁ」
心ここにあらず、そんな返事に北斗は尋ねた。
「そんなに空が懐かしいか?」
漸く颯輝は空を見ることを止め、北斗と向き合った。
この空に似つかわしい、良く晴れた笑顔だった。
| 次へ