風唄 本編15 [2008年06月19日(木)]
颯輝は拳を握りしめた。妹の消息が分からなくなってから大星が突き止めるまで、自分は少しでも強くなれるよう努力したのだ。その時、自分が師と慕う人物に教えられた武器は、双剣。旅の早い段階で必要になると考えてはいたが、ジノはそれすら見抜いていたようだ。
「…おい、傷大丈夫か?」
女性達の姿が砂塵で見えなくなってから、北斗がその傷を確認するように跪いた。傷口に手を伸ばすが、指先が小刻みに震えている。初のバトルは、体よりも精神にダメージを残したようだ。
「平気平気。ってかあの人たち、何だったんだろうなぁ」
「さあ。あまり感じ良くは無かった。一応、出血が酷い所は縛っておくぞ」
そんなに激しく出血している訳ではないので大丈夫だろうと言いながら北斗は平静を装い、縛るものを探した。
「ぇえー、魔法かけてくれよ。一発で治るだろ」
「………それだけ元気なら大丈夫そうだ。マックス、首のそれ、貸してくれんか」
傍で自分の傷口を舐めていたマックスは自分が呼ばれたことに気付いて起き上がると、言葉の意味を理解しているのだろう、
ひょこひょこと近寄ってきた。少し辛そうではあるが、彼もまた重傷ではないようで胸を撫で下ろした。
北斗はマックスが首輪代わりにしていた帯状のものに手を伸ばす。応急処置には丁度良いだろう。しかし、間の抜けた場違いに大きな声が彼の手を止めた。
「あぁっと、それ!」
忘れてた、と慌てたように四つん這いでマックスに近づき、そしてその首の布をいじり始めた。そんなに元気なら傷を縛る必要もないみたいだな、と北斗は安堵すると同時に、行動が突拍子もない颯輝に小さくため息をついた。結び目を摘んだり引っ張ったりして、それを取ろうとしている。マックスは大人しくしたまま上を向いているが颯輝の手はもたついていて、何だか難儀しているようだ。
北斗は敢えて手助けをせず、黙ってそれを見守った。
…いつの間にか解くことをあきらめたらしい颯輝が無理矢理マックスの頭を通そうとしているまで。
マックスの顔が変形している。されたい放題のマックスは少しもがくだけで、それでも爪をひっこめたままというところが健気である。
「これぜってーおかしい!」
「馬鹿、マックスの首が締まるだろ。貸せ」
少し強引に小さな体躯を引き寄せる。颯輝があちらで悪態をついているが気にせずその毛並みを撫でる。可哀想に、苦しかったろう。
北斗はその首にかかる布を確認した。
「お前、よっぽど不器用なんじゃあるまいか」
「ちが…それマジ変なんだって!」
それは予想よりずっとゆるく結ばれてる上、結び方も大したものではない。
拍子抜けした気分だったが、颯輝の言ってる意味がわからない。変、とは?
しかしそれはすぐに理解できた。
北斗がその結び目に指を触れた途端……本当に触れただけで、それはいとも簡単にするりと解け、北斗の手のひらに落下した。
「…………」
何が起きたのか。取り敢えずそれを手に乗せたまま、颯輝を見遣る。彼も憮然としたままだ。
「…だから変だって言ったろー」
この場で晴れ晴れとした顔をしているのはマックスだけだった。
どうやらこれには魔術がかかっていたようだ。解けたきっかけ、一体何が鍵だったのかはわからないが一応颯輝に尋ねてみる。何となく、帰ってくる言葉は予想できるが。
「…これは?」
「大星の」
返答は至って簡潔だった。やはりなとも呆れともつかない何とも不思議な気分に陥る北斗である。どこまでも優秀であらせられたのだろうな、一代目よ。
「なーんとなくだけどさ、それ、北斗が持ってた方が良いような気がする」
何に使えるのかは颯輝にもわからないが、それは北斗が解いたのだ。結び目…封じられた何かを。大星が託したのだ。何か意味があるに違いない。
「な…んだ?」
戸惑うような北斗の声にふとその手元に注意を向けた。皺を伸ばすようになぞっていたはずのそれは。
「伸びてるね」
元はといえば、大星の私物。そう思うと、颯輝はもう何も驚かない。先程まではマックスの首に丁度良いサイズであったはずのそれは、ゆるりとその長さを変えた。
「しかし何故」
「さあ?」
やっぱり北斗に関係している。直感は確信に近づいた。しかし当の本人はまだ呆気にとられたように手にある物を見つめたままである。
「細かいことは気にしない。きっとなんか役に立つだろーし」
気楽な風体で颯輝が声を掛けると、北斗は僅かに顔の筋肉を緩め、小さく息を吐いた。そして少し考えてからその帯をピンと張ると、自らの頭に巻き始めた。
―――確か大星はそれを左腕に巻いていた。
その彼そっくりな末裔が、彼が愛用していた物を身につけている。擬視感ともつかない不思議な感覚は、不快ではない。
「似合う似合う」
茶化したように笑ってやると、憮然とした目で睨まれた。帯は幅も長さもあるようだ。何周か巻かれたその隙間から、北斗の短めの髪が飛び出ている。彼は苦虫を噛み潰したような顔で頭に触れた。
「身に付けたら何か起こるかと思ったんだが…」
「ふーん?」
実際、鳶色をしたそれは彼の金茶の瞳に良く似合っている。
「…行こう」
もうこの話題は十分だと言わんばかりに北斗は歩み始めた。続いてマックスが。その背中を見て、颯輝は負傷した体とは裏腹に、何故か心が浮き立つのを感じている。まだまだ分からない事ばかりなのは仕方がない。しかしなんて頼もしい友人達であろうか。
傷口はまだ痛む。荒野から巻き上げられる砂塵も鬱陶しい。今回のバトルだって危なかった。しかし、全て始まったばかりだという希望が颯輝の胸を満たしていた。照りつける太陽は段々と強さを増し、自分もろとも行くべき道を照らすだろう。夜で見えなくなった時には月と星の光を頼ろうか。寒ければ火を熾すのもいいだろう。自分では大変な作業も、北斗がいればなんとかなる気がする。
それでも寒さに凍えそうな時は、暖かな毛皮をもったマックスを抱いて眠ればいい。
それが、独りではないということ。
2人を追うべく、颯輝は駆け出した。
「…おい、傷大丈夫か?」
女性達の姿が砂塵で見えなくなってから、北斗がその傷を確認するように跪いた。傷口に手を伸ばすが、指先が小刻みに震えている。初のバトルは、体よりも精神にダメージを残したようだ。
「平気平気。ってかあの人たち、何だったんだろうなぁ」
「さあ。あまり感じ良くは無かった。一応、出血が酷い所は縛っておくぞ」
そんなに激しく出血している訳ではないので大丈夫だろうと言いながら北斗は平静を装い、縛るものを探した。
「ぇえー、魔法かけてくれよ。一発で治るだろ」
「………それだけ元気なら大丈夫そうだ。マックス、首のそれ、貸してくれんか」
傍で自分の傷口を舐めていたマックスは自分が呼ばれたことに気付いて起き上がると、言葉の意味を理解しているのだろう、
ひょこひょこと近寄ってきた。少し辛そうではあるが、彼もまた重傷ではないようで胸を撫で下ろした。
北斗はマックスが首輪代わりにしていた帯状のものに手を伸ばす。応急処置には丁度良いだろう。しかし、間の抜けた場違いに大きな声が彼の手を止めた。
「あぁっと、それ!」
忘れてた、と慌てたように四つん這いでマックスに近づき、そしてその首の布をいじり始めた。そんなに元気なら傷を縛る必要もないみたいだな、と北斗は安堵すると同時に、行動が突拍子もない颯輝に小さくため息をついた。結び目を摘んだり引っ張ったりして、それを取ろうとしている。マックスは大人しくしたまま上を向いているが颯輝の手はもたついていて、何だか難儀しているようだ。
北斗は敢えて手助けをせず、黙ってそれを見守った。
…いつの間にか解くことをあきらめたらしい颯輝が無理矢理マックスの頭を通そうとしているまで。
マックスの顔が変形している。されたい放題のマックスは少しもがくだけで、それでも爪をひっこめたままというところが健気である。
「これぜってーおかしい!」
「馬鹿、マックスの首が締まるだろ。貸せ」
少し強引に小さな体躯を引き寄せる。颯輝があちらで悪態をついているが気にせずその毛並みを撫でる。可哀想に、苦しかったろう。
北斗はその首にかかる布を確認した。
「お前、よっぽど不器用なんじゃあるまいか」
「ちが…それマジ変なんだって!」
それは予想よりずっとゆるく結ばれてる上、結び方も大したものではない。
拍子抜けした気分だったが、颯輝の言ってる意味がわからない。変、とは?
しかしそれはすぐに理解できた。
北斗がその結び目に指を触れた途端……本当に触れただけで、それはいとも簡単にするりと解け、北斗の手のひらに落下した。
「…………」
何が起きたのか。取り敢えずそれを手に乗せたまま、颯輝を見遣る。彼も憮然としたままだ。
「…だから変だって言ったろー」
この場で晴れ晴れとした顔をしているのはマックスだけだった。
どうやらこれには魔術がかかっていたようだ。解けたきっかけ、一体何が鍵だったのかはわからないが一応颯輝に尋ねてみる。何となく、帰ってくる言葉は予想できるが。
「…これは?」
「大星の」
返答は至って簡潔だった。やはりなとも呆れともつかない何とも不思議な気分に陥る北斗である。どこまでも優秀であらせられたのだろうな、一代目よ。
「なーんとなくだけどさ、それ、北斗が持ってた方が良いような気がする」
何に使えるのかは颯輝にもわからないが、それは北斗が解いたのだ。結び目…封じられた何かを。大星が託したのだ。何か意味があるに違いない。
「な…んだ?」
戸惑うような北斗の声にふとその手元に注意を向けた。皺を伸ばすようになぞっていたはずのそれは。
「伸びてるね」
元はといえば、大星の私物。そう思うと、颯輝はもう何も驚かない。先程まではマックスの首に丁度良いサイズであったはずのそれは、ゆるりとその長さを変えた。
「しかし何故」
「さあ?」
やっぱり北斗に関係している。直感は確信に近づいた。しかし当の本人はまだ呆気にとられたように手にある物を見つめたままである。
「細かいことは気にしない。きっとなんか役に立つだろーし」
気楽な風体で颯輝が声を掛けると、北斗は僅かに顔の筋肉を緩め、小さく息を吐いた。そして少し考えてからその帯をピンと張ると、自らの頭に巻き始めた。
―――確か大星はそれを左腕に巻いていた。
その彼そっくりな末裔が、彼が愛用していた物を身につけている。擬視感ともつかない不思議な感覚は、不快ではない。
「似合う似合う」
茶化したように笑ってやると、憮然とした目で睨まれた。帯は幅も長さもあるようだ。何周か巻かれたその隙間から、北斗の短めの髪が飛び出ている。彼は苦虫を噛み潰したような顔で頭に触れた。
「身に付けたら何か起こるかと思ったんだが…」
「ふーん?」
実際、鳶色をしたそれは彼の金茶の瞳に良く似合っている。
「…行こう」
もうこの話題は十分だと言わんばかりに北斗は歩み始めた。続いてマックスが。その背中を見て、颯輝は負傷した体とは裏腹に、何故か心が浮き立つのを感じている。まだまだ分からない事ばかりなのは仕方がない。しかしなんて頼もしい友人達であろうか。
傷口はまだ痛む。荒野から巻き上げられる砂塵も鬱陶しい。今回のバトルだって危なかった。しかし、全て始まったばかりだという希望が颯輝の胸を満たしていた。照りつける太陽は段々と強さを増し、自分もろとも行くべき道を照らすだろう。夜で見えなくなった時には月と星の光を頼ろうか。寒ければ火を熾すのもいいだろう。自分では大変な作業も、北斗がいればなんとかなる気がする。
それでも寒さに凍えそうな時は、暖かな毛皮をもったマックスを抱いて眠ればいい。
それが、独りではないということ。
2人を追うべく、颯輝は駆け出した。
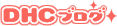


URL http://www.dhcblog.com/arianotonoburoguhoshi/tb_ping/879