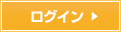サプリ研究の第一人者、蒲原先生の公式ブログです。 |
|
| 更年期の血管神経症状に対する第一選択:コンセンサス・ステートメント |
今月の産婦人科学の専門ジャーナルに、更年期の血管神経症状に対する第一選択としてイソフラボンを推奨したコンセンサス・ステートメントが、欧州(ドイツ・スイス・イタリア・オーストリア・スロベニア)のグループから報告されていました。 (Gynecol Endocrinol. 2016 Mar 4:1-4.) イソフラボン類の摂取と、更年期のほてり(ホットフラッシュ)減少との相関は、1990年代初めに、大豆の摂取との関連による研究にて指摘されました。 それ以降、 大豆やレッドクローバーなどさまざまなイソフラボン源を用いて、多くの臨床研究が実施されされており、 適切なプロトコールにより行われた研究では、すべて、イソフラボンサプリメントの好影響を支持しています。 また、 リスク評価(EFSA 2015)では、いずれのヒト臨床研究でも、 乳腺や子宮、甲状腺において、イソフラボンとホルモン感受性細胞との潜在的な相互作用からの有害事象は見出されていません。 安全性に関しては、 1日あたり150mgまでの3年間の長期間投与により確認が行われました。 さらに、 高用量のイソフラボン摂取により、乳がんリスク低減作用も見出されました。 その他、 臨床での知見から、乳がんに対してタモキシフェンあるいはanastrozoleによる治療中でも、イソフラボン摂取による潜在的な好影響が示唆されています。 大豆やレッドクローバー、プエラリア・ミリフィカには、女性ホルモン様作用を有するファイトケミカル(植物エストロゲン)の1種、イソフラボン類が豊富に含まれており、女性特有の病気に対する予防や改善作用などの機能性が知られています。 また、抗酸化作用や抗炎症作用を介した機能性から、生活習慣病のリスク低下作用や抗がん作用も注目されています。 最近の研究では、次の報告があります。 大豆イソフラボンによる胃がんリスク低下:高山スタディ 植物エストロゲンによる更年期症状改善作用:メタ解析 植物エストロゲンの摂取による卵巣がんリスク低下:メタ解析 DHCでは、大豆イソフラボン、プエラリアミリフィカといったサプリメント、レッドクローバーを含む女性向けの複合サプリメントなどを製品化しています。 ------------------------------------------------------------------ サプリメントと医薬品の相互作用ハンドブック―機能性食品の適正使用情報 DHCが日本のサプリを健康にします。 医療関係者のための健康食品情報サイト【DHCサプリメント研究所】 【健康食品FAQ】 DHCが第1位@利用している(利用したい)メーカー(経産省の調査) ------------------------------------------------------------------ |
| posted at 23:51 | この記事のURL |
| この記事のURL |
| http://www.dhcblog.com/kamohara/archive/3585 |
|