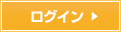サプリ研究の第一人者、蒲原先生の公式ブログです。 |
|
| 乳酸菌の投与が関節リウマチでの炎症を軽減する |
関節リウマチ研究の専門ジャーナルに、乳酸菌の投与による関節リウマチ患者の症状軽減と炎症状態の改善を示した臨床研究が報告されていました。 (Int J Rheum Dis. 2014 Jun;17(5):519-27) 先行研究では、 関節リウマチ患者と健常者では、腸内細菌叢(腸内フローラ)の構成菌種に有意な相違があることが示されています。 ただし、関節リウマチでは、特定の菌種の存在が、病気の原因となるのか、あるいは、関節リウマチに伴う慢性炎症の結果として、特定の菌種の増加や減少といったディスバイオーシスが生じるのかはまだ明確ではありません。 (なお、肥満では、特定の菌種による肥満との因果関係が示唆されています。) さて、今回の研究では、 関節リウマチ患者において、 乳酸菌サプリメントの投与による炎症マーカーおよび症状への影響が検証されました。 具体的には、 ランダム化二重盲検臨床試験として、 20-80歳の関節リウマチ患者の女性を対象に、 (BMIは40未満、試験開始前の3ヶ月間は医薬品の投与が一定で状態が安定している患者) サプリメント投与群(30名) あるいは 偽薬投与群(30名)の2群について、8週間の乳酸菌投与が行われています。 用いられた乳酸菌は、 ラクトバチルス・カゼイLactobacillus caseiの1種です。 (投与量は、Lactobacillus casei 01を10(8) CFU) 病気の症状は、 疾患活動性スコア28(DAS28 EULARレスポンス、 で評価され、 炎症マーカーとして血中のサイトカイン類が測定されています。 (IL-1β, IL-6, IL-10, IL-12, TNF-α) 乳酸菌投与群22名、偽薬投与群24名のデータが解析された結果、 乳酸菌(L. casei 01)投与群では、 炎症マーカーであるhs-CRPの有意な減少、 圧痛や腫脹関節の数の減少(改善)、 グローバルヘルススコアやDAS28の有意な改善が認められたということです。 (P < 0.05) 試験終了時に、 乳酸菌投与群では、より多くの患者が、治療への中等度の反応性が認められました。 (EULARクライテリアによる。P < 0.01) また、 試験終了時に、 IL-10, IL-12, TNF-αの値に関して、両群間に有意差が認められ、 (P < 0.05) 乳酸菌投与群での好影響が示されています。 以上のデータから、 関節リウマチ患者において、 乳酸菌投与による炎症マーカー改善および症状軽減作用が示唆されます。 今後、補完療法としての臨床的意義の検証が期待されます。 腸内細菌叢(腸内フローラ)を健康に保つ(善玉菌を増やし維持する)には、 ・プロバイオティクスの摂取、 ・プレバイオティクスの摂取 が重要です。 腸内細菌叢の改善では、食物繊維の有用性はよく知られています。 また、オリゴ糖は、善玉菌を増やす効果がありますので、 乳酸菌と一緒にオリゴ糖もとることが大切です。 乳酸菌は、ベーシックなサプリメントとして利用が推奨されます。 様々な乳酸菌が製品化されていますので、自分にあった菌種を選ぶことが大切です。 具体的には、1ヶ月ほど試してみて、整腸作用も含めて体調をみるようにします。 (整腸作用は、乳酸菌の摂取後数日間の間に変化を感じると思います。もし、軟便あるいは下痢傾向になってしまうのであれば、他の菌種に変更します。 また、1-3ヶ月から数ヶ月間のサイクルで菌種をローテーションしてもいいでしょうし、複数の種類を同時にとることも大丈夫です。 ヨーグルトなどの発酵食品でもいいのですが、数百グラムを毎日食べるのは大変ですし、 確実に乳酸菌を摂るには、サプリメントの利用が手軽で続けやすいと思います。 プロバイオティクスは、様々な有用性が示されています。 最近の研究では、次の報告があります。 プロバイオティクスによる脂質異常症改善効果:メタ解析 プロバイオティクスによるアトピー性皮膚炎の予防効果:メタ解析 プロバイオティクス摂取による脂質代謝改善作用:メタ解析 DHCでは、プロバイオティクスとして、 ビフィズス菌+オリゴ糖 生菌ケフィア DHC自分でつくるケフィアヨーグルト 複合サプリメント(グッドスルー) などを製品化しています。 また、プレバイオティクスとしては、 食物繊維 があります。 ------------------------------------------------------------------ サプリメントと医薬品の相互作用ハンドブック―機能性食品の適正使用情報 DHCが日本のサプリを健康にします。 医療関係者のための健康食品情報サイト【DHCサプリメント研究所】 【健康食品FAQ】 DHCが第1位@利用している(利用したい)メーカー(経産省の調査) ------------------------------------------------------------------ |
| posted at 23:56 | この記事のURL |
| 抗生物質の利用でうつ病リスクが上昇 |
抗生物質の利用とうつ病との関連を調べた研究が、イスラエルのグループから報告されていました。 (J Clin Psychiatry. 2015 Nov;76(11):1522-8.) 腸内細菌叢(腸内フローラ)は、整腸作用だけではなく、免疫機能の維持や抗炎症作用など健康維持に重要な役割を果たしていることが明らかになっています。 食生活などの環境要因によって、腸内細菌叢に乱れが生じると、脂肪酸などの代謝の変化や慢性炎症の惹起により、 肥満、脂質異常症、アレルギー疾患、炎症性疾患、神経疾患(アルツハイマー病、パーキンソン病)、精神疾患(うつ病や自閉症ADHD)のリスクが高まることが示唆されています。 腸内細菌叢のバランスの異常(構成する菌種の異常)は、ディスバイオーシス(dysbiosis)と呼ばれます。 最近では、ディスバイオーシスを原因とする各種疾患に対する治療として便移植も行われるようになりました。 腸内細菌叢の乱れ・ディスバイオーシスを生じる状態に、抗生物質の服用があげられます。 先行研究では、 抗生物質の服用が多いほど乳がんリスクが上昇 というデータが示されています。 今回の研究では、 抗生物質の服用と、うつ病、不安症、精神病(psychosis)との関連が検証されました。 具体的には、 3個の症例対照研究として、 1995年から2013年までの英国の医学記録から、 うつ病患者202,974名、 不安症患者14,570名、 精神病患者2,690名と、 対照群(それぞれ803,961名、57,862名、10,644名) が対象となり、 (被験者は15歳から65歳) 各クラスの抗生剤の服用状況が調べられました。 診断前の肥満や喫煙、飲酒、感染症の既往などが交絡因子として調整されています。 解析の結果、 まず、 全てのクラスの抗生剤に関して、単回の治療コースの服用と、 うつ病リスク上昇との間に有意な相関が認められました。 例えば、 ペニシリン類では23%上昇、 (1.23, 95% CI, 1.18-1.29) キノロン類では25%上昇 (1.25, 95% CI, 1.15-1.35) でした。 次に、 複数の回数(治療コース)の抗生剤の投与は、 ペニシリン類の場合、 2-5回では40%のリスク上昇 6回以上では56%のリスク上昇が認められたということです。 同様の相関が、 不安症のリスクと、ペニシリン類およびスルホンアミド類の服用との間にも見出されています。 ペニシリン類の単回の治療コースでは17%のリスク上昇、 6回以上では44%のリスク上昇でした。 一方、精神病のリスクと、抗生剤の服用との間に有意な関連は認められませんでした。 その他、 抗真菌薬の服用は、 単回の治療コースでは、うつ病と不安症のリスクの軽度上昇が認められましたが、 複数回の治療コースでは相関は見出されませんでした。 以上のデータから、 抗生剤の服用と、うつ病リスク上昇および不安症リスク上昇との関連が示唆されます。 腸内細菌叢(腸内フローラ)を健康に保つ(善玉菌を増やし維持する)には、 ・プロバイオティクスの摂取、 ・プレバイオティクスの摂取 が重要です。 腸内細菌叢の改善では、食物繊維の有用性はよく知られています。 また、オリゴ糖は、善玉菌を増やす効果がありますので、 乳酸菌と一緒にオリゴ糖もとることが大切です。 乳酸菌は、ベーシックなサプリメントとして利用が推奨されます。 様々な乳酸菌が製品化されていますので、自分にあった菌種を選ぶことが大切です。 具体的には、1ヶ月ほど試してみて、整腸作用も含めて体調をみるようにします。 (整腸作用は、乳酸菌の摂取後数日間の間に変化を感じると思います。もし、軟便あるいは下痢傾向になってしまうのであれば、他の菌種に変更します。 また、1-3ヶ月から数ヶ月間のサイクルで菌種をローテーションしてもいいでしょうし、複数の種類を同時にとることも大丈夫です。 ヨーグルトなどの発酵食品でもいいのですが、数百グラムを毎日食べるのは大変ですし、 確実に乳酸菌を摂るには、サプリメントの利用が手軽で続けやすいと思います。 プロバイオティクスは、様々な有用性が示されています。 最近の研究では、次の報告があります。 プロバイオティクスによる脂質異常症改善効果:メタ解析 プロバイオティクスによるアトピー性皮膚炎の予防効果:メタ解析 プロバイオティクス摂取による脂質代謝改善作用:メタ解析 DHCでは、プロバイオティクスとして、 ビフィズス菌+オリゴ糖 生菌ケフィア DHC自分でつくるケフィアヨーグルト 複合サプリメント(グッドスルー) などを製品化しています。 また、プレバイオティクスとしては、 食物繊維 があります。 ------------------------------------------------------------------ サプリメントと医薬品の相互作用ハンドブック―機能性食品の適正使用情報 DHCが日本のサプリを健康にします。 医療関係者のための健康食品情報サイト【DHCサプリメント研究所】 【健康食品FAQ】 DHCが第1位@利用している(利用したい)メーカー(経産省の調査) ------------------------------------------------------------------ |
| posted at 23:51 | この記事のURL |
| 抗生物質の服用が多いほど乳がんリスクが上昇 |
腸内細菌叢(腸内フローラ)は、整腸作用だけではなく、免疫機能の維持や抗炎症作用など健康維持に重要な役割を果たしていることが明らかになっています。 食生活などの環境要因によって、腸内細菌叢に乱れが生じると、代謝の変化や慢性炎症の惹起により、 肥満、神経疾患(アルツハイマー病、パーキンソン病)、精神疾患(うつ病や自閉症ADHD)のリスクが高まることが示唆されています。 また、アレルギー疾患のリスクも高くなることから、ヨーグルトによる花粉症の症状軽減といった働きも知られています。 腸内細菌叢の乱れを生じる状態に、抗生物質の摂取があげられます。 今日では、腸内細菌叢の重要性が認識されていますが、 特にこの数年、腸内フローラの研究が臨床実践にも応用されるようになりました。 腸内細菌叢の重要性を示唆する研究データとして、 10年以上も前に、抗生物質の利用と乳がんリスクとの関連を示した研究が報告されていました。 (JAMA. 2004 Feb 18;291(7):827-35.) 具体的には、オランダでの症例対照研究として、 19歳以上の侵襲性乳がん患者2,266名と、 対照群7953名を対象に、 薬局の電子記録に基づく抗生物質の利用と、乳がんリスクとの関連が調べられています。 解析の結果、 抗生物質の服用日数の累積(合計)が増えるにしたがって、乳がん発症が有意に増加していたということです。 利用日数ゼロを対照群の1としたときに、それぞれの服用日数の累積と、乳がんリスクとの関係は、 1-50日:45%リスク増加 51-100日:53%リスク増加 101-500日:68%リスク増加 501-1000日:114%リスク増加 1001日以上:107%リスク増加 でした。 (P<.001 for trend). 抗生物質の利用と乳がんリスク増大の相関は、 あらゆるクラスの抗生物質において有意に認められたということです。 抗生物質は、細菌感染症には特効薬となりえますが、(腸内細菌も腸内細菌叢の乱れを生じます。 抗生物質の過剰な投与が長期的な健康リスクとなることを明確に示した研究です。 12年前のこの論文では、著者らは、 相関関係は明確であるが、因果関係については検証が必要、と考察しています。 しかし、その後の腸内細菌叢に関する研究を考えると、 抗生物質の累積利用が、免疫調節や抗炎症といった腸内細菌叢のバランスを乱すことで、 乳がんの発症に関与すると考えられます。 腸内細菌叢(腸内フローラ)を健康に保つ(善玉菌を増やし維持する)には、 ・プロバイオティクスの摂取、 ・プレバイオティクスの摂取 が重要です。 腸内細菌叢の改善では、食物繊維の有用性はよく知られています。 また、オリゴ糖は、善玉菌を増やす効果がありますので、 乳酸菌と一緒にオリゴ糖もとることが大切です。 プロバイオティクスは、様々な有用性が示されています。 最近の研究では、次の報告があります。 プロバイオティクスによる脂質異常症改善効果:メタ解析 プロバイオティクスによるアトピー性皮膚炎の予防効果:メタ解析 プロバイオティクス摂取による脂質代謝改善作用:メタ解析 DHCでは、プロバイオティクスとして、 ビフィズス菌+オリゴ糖 生菌ケフィア DHC自分でつくるケフィアヨーグルト 複合サプリメント(グッドスルー) などを製品化しています。 また、プレバイオティクスとしては、 食物繊維 があります。 ------------------------------------------------------------------ サプリメントと医薬品の相互作用ハンドブック―機能性食品の適正使用情報 DHCが日本のサプリを健康にします。 医療関係者のための健康食品情報サイト【DHCサプリメント研究所】 【健康食品FAQ】 DHCが第1位@利用している(利用したい)メーカー(経産省の調査) ------------------------------------------------------------------ |
| posted at 23:56 | この記事のURL |
| 血中オメガ3系脂肪酸(EPA+DHA)が高いと認知機能が維持されている |
今月のアルツハイマー病研究の専門ジャーナル(電子版)に、沖縄において、血中オメガ3系必須脂肪酸の濃度と認知機能との関連を調べた研究が、琉球大学と米国の大学から報告されていました。 (J Alzheimers Dis. 2016 Feb 16.) EPAやDHAなどのオメガ3系必須脂肪酸は、抗炎症作用・動脈硬化予防作用、認知機能改善作用、抗うつ作用など多彩な働きが示されています。 先行研究(疫学研究)では、 オメガ3系必須脂肪酸(EPAとDHA)の豊富な魚の摂取による認知機能の維持(認知機能低下の抑制)作用が示唆されています。 しかし、高齢者において、血中のオメガ3系必須脂肪酸の濃度と、認知機能との関係は明確ではありません。 そこで、今回の研究では、 地域に居住する高齢者(認知症ではない高齢者)において、 血中オメガ3系脂肪酸の濃度と、認知機能との関連が検証されました。 具体的には、 2011年に、横断研究として、 沖縄在住の基本的には健康な80歳以上の高齢者185名(平均年齢84.1±3.4歳)を対象に、 血中のDHA、EPA、アラキドン酸(AA)、EPA/AA比, DHA/AA比, DHA+EPAが測定され、 年齢や認知機能(MMSE)などとの関連が調べられています。 (Keys to Optimal Cognitive Aging (KOCOA)研究の一環です。) 年齢、性別、教育、肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった交絡因子で補正が行われ、多変量解析の結果、 まず、 血中DHA値は、加齢とともに低下していました。 (p = 0.04) 次に、 交絡因子で補正後、 認知機能が高い(維持されている)ほど、 血中EPA値が高値、 (p = 0.03) 血中DHA+EPAが高値 (p = 0.03) という有意な相関が見出されました。 以上のデータから、 沖縄に居住する認知症ではない80歳以上の高齢者では、 血中EPAおよびDHA+EPAが高いほど、認知機能が保たれており、認知症リスクが低いという関連が示唆されます。 機能性食品・サプリメントの中で、ヒト臨床研究によって、認知症改善作用が示されているのは、次の成分です。 イチョウ葉エキスによる認知症への効果:メタ解析 イチョウ葉エキス イチョウ葉エキス製剤による認知症の症状改善作用 イチョウ葉エキスによる認知症改善効果@ドイツ イチョウ葉エキスの有効性と安全性 イチョウ葉エキス20年間摂取による認知機能低下抑制作用 イチョウ葉エキスと認知症治療薬のシナジー PS(ホスファチジルセリン)サプリメント PS(ホスファチジルセリン)による認知機能改善作用 エクストラヴァージン(バージン)オリーブオイル エクストラバージンオリーブオイルによる認知症予防効果 大豆イソフラボンによる認知機能改善効果@メタ解析 ・ビタミンB群 ビタミンB群投与による脳萎縮(灰白質萎縮)抑制効果と認知機能低下抑制効果 脳萎縮進行抑制効果を示した臨床研究 オメガ3系必須脂肪酸とαリポ酸によるアルツハイマー病の進行抑制効果 一般に、認知機能への効果を期待する場合には、ビタミンB群、オメガ3系脂肪酸(EPAやDHA)、イチョウ葉エキスといったサプリメントを比較的長期間(数ヵ月以上)に利用することが必要と考えられます。 また、ウコン・クルクミンによる認知症改善作用も報告されています。 DHCでは、複合サプリメントも製品化しています。 ------------------------------------------------------------------ サプリメントと医薬品の相互作用ハンドブック―機能性食品の適正使用情報 DHCが日本のサプリを健康にします。 医療関係者のための健康食品情報サイト【DHCサプリメント研究所】 【健康食品FAQ】 DHCが第1位@利用している(利用したい)メーカー(経産省の調査) ------------------------------------------------------------------ |
| posted at 23:53 | この記事のURL |
| αリポ酸による糖尿病性神経障害の症状改善:レビュー |
糖尿病研究の専門ジャーナル(電子版)に、αリポ酸サプリメントによる糖尿病神経障害の有効性を示した系統的レビューが、オランダのグループ(Erasmus Medical Centre University)から報告されていました。 (Diabet Med. 2016 Jan 29.) 今回のレビューでは、 糖尿病合併症として生じる下肢の末梢神経障害に伴う疼痛や感覚障害に対する機能性食品成分の有用性が検証されました。 具体的には、 主要医学データベースを用いて、2015年7月までの研究が対象となり、 (PubMed, Embase, Web-of-Science) 下肢の糖尿病性末梢神経障害に対するランダム化比較試験が検索されています。 薬理学的、非薬理学的介入、および補完療法を用いた27報が解析の対象となりました。 まず、 αリポ酸と偽薬のメタ解析の結果、 αリポ酸(iv、600mgの3報)では、総症状スコアの有意な軽減(改善)、 -2.45 (95% CI -4.52; -0.39) αリポ酸(600mgの経口投与:2報)でも、同様に総症状スコアの有意な軽減(改善) -1.95 (95% CI -2.89; -1.01) が見出されました。 αリポ酸以外では、opioids, botulinum toxin A, mexidolの投与、 あるいは、タイフットマッサージやリフレクソロジーによる症状軽減も示唆されています。 今回のレビューから、 糖尿病性神経障害による下肢の末梢神経障害に対するαリポ酸(600mgの経口投与)の有用性が示唆されます。 αリポ酸は、抗酸化作用を有する機能性成分の一つで、体内ではミトコンドリアで産生されます。 サプリメントとしてのαリポ酸は、抗酸化作用を介した機能性が示されており、 ダイエット目的からアンチエイジングまで、広く利用されています。 特に、欧米の臨床試験では、糖尿病性神経障害に対する症状改善作用が報告されています。 DHCでは、下記のサプリメントを製品化しています。 αリポ酸、 ------------------------------------------------------------------ サプリメントと医薬品の相互作用ハンドブック―機能性食品の適正使用情報 DHCが日本のサプリを健康にします。 医療関係者のための健康食品情報サイト【DHCサプリメント研究所】 【健康食品FAQ】 DHCが第1位@利用している(利用したい)メーカー(経産省の調査) ------------------------------------------------------------------ |
| posted at 23:53 | この記事のURL |
| コーヒーの摂取が肝移植後の生存期間を延長する |
今月の消化器病学の専門ジャーナル(電子版)に、コーヒーの摂取と、肝硬変の進行および肝臓移植後の長期生存との関係を調べた疫学研究が、ドイツのグループ(University Hospital of Heidelberg)から報告されていました。 (J Gastroenterol Hepatol. 2016 Feb 15.) 肝臓疾患末期に対する治療や、肝臓移植後の長期生存の改善に寄与する治療は、限られています。 これまでの疫学研究によって、コーヒーの摂取による生活習慣病リスクの低下が知られています。 例えば、コーヒーの摂取による2型糖尿病リスク低下、脳卒中リスク低下、うつ病リスク低下、肝がんリスク低下、認知機能の低下抑制などがあります。 今回の研究では、コーヒーの摂取と、肝硬変および肝臓移植後の長期生存との関連が検証されました。 具体的には、 肝臓移植待機中の末期肝臓疾患患者379名および肝臓移植後の患者260名を対象に、 コーヒーの摂取と、生存率との関係が調べられています。 解析の結果、 まず、 末期肝臓疾患患者のうち、195名がコーヒーを毎日習慣的に摂取しており、 184名は摂取していませんでした。 生存期間は、コーヒー非摂取群では、摂取群に比べて、有意に短かったということです(p = 0.041)。 各生存期間は: コーヒー非摂取群:40.4 ± 4.3 ヶ月, 95% CI: 32.0-48.9 コーヒー摂取群: 54.9 ± 5.5 ヶ月, 95% CI: 44.0-65.7 でした。 また、 サブ解析では、 アルコール性肝障害患者の生存率(p = 0.020)や原発性肝硬変の生存率 (p = 0.017)でも、コーヒー摂取群による有意な延長(改善)が認められました。 一方、 慢性ウイルス性肝炎(p = 0.517)や、その他の疾患(p = 0.652)ではコーヒーの摂取と非摂取による有意差は認められませんでした。 多変量解析の結果、 原発性肝硬変とアルコール性肝障害では、 コーヒーの摂取が独立したリスク因子であることが示されています。 (OR: 1.94; 95% CI: 1.15-3.28; p = 0.013) その他、MELD-スコアも有意な危険因子です。(OR: 1.13; 95% CI: 1.09-1.17; p = 0.000). 肝移植後の長期生存に関しても、 コーヒーの非摂取群に比べて、 (52.3 ± 3.5 ヶ月, 95% CI: 45.4-59.3; p = 0.001) コーヒー摂取群での有意な延長が認められました。 (61.8 ± 2.0 ヶ月, 95% CI: 57.9-65.8) 以上のデータから、 コーヒーの習慣的な摂取によるアルコール性肝障害、原発性肝硬変といった末期肝臓疾患の進行抑制作用、肝臓移植後の長期生存の改善が示唆されます。 論文著者らは、 習慣的なコーヒーの摂取が、これらの患者に対して推奨されうる、と考察しています。 これまでの疫学研究によって、コーヒーの摂取による生活習慣病リスクの低下が知られています。 例えば、コーヒーの摂取による2型糖尿病リスク低下、脳卒中リスク低下、うつ病リスク低下、肝がんリスク低下、認知機能の低下抑制などがあります。 コーヒーにはファイトケミカルの1種であるクロロゲン酸が含まれており、抗酸化作用を介した生活習慣病予防効果が示唆されています。 (カフェイン以外のコーヒーの主要な成分として、フェルラ酸(ferulic acid)、カフェ酸(caffeic acid,)、クロロゲン酸(chlorogenic acid)が知られており、いずれも抗酸化作用を示します。これらの中ではクロロゲン酸が比較的多く存在します。) これまでの疫学研究や臨床試験では、高血圧症の改善、心血管疾患(動脈硬化性疾患)リスクの低減、抗がん作用などが報告されています。 例えば、次のような研究が知られています。 コーヒー摂取による全死亡率と心血管疾患リスク低下効果:メタ解析 コーヒーの摂取と泌尿器のがんの関係@メタ解析 コーヒーの摂取による前立腺がんリスク低下作用@メタ解析 コーヒーによる肝臓がんリスク低下作用 コーヒーの摂取と前立腺がんリスクとの関連 コーヒーの摂取による口腔咽頭がんリスク低下作用 チョコレートとコーヒーの摂取と肝機能の関係@HIV-HCV重複感染者 コーヒーの摂取が女性のうつ病リスクを抑制 ------------------------------------------------------------------ サプリメントと医薬品の相互作用ハンドブック―機能性食品の適正使用情報 DHCが日本のサプリを健康にします。 医療関係者のための健康食品情報サイト【DHCサプリメント研究所】 【健康食品FAQ】 DHCが第1位@利用している(利用したい)メーカー(経産省の調査) ------------------------------------------------------------------ |
| posted at 23:56 | この記事のURL |
| エクストラバージンオリーブオイルによる食後血糖上昇抑制作用@1型糖尿病 |
今月の糖尿病ケアの専門ジャーナル(電子版)に、1型糖尿病患者において、エクストラバージンオリーブオイルによる食後血糖上昇抑制作用を示した臨床研究が、イタリアのグループ(Federico II University)から報告されていました。 (Diabetes Care. 2016 Feb 9.) 今回の研究では、 1型糖尿病患者において、 高グリセミック指数(HGI)あるいは低グリセミック指数(LGI)の食事摂取時に、 脂質の質による食後血糖値への影響が検証されました。 具体的には、 ランダム化クロスオーバー法にて、 インスリンポンプによる治療中の1型糖尿病患者13名を対象に、 同じ炭水化物量の高GI(HGI)食あるいは低GI(LGI)食の摂取時に、 1)低脂肪食 2)高飽和脂肪酸食(バター) 3)高単価不飽和脂肪酸(エクストラバージンオリーブオイル) の3種類の脂質が併用投与されました。 食前のインスリン投与量は、インスリン・グリセミック負荷比に基づいています。 血糖値の持続モニタリングおよび6時間食後血糖値が測定されました。 解析の結果、 まず、 食後血糖値は、 高GI食の摂取後3時間の間、有意に高く、その後は逆パターンとなり、 高GIと低GIの間に有意差が認められました。 (P = 0.005 for time × glycemic index interaction by repeated-measures analysis [RMA]) 次に、 高GI食摂取時の食後血糖値は、 低脂肪食あるいはバターの摂取後よりも、 エクストラバージンオリーブオイル摂取後のほうが、有意に低値でした。 0から3時間の間の血糖上昇のAUCの平均値は、 エクストラバージンオリーブオイル:198 ± 273 mmol/L × 180 min、 低脂肪食: 416 ± 329 mmol/L × 180 min、 バター: 398 ± 355 mmol/L × 180 min でした。 (P < 0.05). なお、低GI摂取時には、食後血糖値に関して、脂質の3種類での間に有意差は認められませんでした。 以上のデータから、 炭水化物の質の相違(高GI, 低GI)は食後血糖値に有意な影響を与えること、 高GI食の摂取時には、 低脂肪やバターよりも、エクストラバージンオリーブオイルとの併用が、食後血糖値の上昇を有意に抑制すること が示唆されます。 したがって、 1型糖尿病患者におけるインスリン投与では、 炭水化物の量に加えて、 炭水化物の種類(質)および脂質の種類の組み合わせを考慮する必要があります。 DHCでは、 肥満・糖尿病・アンチエイジング・ヘルシーエイジング(健康長寿)のための食事として、 「‘ゆるやか’糖質制限」(緩やかな糖質制限食・低炭水化物食)を推奨しています。 最新の科学的根拠を俯瞰すると、 「緩やかな糖質制限食・低炭水化物食」を基本とした食生活が、 「ヘルシーエイジング(健康長寿)」 「ダイエット(適正体重の維持)」 「アンチエイジング(抗加齢)」 に有用であると考えられます。 近年の研究では、 単なるオリーブオイルではなく、 オリーブ由来のポリフェノールが豊富なエクストラバージンオリーブオイルのほうが、優れた機能性を有することが分かってきました。 ただし、日本では、JAS基準のオリーブオイルが出回っており、エクストラバージンオリーブオイルの品質が国際基準と比べて、高くありません。 エクストラバージンオリーブオイルの基準は、 IOC(国際オリーブ協会)では酸度0.8%以下、 JASの基準では酸度が2%未満です。 DHCのエクストラバージンオリーブオイルは、 酸度はわずか0.2%以下となっています。 地中海食は、スペインやギリシャ、南フランスなど地中海地方の伝統食です。 野菜や果物、全粒の穀類、種実類、オリーブオイルの利用が多いという特徴があります。 地中海食は、健康増進や疾病予防に有用であることが知られており、多くの研究によってエビデンスが示されています。 地中海食やオリーブオイルの効能については、多くのエビデンスが報告されています。 地中海食で死亡率が半減する 低炭水化物(糖質制限)食と地中海食は低脂肪食よりも有効 オリーブオイルの摂取10gで全死亡率が7%低下 地中海食がメタボを抑制 バージンオリーブオイルとナッツ類を含む地中海食の抗炎症作用 バージンオリーブオイルの心臓病予防作用 オリーブオイルによる皮膚の老化抑制作用 地中海食による認知症予防効果 地中海食+CoQ10サプリによる抗酸化作用 超低炭水化物・地中海食による減量効果 地中海食による高尿酸血症リスクの低下 オリーブオイルによる動脈硬化抑制作用 バージンオリーブオイルによる骨代謝改善作用 オリーブオイルとナッツによる心血管リスク低下作用 伝統的地中海食による脂質代謝改善作用 オリーブオイルによる膀胱がんリスク低下 ------------------------------------------------------------------ サプリメントと医薬品の相互作用ハンドブック―機能性食品の適正使用情報 DHCが日本のサプリを健康にします。 医療関係者のための健康食品情報サイト【DHCサプリメント研究所】 【健康食品FAQ】 DHCが第1位@利用している(利用したい)メーカー(経産省の調査) ------------------------------------------------------------------ |
| posted at 23:54 | この記事のURL |
| レスベラトロールの体内動態と安全性 |
本日、私が査読委員をしている欧州の専門ジャーナルから査読論文の依頼がありました。 論文の査読では、あらかじめ登録されている(私の)専門分野の情報から、適宜、関連する論文が回ってくるのですが、今回の原著論文(投稿論文)は、ジンバブエの伝統医療/補完代替医療に関する調査研究でした。 専門とはいいがたいので、他の査読委員に担当してもらうように依頼するつもりです。 さて、本日の私的なお勉強日記です。 実験治療医学の専門ジャーナルに、レスベラトロールのバイオアベイラビリティと安全性を検証した臨床研究が、欧州(キプロス・ルーマニア・ドイツ)のグループから報告されていました。 (Exp Ther Med. 2016 Jan;11(1):164-170.) レスベラトロールは、ポリフェノールの1種で、赤ワインやブドウ、ピーナッツなどに見出される色素成分です。 サプリメントで用いられる機能性成分のトランス・レスベラトロールは、 抗酸化作用、抗炎症作用、抗腫瘍作用、抗糖尿病作用、心保護作用、神経保護作用などが示されています。 今回の研究では、 トランス・レスベラトロールのバイオアベイラビリティと安全性が検証されました。 具体的には、 オープンラベル試験として、 健康な被験者15名を対象に、 空腹時に、トランス・レスベラトロールを500mg、単回投与し、 24時間後までの定期的な検体採取により、 レスベラトロールの代謝物の測定が行われ、体内動態(Cmax, AUC0-t, AUC0-inf, Tmax, T1/2 and MRT,)が調べられています。 解析の結果、 まず、 Cmax と AUC0-inf は、 レスベラトロールでは、 代謝物(グルクロン酸抱合や硫酸抱合)よりも低値でした。 Cmaxは、 レスベラトロール、グルクロン酸抱合レスベラトロール、硫酸抱合レスベラトロールでそれぞれ71.2±42.4 ng/ml, 4,083.9±1,704.4 ng/ml,1,516.0±639.0 ng/mlでした。 また、AUC0-inf は、ぞれぞれ、 179.1±79.1 ng/ml, 39,732.4±16,145.6 ng/ml, 14,441.7±7,593.2 ng/mlでした。 レスベラトロール摂取による有害事象は認められませんでした。 血中レスベラトロール濃度(フリー体および抱合体)は、先行研究と同程度であることも確認されています。 以上のデータから、 トランス・レスベラトロール(500mg含有タブレット)の単回投与による一定のバイオアベイラビリティと許容性が示唆されます。 レスベラトロールは、ポリフェノールの1種で、赤ワインやブドウ、ピーナッツなどに見出される色素成分です。 レスベラトロールは、長寿関連遺伝子の1つであるサーチュイン遺伝子の活性化を介して、アンチエイジング効果があるのでは、と期待されています。 長寿になるかどうかを確認するためのヒト臨床試験は容易ではありませんが、 最近の臨床研究では、内分泌代謝疾患や生活習慣病の改善効果が示唆されています。 現在、レスベラトロールは、抗酸化作用や抗炎症作用を有し、代謝に好影響を及ぼすことから、健康維持や生活習慣病予防からアンチエイジングの分野で注目されています。 例えば、基礎研究では、 レスベラトロールによるインスリン抵抗性改善作用 レスベラトロールによる糖尿病予防 レスベラトロールによる糖代謝改善作用 レスベラトロールの心不全リスク低減作用 レスベラトロールによる肥満予防のメカニズム レスベラトロールによる抗がん作用 レスベラトロールによる大腸がん抑制作用 レスベラトロールの抗炎症作用 動脈硬化抑制作用 という報告があり、 ヒト臨床研究では、 レスベラトロールによる肥満者での代謝改善 レスベラトロールによる糖尿病改善作用 レスベラトロールによる脳循環改善 子宮内膜症関連痛に対するレスベラトロールの効果 レスベラトロールによる運動効果@2型糖尿病患者 レスベラトロールによる非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)改善作用 という報告が知られています。 ------------------------------------------------------------------ サプリメントと医薬品の相互作用ハンドブック―機能性食品の適正使用情報 DHCが日本のサプリを健康にします。 医療関係者のための健康食品情報サイト【DHCサプリメント研究所】 【健康食品FAQ】 DHCが第1位@利用している(利用したい)メーカー(経産省の調査) ------------------------------------------------------------------ |
| posted at 23:55 | この記事のURL |
| オメガ3系必須脂肪酸による高齢者の認知機能改善作用@ドイツ |
医療情報誌をめくっていたら、医療時事に関するクイズがありました。 Q. 診察なしで緊急避妊薬を入手できる国は? 日本、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア 性犯罪被害や避妊具の破損などが原因の望まない妊娠を回避するために、緊急避妊薬が用いられます(レポノルゲストレルがあり、服用が早いほど効果的とされています)。 答えは、 英国 なのだそうです。 (その他に、オレゴン州でも本年1月から、医師の処方箋なしで購入可能。) 日本では、処方箋が必要です。 さて、本日の私的なお勉強日記です。 今月のアルツハイマー病研究の専門ジャーナル(電子版)に、オメガ3系必須脂肪酸による高齢者での認知機能改善作用を示した臨床研究が、ドイツのグループ(Charité-Universitätsmedizin)から報告されていました。 (J Alzheimers Dis. 2016 Feb 10) アルツハイマー病では、臨床症状の発症の以前から病態の進行が推定されており、 機能性食品成分の作用として、βアミロイドの蓄積やタウタンパクリン酸化に対する介入の効果が期待されています。 先行研究では、 健常な高齢者における認知機能への作用の検出は容易ではないことから、結果にばらつきが示されています。 そこで、今回の研究では、 認知機能の指標として新たに開発された指標であるLOCATOを用いて、高齢者でのオメガ3系必須脂肪酸の作用が検証されました。 具体的には、 ランダム化二重盲検偽薬対照試験として、 認知機能が正常な被験者44名(うち女性20名、年齢は50−75歳)を対象に、 ・オメガ3系必須脂肪酸投与群 (2,200 mg/day, n = 22) ・偽薬投与群 (n = 22) の2群について、 26週間の介入が行われています。 介入の前後で、 主アウトカムとして 記憶能(OLM-task)、 副アウトカムとして、 言語認知機能指標(AVLT), 食習慣, オメガ-3-指数などが調べられました。 解析の結果、 まず、 オメガ3系必須脂肪酸投与群では、 偽薬投与群に比べて、 オメガ3インデックスの有意な増加が認められ、 認知機能指標(recall of object locations)において、 偽薬群に比べて、 実薬群で有意な改善が見出されました。 なお、AVLTにおけるパフォーマンスでは有意差は示されませんでした。 以上のデータから、 健康な高齢者において、 オメガ3系必須脂肪酸サプリメント投与による認知機能への好影響が示唆されます。 機能性食品・サプリメントの中で、ヒト臨床研究によって、認知症改善作用が示されているのは、次の成分です。 イチョウ葉エキスによる認知症への効果:メタ解析 イチョウ葉エキス イチョウ葉エキス製剤による認知症の症状改善作用 イチョウ葉エキスによる認知症改善効果@ドイツ イチョウ葉エキスの有効性と安全性 イチョウ葉エキス20年間摂取による認知機能低下抑制作用 イチョウ葉エキスと認知症治療薬のシナジー PS(ホスファチジルセリン)サプリメント PS(ホスファチジルセリン)による認知機能改善作用 エクストラヴァージン(バージン)オリーブオイル エクストラバージンオリーブオイルによる認知症予防効果 大豆イソフラボンによる認知機能改善効果@メタ解析 ・ビタミンB群 ビタミンB群投与による脳萎縮(灰白質萎縮)抑制効果と認知機能低下抑制効果 脳萎縮進行抑制効果を示した臨床研究 オメガ3系必須脂肪酸とαリポ酸によるアルツハイマー病の進行抑制効果 一般に、認知機能への効果を期待する場合には、ビタミンB群、オメガ3系脂肪酸(EPAやDHA)、イチョウ葉エキスといったサプリメントを比較的長期間(数ヵ月以上)に利用することが必要と考えられます。 また、ウコン・クルクミンによる認知症改善作用も報告されています。 DHCでは、複合サプリメントも製品化しています。 ------------------------------------------------------------------ サプリメントと医薬品の相互作用ハンドブック―機能性食品の適正使用情報 DHCが日本のサプリを健康にします。 医療関係者のための健康食品情報サイト【DHCサプリメント研究所】 【健康食品FAQ】 DHCが第1位@利用している(利用したい)メーカー(経産省の調査) ------------------------------------------------------------------ |
| posted at 23:56 | この記事のURL |
| オリーブポリフェノールによる酸化ストレス障害の抑制作用@脂質異常症 |
今日は、家に引きこもって、投稿していた論文(総説)の校正確認など、いろいろたまっていた仕事をしていました。 さて、本日の私的なお勉強日記です。 今月の農芸化学の専門ジャーナル(電子版)に、バージンオリーブオイル+オリーブポリフェノール投与により、脂質異常症患者における酸化ストレス軽減作用を示した臨床研究が報告されていました。 (J Agric Food Chem. 2016 Feb 18.) 近年の研究では、 単なるオリーブオイルではなく、 オリーブ由来のポリフェノールが豊富なエクストラバージンオリーブオイルのほうが、優れた機能性を有することが分かってきました。 今回の研究では、 脂質異常症患者において、 オリーブポリフェノール強化したバージンオリーブオイル あるいは、 タイム由来ポリフェノールを添加したバージンオリーブオイル投与によるDNA酸化障害および抗酸化能への作用が検証されました。 具体的には、 脂質異常症患者33名を対象に、 バージンオリーブオイル投与群(VOO群) オリーブポリフェノール(PC)強化したバージンオリーブオイル投与群(FVOO群) タイム由来ポリフェノールを添加したバージンオリーブオイル投与群(FVOOT群) の3群について、 介入の前後で、 DNAの酸化ストレス指標である8-OHdG値、抗酸化能の測定が行われています。 解析の結果、 FVOO投与により、 介入前に比べて、介入後に、8-OHdGの有意な減少(酸化ストレスの低下)が認められました。 また、 FVOOT投与でも、さらに顕著な8-OHdGの減少が示されました。 このとき、 オリーブポリフェノールおよびタイムポリフェノールに関連するバイオマーカーの増加が見出されています。 さらに、 抗酸化能の指標であるスーパーオキシドディスムターゼ (Superoxide dismutase, SOD)も、 FVOO投与およびFVOOT投与により有意な増加を示しました。 以上のデータから、 脂質異常症患者において、 オリーブポリフェノール強化バージンオリーブオイルによる抗酸化能の亢進、酸化ストレス障害の抑制作用が示唆されます。 近年の研究では、 単なるオリーブオイルではなく、 オリーブ由来のポリフェノールが豊富なエクストラバージンオリーブオイルのほうが、優れた機能性を有することが分かってきました。 ただし、日本では、JAS基準のオリーブオイルが出回っており、エクストラバージンオリーブオイルの品質が国際基準と比べて、高くありません。 エクストラバージンオリーブオイルの基準は、 IOC(国際オリーブ協会)では酸度0.8%以下、 JASの基準では酸度が2%未満です。 DHCのエクストラバージンオリーブオイルは、 酸度はわずか0.2%以下となっています。 地中海食は、スペインやギリシャ、南フランスなど地中海地方の伝統食です。 野菜や果物、全粒の穀類、種実類、オリーブオイルの利用が多いという特徴があります。 地中海食は、健康増進や疾病予防に有用であることが知られており、多くの研究によってエビデンスが示されています。 地中海食やオリーブオイルの効能については、多くのエビデンスが報告されています。 地中海食で死亡率が半減する 低炭水化物(糖質制限)食と地中海食は低脂肪食よりも有効 オリーブオイルの摂取10gで全死亡率が7%低下 地中海食がメタボを抑制 バージンオリーブオイルとナッツ類を含む地中海食の抗炎症作用 バージンオリーブオイルの心臓病予防作用 オリーブオイルによる皮膚の老化抑制作用 地中海食による認知症予防効果 地中海食+CoQ10サプリによる抗酸化作用 超低炭水化物・地中海食による減量効果 地中海食による高尿酸血症リスクの低下 オリーブオイルによる動脈硬化抑制作用 バージンオリーブオイルによる骨代謝改善作用 オリーブオイルとナッツによる心血管リスク低下作用 伝統的地中海食による脂質代謝改善作用 オリーブオイルによる膀胱がんリスク低下 ------------------------------------------------------------------ サプリメントと医薬品の相互作用ハンドブック―機能性食品の適正使用情報 DHCが日本のサプリを健康にします。 医療関係者のための健康食品情報サイト【DHCサプリメント研究所】 【健康食品FAQ】 DHCが第1位@利用している(利用したい)メーカー(経産省の調査) ------------------------------------------------------------------ |
| posted at 23:51 | この記事のURL |
| グルコサミン/コンドロイチンによる膝関節構造変化への働き:6年間のフォローアップ研究 |
今月の関節疾患研究の専門ジャーナル(電子版)に、グルコサミン/コンドロイチンサプリメントによる関節の構造への作用を調べた臨床研究が、カナダのグループ(University of Montreal)から報告されていました。 (Arthritis Care Res (Hoboken). 2016 Feb 16.) 今回の研究では、 グルコサミン+コンドロイチンサプリメントの併用での6年間の長期投与により、 関節の構造変化(関節軟骨容積)への働きが検証されました。 具体的には、 グルコサミンコンドロイチン含有サプリメントの摂取者1593名を対象に、 6年間の摂取後に、 試験開始時と比べて、関節間隙狭小化(1mm以上)について、MRIによる評価が行われています。 (OAI Progression and Incidence研究のサブコホートです。) なお、 被験者(1593名)は、 試験開始時において、半月板の突出の有無により、 (脛骨内側縁から 3 mm 以上、辺縁の突出を生じた半月板、いわゆるmeniscal extrusion) 突出を有する群429名のサブグループ解析が行われ、 また、投与期間で、 1年間、2−3年間、4−6年間での関節軟骨容積の変化が評価されています。 解析の結果、 グルコサミン+コンドロイチンサプリメント投与により、 関節軟骨容積の減少が有意に抑制されたということです (ヨンクヒール・タプストラ検定Jonckheere-Terpstra trend testにて統計処理) この関節軟骨保護効果は、投与期間に比例して見出されており、 6年間の投与期間中、2年以上の摂取により認められています。 以上のデータから、 グルコサミン+コンドロイチンサプリメントの長期投与による関節軟骨保護作用が示唆されます。 グルコサミンは、変形性膝関節症などの関節疾患に広く利用されているサプリメントです。 グルコサミンの有用性に関するエビデンス 作用メカニズムとして、アミノ糖であるグルコサミンが関節軟骨の成分であることから、構成成分を経口摂取することによる直接的な修復機構が想定されていました。 一方、最近の研究では、グルコサミンやコンドロイチンは、情報伝達機構における調節因子であることが示されており、変形性膝関節症に対する改善効果のメカニズムとして、構成成分自体を直接摂取する作用というよりは、シグナル伝達物質を摂取することによる作用が考えられています。 膝OAなどの変形性関節症に対して、 サプリメントでは、グルコサミンやコンドロイチンが最もエビデンスが豊富であり、欧州の学術団体EULARではグレードAの推奨になっています。 (一方、ACRではGAIT1のみを解析対象としたため、偽陰性データのバイアスによってネガティブになっています。) 2014年以降に発表された最新の研究―MOVES研究やLEGS研究--では、 グルコサミンやコンドロイチンの効果が示されています。 ------------------------------------------------------------------ サプリメントと医薬品の相互作用ハンドブック―機能性食品の適正使用情報 DHCが日本のサプリを健康にします。 医療関係者のための健康食品情報サイト【DHCサプリメント研究所】 【健康食品FAQ】 DHCが第1位@利用している(利用したい)メーカー(経産省の調査) ------------------------------------------------------------------ |
| posted at 23:54 | この記事のURL |
| マルチビタミンサプリメントが軽度認知障害(MCI)を改善 |
今月の看護学の専門ジャーナル(電子版)に、軽度認知障害(MCI)におけるマルチビタミンサプリメントの有用性を調べた臨床研究が、韓国のグループから報告されていました。 (J Nurs Scholarsh. 2016 Feb 15) 今回の研究では、 ケア施設の軽度認知障害(MCI)の高齢者において、 マルチビタミンサプリメント投与による認知機能、血中ホモシステイン値、うつ状態への影響が検証されました。 具体的には、 65歳以上でMCIの被験者48名を対象に、 マルチビタミンサプリメント介入群(24名) (ビタミンB6,B12,葉酸含有サプリメントを1日1回投与) 対照群(24名) の2群について、12週間の介入が行われています。 認知機能(MMSE)、血中ホモシステイン値、老年うつスケール(GDS)が測定されています。 解析の結果、 マルチビタミンサプリメント投与により、 認知機能の有意な改善、 (F = 3.624, p = .021) 血中ホモシステイン値の有意な改善、 (F = 6.974, p = .001) うつ状態の有意な改善 (F = 10.849, p = .001). が見出されたということです。 以上のデータから、 MCIの高齢者において、 マルチビタミンサプリメント(ビタミンB群)による認知機能の改善、血中ホモシステイン値の低下、うつ状態の改善が示唆されます。 機能性食品・サプリメントの中で、ヒト臨床研究によって、認知症改善作用が示されているのは、次の成分です。 イチョウ葉エキスによる認知症への効果:メタ解析 イチョウ葉エキス イチョウ葉エキス製剤による認知症の症状改善作用 イチョウ葉エキスによる認知症改善効果@ドイツ イチョウ葉エキスの有効性と安全性 イチョウ葉エキス20年間摂取による認知機能低下抑制作用 イチョウ葉エキスと認知症治療薬のシナジー PS(ホスファチジルセリン)サプリメント PS(ホスファチジルセリン)による認知機能改善作用 エクストラヴァージン(バージン)オリーブオイル エクストラバージンオリーブオイルによる認知症予防効果 大豆イソフラボンによる認知機能改善効果@メタ解析 ・ビタミンB群 ビタミンB群投与による脳萎縮(灰白質萎縮)抑制効果と認知機能低下抑制効果 脳萎縮進行抑制効果を示した臨床研究 オメガ3系必須脂肪酸とαリポ酸によるアルツハイマー病の進行抑制効果 一般に、認知機能への効果を期待する場合には、ビタミンB群、オメガ3系脂肪酸(EPAやDHA)、イチョウ葉エキスといったサプリメントを比較的長期間(数ヵ月以上)に利用することが必要と考えられます。 また、ウコン・クルクミンによる認知症改善作用も報告されています。 DHCでは、複合サプリメントも製品化しています。 ------------------------------------------------------------------ サプリメントと医薬品の相互作用ハンドブック―機能性食品の適正使用情報 DHCが日本のサプリを健康にします。 医療関係者のための健康食品情報サイト【DHCサプリメント研究所】 【健康食品FAQ】 DHCが第1位@利用している(利用したい)メーカー(経産省の調査) ------------------------------------------------------------------ |
| posted at 23:56 | この記事のURL |
| 2型糖尿病に対する朝鮮人参の有用性:メタ解析 |
今月の臨床医学のジャーナルに、2型糖尿病に対する朝鮮人参(高麗人参)の有用性を調べたメタ解析が報告されていました。 (Medicine (Baltimore). 2016 Feb;95(6):e2584.) 高麗人参(朝鮮人参)は、ウコギ科ニンジン属の生薬であり、中国伝統医学の処方や和漢薬として利用されてきました。 『日本薬局方』には、効能として虚弱体質の改善や肉体疲労の回復、病中病後の体力回復があげられています。 基礎研究では、抗酸化作用、抗ウイルス作用、抗ストレス作用、抗糖尿病作用、抗がん作用、循環改善作用などが示されてきました。 予備的な臨床研究では、認知機能の改善、心血管疾患の予防および改善、狭心症治療、脂質異常症改善、血糖コントロール改善、がん患者のQOL改善、勃起障害改善、運動耐用能改善などが示唆されています。 さて、今回のメタ解析では、 2型糖尿病あるいは耐糖能異常に対する朝鮮人参(高麗人参)サプリメント投与による作用が検証されました。 具体的には、 主要医学データベースから、 (Medline, Cochrane, Google Scholar) 2型糖尿病あるいは耐糖能異常に対する高麗人参を投与したランダム化比較試験が抽出され、 主アウトカムはHbA1c、 副アウトカムは空腹時血糖値、食後血糖値、空腹時インスリン値、インスリン抵抗性(HOMA−IR)、TG、総コレステロール、LDL、HDL値にて評価が行われました。 141報が抽出され、 8試験がメタ解析の対象となりました。 (被験者数、年齢、性別などは比較可能な試験ということです。) 解析の結果、 まず、HbA1cには両群間(人参投与群と対照群)に有意差は認められませんでした。 (pooled standardized difference in means = -0.148, 95% CI: -0.637 to 0.228, P = 0.355) 次に、、 高麗人参投与群にて、 空腹時血糖値、食後インスリン値、HOMA-IRの有意な改善が認められました。 なお、食後血糖値、空腹時インスリン値には両群間での有意差はありませんでした。 脂質代謝指標では、 TG値、総コレステロール、LDL値において、介入群での有意差が認められました。 (HDLでは有意な変化は示されていません。) その他、 経口血糖降下剤やインスリンによる治療を受けている患者では、 高麗人参投与による空腹時血糖の低下作用は見出されていません。 以上のデータから、 論文著者らは、 2型糖尿病あるいは耐糖能異常において、 高麗人参投与による糖代謝への好影響やインスリン抵抗性の改善が示唆される、と考察しています。 一般に、 高麗人参・朝鮮人参には、血糖降下作用はないと考えられますが、生体のホメオスターシスを保つ方向に作用することで、体質によっては、糖代謝改善作用が数値として認められるとも考えられます。 今回のメタ解析でも、糖尿病治療(経口血糖降下薬服用やインスリン治療)を受けている場合に、高麗人参を摂取しても、追加的な血糖降下は生じないということから、併用に際して、低血糖などのリスクは少ないと考えられます。 DHCでは、下記の製品を取り扱っています。 高麗人参 30日分 6年根の高麗人参に精製エキスを配合! バイタリティあふれる毎日に 通常価格 \1,270(税込\1,371) ------------------------------------------------------------------ サプリメントと医薬品の相互作用ハンドブック―機能性食品の適正使用情報 DHCが日本のサプリを健康にします。 医療関係者のための健康食品情報サイト【DHCサプリメント研究所】 【健康食品FAQ】 DHCが第1位@利用している(利用したい)メーカー(経産省の調査) ------------------------------------------------------------------ |
| posted at 23:53 | この記事のURL |
| マルチビタミンミネラルQ10による代謝亢進作用 |
今月の栄養学の専門ジャーナルに、マルチビタミンミネラル+Q10サプリメント投与によって、タスク負荷時におけるエネルギー消費量の増大と脳血流量の増加を示した臨床研究が、欧州(イギリスとスイス)のグループから報告されていました。 (Nutr Metab (Lond). 2016 Feb 11;13:11) 脳の神経活動において、エネルギー消費や脳血流循環が活発に行われます。 それらの代謝活動には、適切な微量栄養素が必須です。 今回の研究では、 マルチビタミンミネラル+コエンザイムQ10サプリメントの投与により、 難易度の異なる認知機能へのタスク負荷時での、代謝や脳血流への影響が検証されました。 具体的には、 ランダム化二重盲検偽薬対照試験として、 健常者(25−49歳の女性)を対象に、 (106名の被験者が参加し、56日目に87名から解析の対象となるデータ取得) ・偽薬 あるいは ・マルチビタミンミネラル(用量は2通り)のいずれかが投与され、 前頭葉の脳血流量関連指標(NIRS)、 全エネルギー消費量、 炭水化物酸化/脂質酸化比が、 難易度による段階に分けられた認知負荷試験と、対照群の負荷タスク下にて測定されています。 評価は、 8週間のサプリメント投与後に行われました。 解析の結果、 認知機能タスク負荷時に、 総エネルギー消費量、脂質酸化は、サプリメントの用量依存的に亢進が認められたということです。 マルチビタミンミネラルQ10サプリメントの初回投与時から、高用量投与時にいたるまで、用量依存性が示されています。 また、脳血流の指標となるヘモグロビン濃度も、タスク付加時において、ビタミンミネラルQ10サプリメント投与による上昇が見出されました。 8週間にわたるサプリメント投与により、 用量依存的な総エネルギー消費量の増加が見出されました。 ただし、気分や認知機能の指標では有意差は見出されていません。 以上のデータから、 健常者において、 マルチビタミンミネラルコエンザイムQ10サプリメント投与により、 認知機能負荷タスク時のエネルギー消費量増大、脳血流増加作用が示唆されます。 今回は、健常者が対象となっていますので、感情や認知機能の指標での変化までは検出されていません。 また、マルチビタミンミネラルQ10(コエンザイムQ10は4.5mgと低用量)サプリメントのため、介入効果としても大きくはないことから、検出力不足であったと考えられます。 したがって、未病の状態の被験者における臨床的意義の検証が期待されます。 DHCでは、適正な価格で高品質のマルチビタミン、マルチミネラル、カルシウム・マグネシウムを提供しています。 中高年以上の疾病予防・健康増進のためには、 下記のサプリメントは、すべてベーシックサプリメントとして摂取が推奨できます。 すべての摂取にかかるコストは1か月分で、2,000円程度から、ですので、 安全性・有効性に加えて、経済性(費用対効果)にも優れています。 マルチビタミン、 (マルチビタミン 徳用90日分 \886(税込\956)) ⇒1ヵ月分は約300円。 マルチミネラル、 (マルチミネラル 徳用90日分【栄養機能食品(鉄・亜鉛・マグネシウム)】\1,239(税込\1,338)) ⇒1ヵ月分は約450円。 ビタミンC ハードカプセル(1,000mg) (ビタミンC(ハードカプセル)徳用90日分【栄養機能食品(ビタミンC・ビタミンB2)】\629(税込\679)) ⇒1ヵ月分は約210円。 ビタミンD3 (ビタミンD3 30日分 \286(税込\308)) ⇒1ヵ月分は約300円。 コエンザイムQ10、 (コエンザイムQ10 包接体 徳用90日分 通常価格\2,143(税抜)) ⇒1ヵ月分は約700円。 ↑ 上記は、合計で一か月分が約2,000円ほどです。中高年以上の全員に推奨できるベーシックな成分です。 ↓ 下記の成分は、上記に加えて追加する場合に、優先されるサプリメントです。 EPA、 (EPA 30日分 \950(税込\1,026)) DHA、 (DHA 30日分 \1,191(税込\1,286)) 乳酸菌 (届くビフィズス 30日分 通常価格 \1,429(税抜)) ------------------------------------------------------------------ サプリメントと医薬品の相互作用ハンドブック―機能性食品の適正使用情報 DHCが日本のサプリを健康にします。 医療関係者のための健康食品情報サイト【DHCサプリメント研究所】 【健康食品FAQ】 DHCが第1位@利用している(利用したい)メーカー(経産省の調査) ------------------------------------------------------------------ |
| posted at 23:54 | この記事のURL |
| チョコレートの摂取が認知機能に好影響を与える:Maine-Syracuse縦断研究 |
今月の摂食行動研究の専門ジャーナル(電子版)に、チョコレートの摂取と認知機能との関連を調べた疫学研究が、米国のグループ(University of Maine)から報告されていました。 (Appetite. 2016 Feb 9.) チョコレートには、カカオ(ココア)ポリフェノールが含まれており、抗炎症作用や抗酸化作用を介した機能性が知られています。 これまでの疫学研究や臨床試験では、高血圧症の改善、心血管疾患(動脈硬化性疾患)リスクの低減、抗がん作用などが報告されています。 特に、ダークチョコレートによる心血管リスク提言作用は確立しているといいでしょう。 一方、カカオポリフェノールによる認知期のへの作用は明確ではありません。 そこで、今回の研究では、 チョコレートの摂取と、認知機能との関連が検証されました。 具体的には、 横断研究として、 地域居住の被験者968名(23-98歳)を対象に、 習慣的なチョコレートの摂取と、 認知機能関連指標との関係が調べられています。 (Maine-Syracuse Longitudinal Study (MSLS)という縦断研究の一環です。) 解析の結果、 チョコレートの摂取が多いほど、 認知機能の指標への好影響が認められたということです。 好影響が認められた認知機能関連指標は、 Global Composite score, Visual-Spatial Memory and Organization, Working Memory, Scanning and Tracking, Abstract Reasoning, MMSE の各指標です。 この相関は、心血管イベントやライフスタイル、食事因子といった交絡因子による補正後でも減弱しませんでした。 (なお、MMSEは減弱しており、それ以外の指標。) 以上のデータから、 カカオポリフェノールによる認知機能への好影響が示唆されます。 今後、介入試験による検証が期待される分野です。 チョコレートの機能性について、次のような研究が知られています。 病棟でのチョコレートの生存期間 ダークチョコレートによる脂質代謝改善作用@隠れ肥満女性 ダークチョコレートで歩行距離が改善 チョコレートの摂取と脳卒中リスクの低下:前向き研究とメタ解析 ダークチョコレートによる血管内皮機能改善作用 小児の血圧とダークチョコレート ココアによる抗炎症作用@肥満症 ココア飲料が善玉コレステロールを増加 健康増進・疾病予防という目的では、カカオの含有量が多いダークチョコレートの摂取がポイントです。 また、ココアパウダーを用いたココア飲料では、糖分の過剰摂取に注意が必要です。 チョコレートポリフェノール/フラボノイドによる高血圧改善効果は、メタ解析でも示されています。 DHCでは、 「おいしい食品カテゴリ」で、チョコレート製品を取り扱っています。 ------------------------------------------------------------------ サプリメントと医薬品の相互作用ハンドブック―機能性食品の適正使用情報 DHCが日本のサプリを健康にします。 医療関係者のための健康食品情報サイト【DHCサプリメント研究所】 【健康食品FAQ】 DHCが第1位@利用している(利用したい)メーカー(経産省の調査) ------------------------------------------------------------------ |
| posted at 23:53 | この記事のURL |
| 減量による膝関節症リスク低減効果 |
今月の関節疾患研究の専門ジャーナル(電子版)に、減量による膝関節症リスク低減効果を示した臨床研究が、オランダのグループから報告されていました。 (Arthritis Care Res (Hoboken). 2016 Feb 11.) 今回の研究では、 中年期の肥満女性での減量により、 膝関節症の発症率への影響が検証されました。 具体的には、 臨床的にも放射線学的にも膝OAを有していない肥満女性353名を対象に、 テイラーメイドの食事療法と運動療法、グルコサミン硫酸塩の経口投与を行い、 目標の減量幅である5kg減量ありは5%の減量のいずれかを達成した群と、達成しなかった群の2群について、 30ヶ月後の膝OA発症が調べられています。 (PROOF研究の一環です。) (OA発症率は、ACRクライテリア、KLグレード、関節間隙狭小化1.0 mm以上といった基準で判断されています。) 解析の結果、 膝OAの発症率は、 減量群では、非減量群に比べて有意な低下が認められたということです。 (15% vs. 20%; OR 0.5, 95% CI 0.3 - 0.9) また、 血糖値や体脂肪率、血圧といった健康指標は、減量により改善が示されました。 以上のデータから、 中年期の肥満女性では、 30ヶ月の期間において、5kg以上あるいは5%以上の減量による膝関節症リスク低下作用が示唆されます。 なお、PROOF研究では、グルコサミンサプリメントの有用性が示されています。 グルコサミンは、変形性膝関節症などの関節疾患に広く利用されているサプリメントです。 作用メカニズムとして、アミノ糖であるグルコサミンが関節軟骨の成分であることから、構成成分を経口摂取することによる直接的な修復機構が想定されていました。 一方、最近の研究では、グルコサミンやコンドロイチンは、情報伝達機構における調節因子であることが示されており、変形性膝関節症に対する改善効果のメカニズムとして、構成成分自体を直接摂取する作用というよりは、シグナル伝達物質を摂取することによる作用が考えられています。 膝OAなどの変形性関節症に対して、 サプリメントでは、グルコサミンやコンドロイチンが最もエビデンスが豊富であり、欧州の学術団体EULARではグレードAの推奨になっています。 (一方、ACRではGAIT1のみを解析対象としたため、偽陰性データのバイアスによってネガティブになっています。) 2014年以降に発表された最新の研究―MOVES研究やLEGS研究--では、 グルコサミンやコンドロイチンの効果が示されています。 ------------------------------------------------------------------ サプリメントと医薬品の相互作用ハンドブック―機能性食品の適正使用情報 DHCが日本のサプリを健康にします。 医療関係者のための健康食品情報サイト【DHCサプリメント研究所】 【健康食品FAQ】 DHCが第1位@利用している(利用したい)メーカー(経産省の調査) ------------------------------------------------------------------ |
| posted at 23:54 | この記事のURL |
| グルコサミンの有用性に関するエビデンス |
今日は、第12回ファンクショナルフード学会でした。 (旧グルコサミン研究会です。) 今日の講演の中では、関節軟骨の破壊と再生機構に関する研究が興味深い内容でした。 変形性膝関節症の予防/リスク低減や症状の改善を訴求する機能性食品成分の中では、グルコサミンが最もエビデンスレベルが高いと思います。 グルコサミンは、抗炎症作用、軟骨細胞でのシグナル伝達作用、長寿関連遺伝子活性化など多彩な作用を有しており、基礎研究から臨床試験、疫学研究まで多くの知見が集積されています。 これに対して、医薬品は、消炎鎮痛薬ですので、短期的にNSAIDsを利用することはあるとしても、長期間の投与は不適切です。 中期的、長期的な有効性や安全性を考慮し、エビデンスを俯瞰するとき、変形性関節症の予防/リスク低減の目的で、グルコサミン(1500m〜)の利用が推奨されます。 グルコサミンの膝OA(変形性膝関節症)に対する有効性は、2001年のランセットに報告された臨床研究によって、広く知られるようになりました(Reginster)。 その後、多くの研究によって、グルコサミンによる膝OAへの有効性が示されています。 一方、否定的な研究も散見され、特に2006年のGAIT研究が、その後のメタ解析の結果にネガティブなバイアスを与えるようになりました(Clegg)。 しかし、2014年以降に報告された最新の研究では、グルコサミンによる膝OAへの有効性が支持されています。 具体的には、 2014年のLEGS研究や2015年のMOVES研究などがあります(Fransen、 Hochberg)。 なお、GAIT研究は、プロトコールに問題が指摘されており、偽陰性のデータです。 グルコサミンの投与量は、一般に1,500mg/日です。 臨床試験では、1,000mg〜3,000mgの投与例があります。 硫酸塩に関して、臨床試験での投与期間は、4週間から3年間でした。 グルコサミンの血中濃度は、単回投与のほうが、分3による投与よりも高くなることが示されており、グルコサミンは単回投与が推奨されます(Persiani)。 また、前述のように、グルコサミンサプリメントの経口投与後、血液中および関節液(滑液)中にグルコサミンが検出されます(Pastorini)。 近年、グルコサミンの働きが、アンチエイジングの分野でも注目されるようになりました。 まず、米国での5年間のコホート研究では、77,719名を対象に、10年間のサプリメント摂取と死亡率が検証され、グルコサミンあるいはコンドロイチンの摂取と17%の死亡率低下との相関が示されています(Pocobelli)。 また、グルコサミン摂取と18%の死亡率低下、コンドロイチン摂取と14%の死亡率低下というデータも知られています(Bell)。 NHANES研究では、グルコサミンやコンドロイチンの摂取によるCRPの低下が認められました(Kantor)。 DHCでは、関節機能訴求に関連したサプリメントとして、次の製品を扱っています。 パワーグルコサミン 極らくらく らくらく(グルコサミン、コンドロイチン、II型コラーゲン、CBP、MSM(メチルスルフォニルメタン)、コラーゲンペプチド、ヒドロキシチロソール) グルコサミン コンドロイチン グルコサミン&コンドロイチン II型コラーゲン+プロテオグリカン ------------------------------------------------------------------ サプリメントと医薬品の相互作用ハンドブック―機能性食品の適正使用情報 DHCが日本のサプリを健康にします。 医療関係者のための健康食品情報サイト【DHCサプリメント研究所】 【健康食品FAQ】 DHCが第1位@利用している(利用したい)メーカー(経産省の調査) ------------------------------------------------------------------ |
| posted at 23:54 | この記事のURL |
| アロマセラピーオイルマッサージによるむずむず脚症候群改善作用 |
看護学の専門ジャーナルに、アロマセラピーのラベンダーオイルマッサージによる慢性維持透析患者でのむずむず脚症候群改善作用を示した臨床研究が、イランのグループから報告されていました。 (Nurs Midwifery Stud. 2015 Dec;4(4):e29617.) 慢性維持透析患者では、多くの不定愁訴や合併症が生じ、それらの対策として、さまざまな補完代替医療の併用が行われています。 むずむず脚症候群(RLS; Restless legs syndrome, 下肢静止不能症候群、不穏下肢症候群)も、透析患者によく認められる症状であり、QOLの低下や睡眠障害が問題となります。 今回の研究では、 慢性維持透析患者に認められるむずむず脚症候群に対して、アロマセラピーのエッセンシャルオイルを用いたマッサージの作用が検証されました。 具体的には、 ランダム化比較試験として、 むずむず脚症候群(RLS)を有する人工透析患者70名を対象に、 (18−65歳で6か月間以上の透析期間、1週間に2回以上透析実施) ・ラベンダーオイルを用いたマッサージ施行群(35名) ・対照群(通常のケア実施群)(35名) の2群について3週間の介入が行われています。 介入は、1週間に2回、10分間以上、3週間で、 1.5%濃度のラベンダーオイルを10−15ml利用して、トレーニングを受けた看護師により行われました。 解析の結果、 まず、 試験開始時には、 RLSスコアに関して、両群間に有意差は認められていません。 (22.41 ± 7.67 vs. 22.90 ± 4.38, P = 0.76) 次に、 試験終了時には、 RLSスコアは、介入群において、有意に減少したのに対して、 対照群では変化は示されませんでした。 (12.41 ± 5.49 vs. 23.23 ± 4.52, P < 0.0001). 以上のデータから、 慢性維持透析患者でのRLS(むずむず脚症候群)に対して、ラベンダーオイルマッサージの補完療法としての有用性が示唆されます。 最近の研究では、 アロマセラピー+マッサージによる乳がん患者のQOL改善作用 アロマセラピーによる認知症改善作用 ベルガモット精油アロマセラピーによるストレス軽減効果 月経困難症に対するアロマセラピーの効果 アロマセラピーによるストレス軽減効果:メタ解析 アロマセラピーによる術後の鎮痛効果 アロマセラピーによるストレス軽減効果@看護師 アロマセラピーによる掻痒改善効果@慢性維持透析患者 も示されています。 なお、 日本では、アロマセラピーの精油(エッセンシャルオイル)は雑貨扱いになっており、 品質が玉石混淆です。 したがって、一定以上の品質を有する、質の高いアロマセラピー製品を選ぶ必要があります。 DHCでは、アロマセラピーの関連製品を扱っています。 ------------------------------------------------------------------ サプリメントと医薬品の相互作用ハンドブック―機能性食品の適正使用情報 DHCが日本のサプリを健康にします。 医療関係者のための健康食品情報サイト【DHCサプリメント研究所】 【健康食品FAQ】 DHCが第1位@利用している(利用したい)メーカー(経産省の調査) ------------------------------------------------------------------ |
| posted at 23:54 | この記事のURL |
| グルコサミンが変形性膝関節症を予防する:PROOF研究 |
関節疾患研究の専門ジャーナル(電子版)に、肥満女性において、グルコサミンサプリメント投与による変形性膝関節症リスク低減(予防)効果を示した臨床研究が、欧州(オランダ・ベルギー・イタリア)のグループから報告されていました。 (Semin Arthritis Rheum. 2015 Nov 19.) 今回の研究では、グルコサミンサプリメントによる肥満女性での変形性膝関節症の予防効果が検証されました。 (PROOF研究の一環です。) (PRevention of knee Osteoarthritis in Overweight Females study) 具体的には、 BMI27以上の肥満女性407名(50-60歳)を対象に、 (変形性膝関節症と診断されていない健常者の肥満女性が対象です) (1) 対照群102名(食事運動の指導はなく、偽薬投与) (2) テイラーメイドの食事と運動療法+偽薬投与群:101名、 (3) グルコサミン硫酸塩投与+食事運動非介入群:102名 (4) グルコサミン硫酸塩投与+テイラーメイドの食事と運動療法実施群:102名 の4群について、2.5年間のフォローアップが行われました。 アウトカムとして、 膝関節の標準撮影が介入前後で測定されています。 (MTP view) グルコサミン投与群は、 グルコサミン硫酸塩として1日あたり1500mgが1回投与されました。 (偽薬との二重盲検試験です。) 膝OA(変形性膝関節症)の発症は、関節間隙狭小化(≥1mm)にて判断されています。 解析の結果、 2.5年後に、 対照群では、11.8%の被験者が膝OAと診断されました。 グルコサミン投与の2つの群では、食事療法との併用の有無に関わらず、 膝OA発症率の低減(予防効果)が見出されています。 テイラーメイドの食事運動療法のみの群では、リスク低減効果は示されませんでした。 次に、 グルコサミンの投与群(204名)と、非投与群(203名)の比較では、 グルコサミン投与により膝OAの発症リスクが59%有意に低下していました。 (関節間隙による評価:OR = 0.41, 95% CI: 0.20-0.85, P = 0.02) なお、 テイラーメイドの食事と運動療法実施群203名と、非実施群204名の比較では有意さは認められていません。 以上のデータから、 中高年の肥満女性において、 グルコサミンサプリメント(硫酸塩1500mg/日)の2年半の投与により、 変形性膝関節症の新規発症リスク低減効果が示唆されます。 今回の研究では、mJSN関節間隙が指標となっており、客観性が担保されています。 また、食事と運動の介入群では、有意な予防効果は見出されておらず、減量の有用性が期待よりも大きくなかったと考えられます。 これまで、グルコサミンは有病者への介入による有効性を示したデータが多かったのですが、今回は、予防的な意義を示したことに意義があると考えます。 DHCでは、関節機能訴求に関連したサプリメントとして、次の製品を扱っています。 パワーグルコサミン 極らくらく らくらく(グルコサミン、コンドロイチン、II型コラーゲン、CBP、MSM(メチルスルフォニルメタン)、コラーゲンペプチド、ヒドロキシチロソール) グルコサミン コンドロイチン グルコサミン&コンドロイチン II型コラーゲン+プロテオグリカン グルコサミンは、変形性膝関節症などの関節疾患に広く利用されているサプリメントです。 作用メカニズムとして、アミノ糖であるグルコサミンが関節軟骨の成分であることから、構成成分を経口摂取することによる直接的な修復機構が想定されていました。 一方、最近の研究では、グルコサミンやコンドロイチンは、情報伝達機構における調節因子であることが示されており、変形性膝関節症に対する改善効果のメカニズムとして、構成成分自体を直接摂取する作用というよりは、シグナル伝達物質を摂取することによる作用が考えられています。 膝OAなどの変形性関節症に対して、 サプリメントでは、グルコサミンやコンドロイチンが最もエビデンスが豊富であり、欧州の学術団体EULARではグレードAの推奨になっています。 (一方、ACRではGAIT1のみを解析対象としたため、偽陰性データのバイアスによってネガティブになっています。) 2014年以降に発表された最新の研究―MOVES研究やLEGS研究--では、 グルコサミンやコンドロイチンの効果が示されています。 ------------------------------------------------------------------ サプリメントと医薬品の相互作用ハンドブック―機能性食品の適正使用情報 DHCが日本のサプリを健康にします。 医療関係者のための健康食品情報サイト【DHCサプリメント研究所】 【健康食品FAQ】 DHCが第1位@利用している(利用したい)メーカー(経産省の調査) ------------------------------------------------------------------ |
| posted at 23:52 | この記事のURL |
| ヴィーガン食は全がんリスクを15%低下させる:メタ解析 |
今月の食物科学の専門ジャーナル(電子版)に、ベジタリアン食およびヴィーガン(ビーガン食)による健康アウトカムへの影響を検証したメタ解析が、イタリアのグループから報告されていました。 (Crit Rev Food Sci Nutr. 2016 Feb 6) 今回の研究では、 ベジタリアン食、ヴィーガン食と 慢性疾患リスク、全死亡率、主要疾患別の死亡率が調べられました。 具体的には、 主要医学データベースを用いて、 (Medline, EMBASE, Scopus, The Cochrane Library, Google Scholar) 横断研究86報 前向きコホート研究10報が抽出されました。 解析の結果、 まず、 非ベジタリアン食に比べて、 ベジタリアン食およびヴィーガン食では、 BMIの有意な減少、総コレステロール値、LDL値、血糖値の有意な低下が見出されました。 前向きコホート研究からのデータ解析によると、 虚血性心疾患の罹患率および死亡率が25%低下、 (RR 0.75; 95% CI, 0.68 to 0.82) 全がん罹患率が8%低下、 (RR 0.92; 95% CI 0.87 to 0.98) という相関が見出されています。 なお、心血管疾患及び脳血管疾患、全死亡率、がん死亡率、部位別のがんでは有意な関連は示されていません。 ヴィーガン食に関する解析では、 全がん死亡率の15%低下という相関が示されました。 (RR 0.85; 95% CI, 0.75 to 0.95) 以上のデータから、 ベジタリアン食による虚血性心疾患の罹患率及び死亡率の25%低下、 全がん罹患率の8%低下、 ヴィーガン食による全がん罹患率の15%低下作用が示唆されます。 これまでの多くの研究によって、ベジタリアン食摂取群では、非ベジタリアン食摂取群よりも、生活習慣病リスクが低いことが知られています。 ベジタリアン食による心血管疾患リスク低下作用 ベジタリアン食による血圧低下作用@メタ解析 なお、ベジタリアン食であれば何でも健康的になる、というわけではありません。 (例えば、野菜はナシで、パスタにチーズ、パンの組み合わせでも、ラクトオボにはなりますが。) もちろん、栄養学的にバランスの取れた、適切なベジタリアン食を摂取することが重要です。 一般に、植物性食品の摂取が多いベジタリアン食では、ファイトケミカル・ポリフェノールの摂取が多く、抗酸化作用を介した生活習慣病の予防効果が想定されます。 北米の栄養士会が共同で発表した見解によると、「適切に準備されたベジタリアン食は、健康に有益であり、必要な栄養素を満たしており、いくつかの疾患の予防や治療にも利点がある」とされています。 実際、これまでの疫学研究によって、肉食をする人々に比べて、ベジタリアンでは生活習慣病が少ないことが示されています。 ベジタリアン食による具体的な効果として、肥満、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患、高血圧、脂質異常症、糖尿病、前立腺がん、大腸がんの発症リスクが低下します。 また、日本人ベジタリアンを対象にした調査でも、ベジタリアンは、非ベジタリアンと比べて、体格指数(BMI)、血圧、血中総コレステロール値、中性脂肪値が有意に低いことが見出されています。 DHCでは、良質の植物性食品として、 次のような関連製品を取り扱っています。 DHC発芽玄米 DHC発芽玄米麺 エクストラバージンオリーブオイル ところで、最近の研究によって、糖質制限食・低炭水化物食よる減量・ダイエット効果や2型糖尿病での血糖コントロール改善効果が明らかとなっています。 また、 植物性たんぱく質および植物性脂質による心臓病リスク低減作用が知られています。 医学的に適切ではない糖質制限食のパターンとして、「糖質制限食・低炭水化物食では、‘焼き肉・ステーキ’食べ放題」があります。 動物性たんぱく質や動物性脂質の過剰摂取は、心血管疾患リスクを高めることが懸念されます。 植物性食品をベースにした糖質制限食・低炭水化物食による体重と脂質代謝への効果として、 エコアトキンスダイエットの減量と脂質代謝改善作用 といった研究もあります。 DHCでは、 肥満・糖尿病・アンチエイジング・ヘルシーエイジング(健康長寿)のための食事として、 「‘ゆるやか’糖質制限」(緩やかな糖質制限食・低炭水化物食)を推奨しています。 最新の科学的根拠を俯瞰すると、 「緩やかな糖質制限食・低炭水化物食」を基本とした食生活が、 「ヘルシーエイジング(健康長寿)」 「ダイエット(適正体重の維持)」 「アンチエイジング(抗加齢)」 に有用であると考えられます。 ------------------------------------------------------------------ サプリメントと医薬品の相互作用ハンドブック―機能性食品の適正使用情報 DHCが日本のサプリを健康にします。 医療関係者のための健康食品情報サイト【DHCサプリメント研究所】 【健康食品FAQ】 DHCが第1位@利用している(利用したい)メーカー(経産省の調査) ------------------------------------------------------------------ |
| posted at 23:53 | この記事のURL |
| 次へ
|